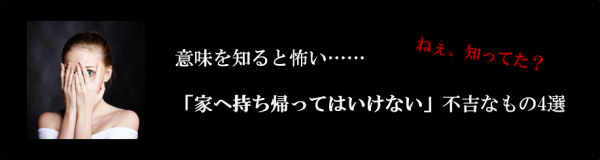「夫は、謝らなかったし一度も説明せず逃げていった。信頼を何度も踏みにじられ、本当にどん底でした」
執筆のきっかけのひとつは、ある女性カメラマンが放ったひと言。〈あなたのご主人、あなたのお金で好き勝手出来て、本当に良かったわね〉
「そのとき感じた苦しみは、怒りや悲しみから来たというより『それ、本当ですか、本当によかったですか』という疑問です。あの1秒後からずーっと心の中から消えません。結婚生活という言葉があるなら、離婚生活という言葉も成立するだろう。離婚というたった2文字では表せない関係が始まるのだ。一生一度の大ネタ、仕留めなければ私はもの書きではない。そう思いました。とはいえ発表のあてがあったわけではなかったんです」
つてをたどって、文芸誌に表題作の掲載が決まった。鈴木さんは、2年半ほどの日々を本作だけに懸けた。
4話の連作形式。表題作に続く、「ガスコンロとわたし」「亀とわたし」「チュールとわたし」というタイトルからは、どんなエピソードが織り込まれているか見当もつかないだろうが、ここでは触れない。だが、〈わたしが心配して何か尋ねると、「君は知らなくていいから」(略)でも毎回、後から起こる不都合な結果だけを突然押しつけられるのでした〉という部分から察してほしい。
一方で、鈴木さんが決して恨みつらみから書いたわけではないのもわかる。夫失格、父親失格ではあっても、作品には敬意を払い、子どもたちからは慕われていたこと、ときには徹底的に妻の味方をしてくれたことにも触れているからだ。
「どういう結末になるかわからないまま書き始めましたが、元夫がこんなに早く死ぬとは思いませんでした。ただ、彼が死んだことで、他人の残酷さや無責任さ…それをよく考えましたね。あの霊安室には、いい気になっている他人が大勢いました」
だが、告別式の翌朝、鈴木さんは、元夫のためにある決意をするのだ。死んでなお深い「夫婦」という業を、あなたはどう読むだろう。

『おめでたい女』 執筆に際しては、来る日も来る日も、カバーにある寺門孝之さんの絵を、書きものもするダイニングテーブルに置いてじっと見ていたという。小学館 1500円
※『anan』2017年12月6日号より。写真・土佐麻理子(鈴木さん) 水野昭子(本) インタビュー、文・三浦天紗子
(by anan編集部)
【人気記事】
※いい女は寝る前にアレを枕元に置く!? 横澤夏子が解説