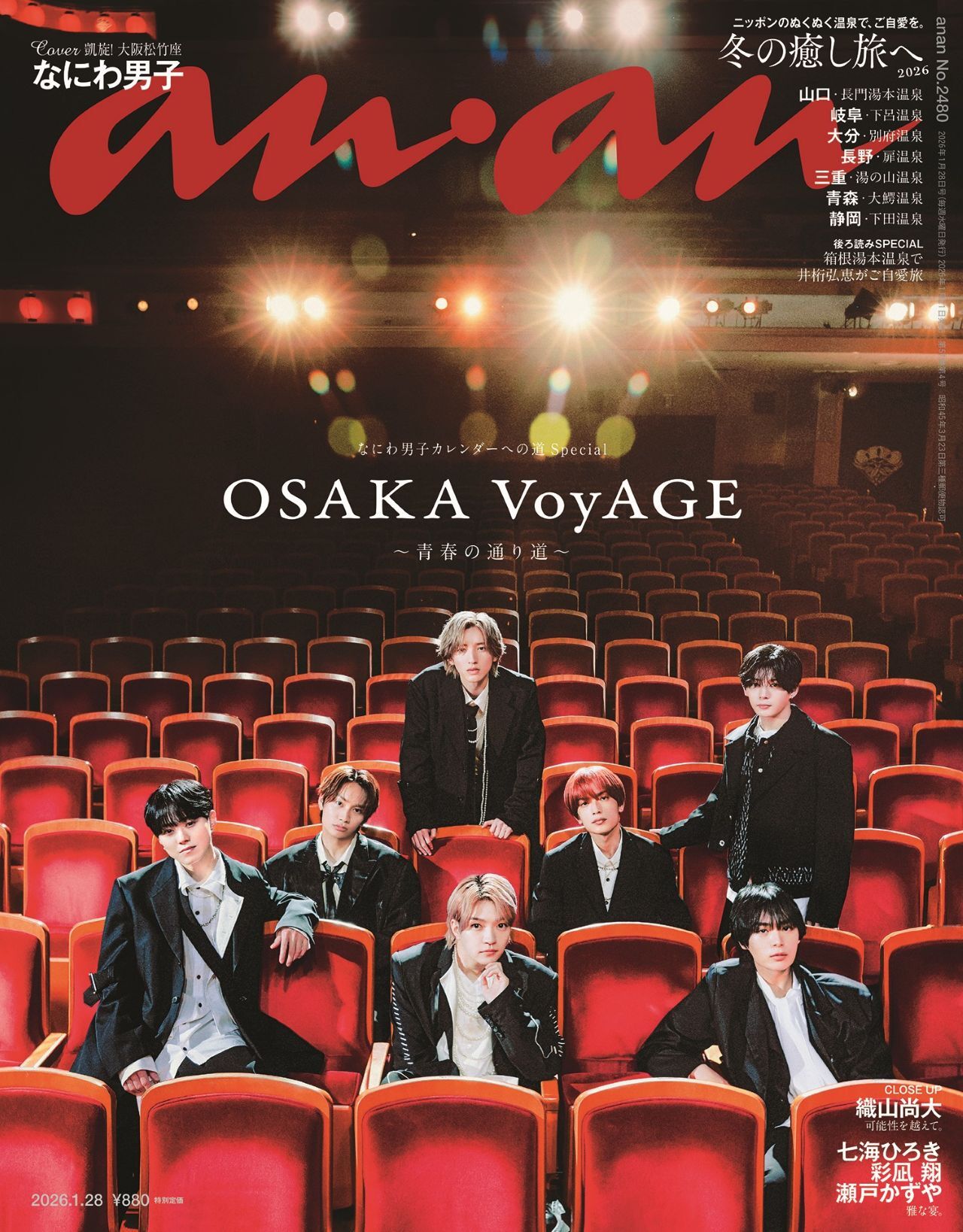今回は、プライベート編。友達や家族など、お互いのことを知っている近しい間柄だからこそ、深入りせずに尊重し合うべきときもあれば、相手のために言ってあげたほうがいいときも。よい関係を続けるための秘訣って?
お悩みに答えていただいたおふたり
犬山紙子さん
いぬやま・かみこ イラストエッセイスト。著書に『私、子ども欲しいかもしれない。』『女の子に生まれたこと、後悔してほしくないから』など多数。
Pocheさん
ポッシュ 心理カウンセラー。人間関係、親子問題、機能不全家族などが専門。著書に『あなたはもう、自分のために生きていい』『SNSのモヤモヤとの上手なつきあい方』など。
お悩み ①|推し活のモヤモヤ…

仲のいい友達が、私の好きなアニメにハマりました。最初は嬉しかったけど、作品の解釈やオタクとしての姿勢が合わずにモヤモヤ。友達としては好きなので変わらず仲良くしたいのですが…。

A. 「趣味の話は短く切り上げふだんの関係を大切に」(Poche)
好きなアニメだからこそ、無理に相手の価値観に合わせたり、“同じ温度”で語り合おうとすると、かえってストレスが溜まってしまうこともあります。話をする楽しみよりストレスのほうが大きいと感じたら、趣味の話は短く切り上げ、ふだんの関係を大切にする。そのバランスが、心地よい友情を長く保つコツです。無理に合わせて疲れるより、お互いにとって心地よい距離感を保つことで、関係はむしろ長く続きやすくなります。
A. 「アカウントはこっそりミュートしても」(犬山)
オタクとしてこれは大問題。私なら、友人が推し作品について言及しているSNSのアカウントはミュートしつつ、今まで通りの付き合いを続けると思います。ただし直接語ってきたら、否定せずに尊重してあげましょう。“好き”の気持ちは大切なものなので。もし友人が暴走してファンダムのマナー違反なことをやっているのであれば、「自分も昔、こういう失敗をしちゃったんだよね」とやんわり気づかせてあげるのも優しさです。
お悩み ②|“受動的攻撃”を受けたら…

はっきり自分の意思を言わず人を攻撃する“受動的攻撃”タイプが身近にいます。たとえば「ランチはこのお店でいい?」と聞いたとき、「いいよ」と言うのに、お店に入ると嫌そうに溜め息をついたり、こちらの罪悪感を刺激してきます。どう対応するべきですか?

A. 「相手に振り回されず距離を取るのも大切」(Poche)
受動的攻撃をする人は、こちらに「悪いことをしたかも」と思わせることで、不満を間接的に伝えようとしている可能性があります。大切なのは、相手の態度に過剰に振り回されないこと。なぜなら、こちらが毎回気を遣いすぎて対応してしまうと、「この人は受け止めてくれる」と思われ、今後も同じような受動的攻撃に巻き込まれやすくなってしまうからです。必要以上に責任を感じず、距離を取るのも、自分を守る大切な対応です。
A. 「はっきり言ってあげるかその人に選択させてみて」(犬山)
不機嫌で人を動かそうとするのは、子どもっぽい行為ですよね。実は私も学生時代、姉に対して似たような態度をとって注意された経験が。自分が甘えきっていたことに、指摘されて初めて気がつきました。注意できる間柄なら、本人のためにもはっきり言ってあげましょう。おかげで変わることのできた人間が、ここにいますから(笑)。それが難しいようなら、「今回はあなたが決めて」と自分で選択させるのもありだと思います。
お悩み ③|親友って必要?

友達付き合いは「広く浅く」タイプです。気づいたら、腹を割って話せる友人がいないことにハッとしました。深い付き合いの友達もいたほうがいいですか?

A. 「必要だと思うなら“お試し”してみるのも」(犬山)
ひとりが好きな人もいるので、こればかりは人によると思いますが、親友でなくても家族や恋人など、もしものときSOSを出せる人は誰かしらいたほうが安心かもしれません。もし親友が欲しいと思うなら、“深い付き合い”が自分に合っているかどうか試してみるのも。仲を深めていく過程でお互いの自己開示を受け入れ、愛情を持って接することができるようなら、その人との関係はきっと人生の宝物になっていくと思いますよ。
A. 「焦って作ろうとせず“育てて”みては」(Poche)
「広く浅く」の関係を築いてきたのは、それが今のあなたにとって心地よく、自分を守るバランスだったということでもあるので、無理にスタイルを変えようと焦る必要はありません。深い付き合いは“作るもの”というより、“育っていくもの”。広く浅くたくさんの人と関わるなかで、「この人とはもっと話してみたいな」と思える誰かと、少しずつ距離が近づいて、深い付き合いになることもある…と思ってみてくださいね。
お悩み ④|影響されやすい友人…

SNSの情報を鵜呑みにして信じ込んでしまう友人がいます。極端で過激なことを言ったり、情報の裏側をやたら疑ったり…。お互い大人なので口出しすることでもないかと思いつつ、心配です。

A. 「肯定はせずに話を聞いてあげる」(犬山)
ある考えに染まりきっているときほど、相容れない考えには耳を傾けられないものなので、「正してあげよう」とは思わないほうが、自分も苦しまずに済みます。このまま付き合いを続けていきたかったら、肯定はしなくても話を聞いてあげて「そういえば、こういう情報もあったよ」と信憑性の高い情報をさりげなく渡しましょう。聞くに堪えない差別的な発言をするようであれば、フェードアウトするのも自分のためです。
A. 「一度受け止めて違和感をそっと伝える」(Poche)
影響されやすい人ほど、強く否定されると心を閉ざしてしまうことも。だからこそ、無理に正そうとせず、「最近そういう考え方に興味があるんだね」と一度受け止めたうえで、違和感をそっと伝えてみましょう。別の視点をやんわりと差し出すことで、友人も自分の考えを振り返るきっかけになるかもしれません。心配する気持ちがあるからこそ、相手を否定しないでおく。静かに寄り添う形でも、ちゃんと届くことがありますよ。
イラスト・SAKIPON 取材、文・兵藤育子
anan 2447号(2025年5月21日発売)より