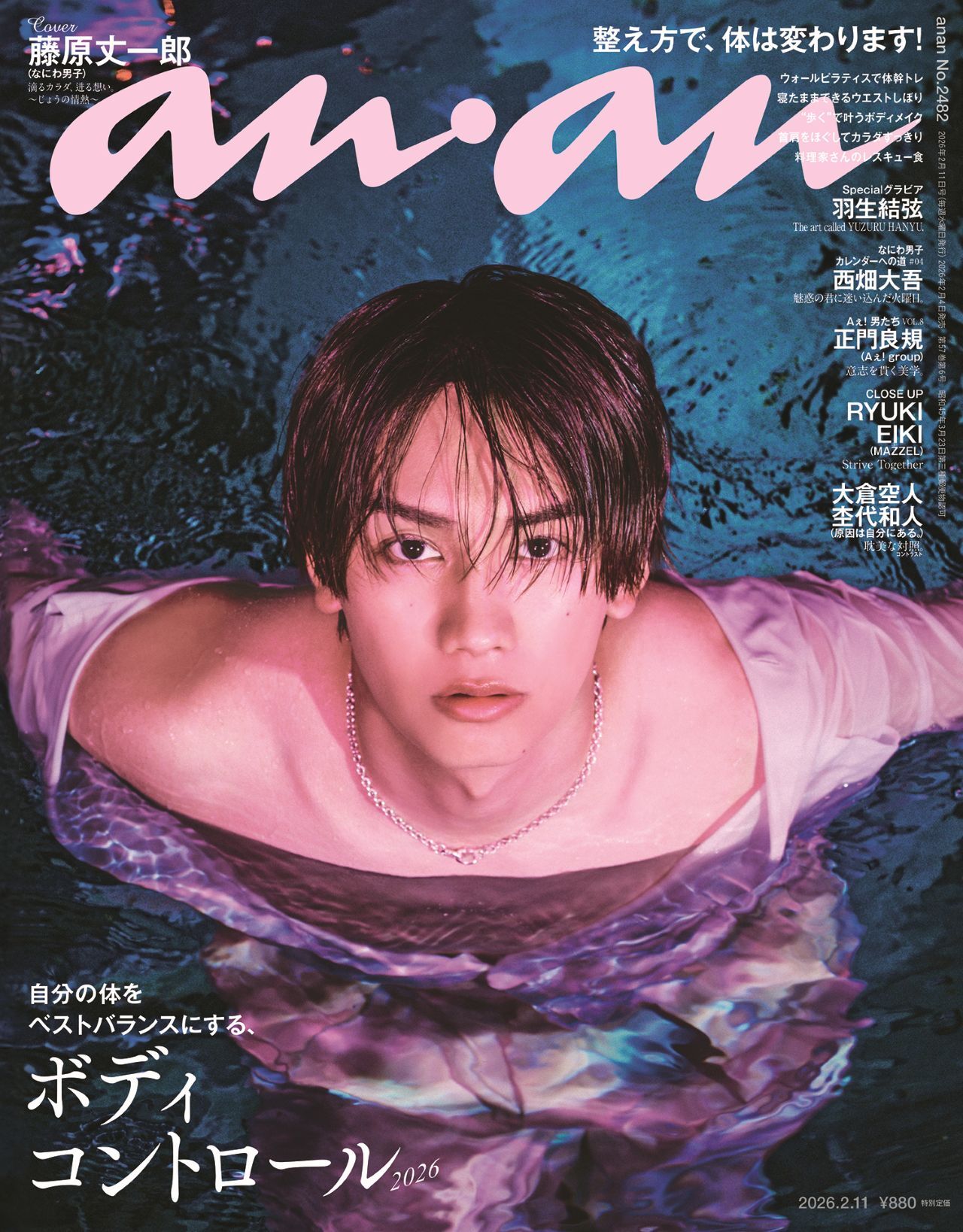進む競争社会。権利や保障、教育機会なども必要に。
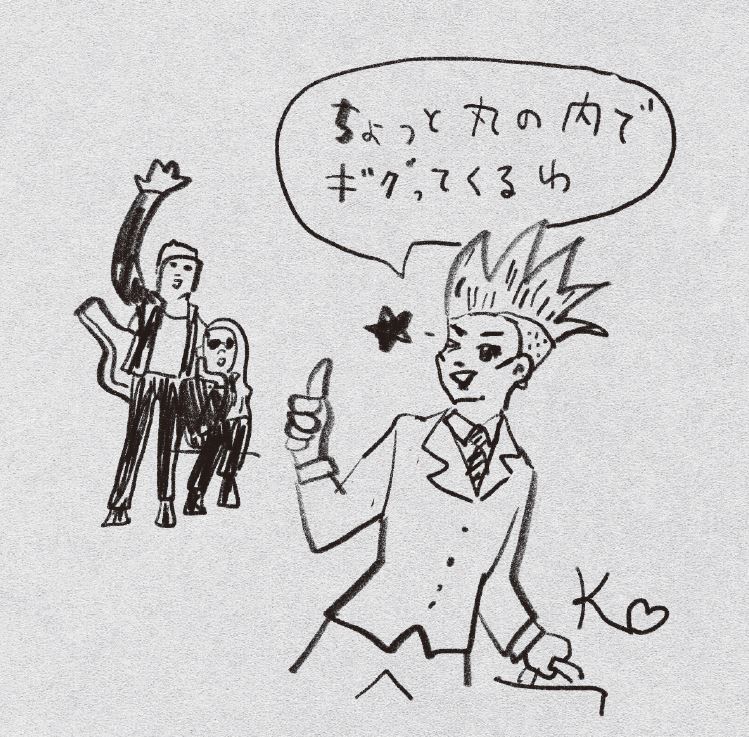
「ギグ・エコノミー」とは、アメリカ発祥の言葉で、インターネットやスマホのアプリを通じて、単発で請け負う働き方を指します。ミュージシャンの単発ライブの“ギグ”という言葉がもとになっています。このスタイルで働く人は「ギグ・ワーカー」と呼ばれ、いわゆる「派遣社員」や「日雇い派遣」とほぼ同義です。
ネットのマッチングサービスが発達するなかで、さまざまな職種でギグ・エコノミーは増えました。最もイメージしやすいのは、オンラインで注文を受け、飲食店の出前を行うウーバーイーツの配達員でしょう。日本では、得意なことを売り買いするマーケット「ココナラ」も有名です。Webデザインやイラスト、翻訳など、自分のスキルを生かし、仕事を請け負います。コロナ禍では、在宅・遠隔でもできる、空いている時間に働けるというので、こういう働き方が増えていきました。
働く側は働く機会を得やすくなり、企業にとっては人を雇い続けるリスクを減らし、柔軟に働き手を調達できるようになりました。ただ、正社員との格差があったり、労働組合もなく、何かあったときに誰も守ってくれない弱い立場にあるという問題があります。
たとえばウーバーイーツでは、配達途中の事故や料理が崩れたなどのトラブルは、配達員が責任を負っていました。ウーバーはあくまでプラットフォーマーですが、そうだとしても働き手の権利を保障することは重要と、国は3月に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しました。
ギグ・ワーカーが増えれば競争は激しくなり、単価は下がっていくでしょう。付加価値を付けられる人はのし上がれますが、そうでなければあっという間に転落する恐れがあります。副業としては有効ですが、生業となるとローンが組めない、家を借りられないなどの課題も出てきます。
今後、フリーランスやギグ・ワーカーが広まるのであれば、職業訓練の制度を充実させ、スキルを磨く仕組みを作ったり、大学の教育も技能に特化したプログラムに変えていくことなどが必要になるのではないかと思います。

ジャーナリスト。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。Z世代と語る、報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX平日7:00~)が放送中。
※『anan』2021年12月22日号より。写真・中島慶子 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子
(by anan編集部)