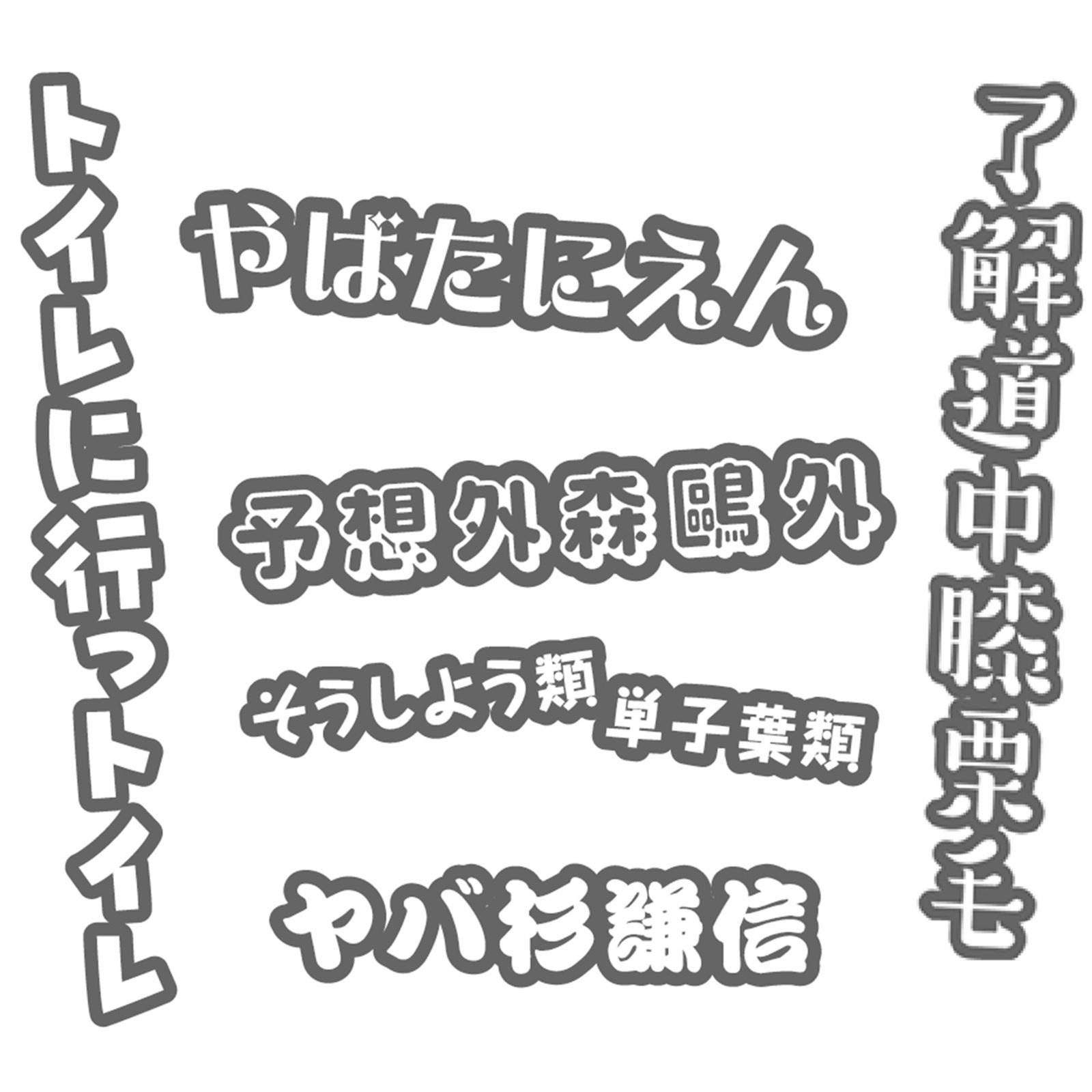映像の歴史と女たちの年代記。新芥川賞作家による注目長編。

「とても楽しく書かせてもらえた、自分にとってご褒美的な小説です。自分が楽しんで書いて、そこに人を巻き込むことができたらなと考え、自分のテンションを文章に写すことに心を注ぎました」
映画の黎明期から現在に至るまでの、映像に関わった女性たち数世代の物語や、映像や映画の歴史、さらには兵器として映像が使われたエピソードが並行して語られていく本作。
「そもそも映画の歴史みたいなものを、ねじれを生じさせながら書きたい気持ちがありました。正確なきっかけは忘れましたが、7~8年前にフィレンツェの科学館みたいなところに行ったことがあって。そこに、古い、レンズのついた測量機器が並んで展示されていて、最初見た時に“武器かな”と思ったんです。そのあたりから、こういう話を考えていたのかもしれません」
女性の年代記というテーマもある時から頭に浮かんでいた。
「映画の歴史は100年ちょっとなので、何世代かにわたる年代記的なものができるなと思いました。調べると海外では黎明期の映画業界で活躍した女性もいるんですが、歴史で取り上げられるのは男性の作品が多い。それで、ある程度女性にスポットを当てることにしました」
19世紀末、横浜随一の歓楽街の娼館の娘・照は機械学を学び、フランスに旅立って映像技術の研究所で働くことに。やがて、亡くなった友人の幼い娘を呼び寄せるが、その娘も成長し、また違う場所で映像に携わるように―。
「こういう人生、ああいう人生が奇妙な縁で繋がっていく奇譚のようなものが書けたらと思っていました」
一方、別のパートで語られるのは、監視カメラに囲まれた町でスマホで映像を撮る〈わたし〉の物語や、先述の通り兵器として利用された映像の話など、ちょっと不思議なエピソード。これがまた、どれもリアリティがありつつ、突拍子もなくて絶妙の面白さ!
「古いものと新しいものを混ぜて、ありうる気がしなくはないものを書いていきました。私は分かりやすく笑わせるのは不得意なんですけれど、ヘンなことを大真面目に言っている面白さが出るといいなと思いながら書きました(笑)」
ドキュメンタリーなど記録としての映像のあり方も考えさせられる。
「映像は説得力があるから、それで世論が動く場合もある。簡単に映像が加工できるようになった今、私たちはそれらにどう接していくか、ということはよく考えます。私自身、書いているのはフィクションですが、人が生活している場所を舞台に小説を書く以上、なんらかの倫理的な物差しを持っておく必要があるなと感じます。その物差しは時代によって変わっていく。ちょっとずつ更新しながら、自分の物差しを信じていくしかないなと思っています」
最後数ページでは熱いものがこみ上げる。極上の偽史をご堪能あれ。

『暗闇にレンズ』 レンズをのぞいて世界を切り取る〈わたし〉。彼女の母、祖母、曾祖母もかつて映像に関わっていた。映画と映像をめぐる奇妙で壮大な物語。東京創元社 1700円
たかやま・はねこ 1975年生まれ。2010年に「うどん キツネつきの」で第1回創元SF短編賞の佳作に選出され、’14年、同作を表題とした短編集を刊行。今年「首里の馬」で芥川賞受賞。
※『anan』2020年10月21日号より。写真・土佐麻理子 インタビュー、文・瀧井朝世
(by anan編集部)