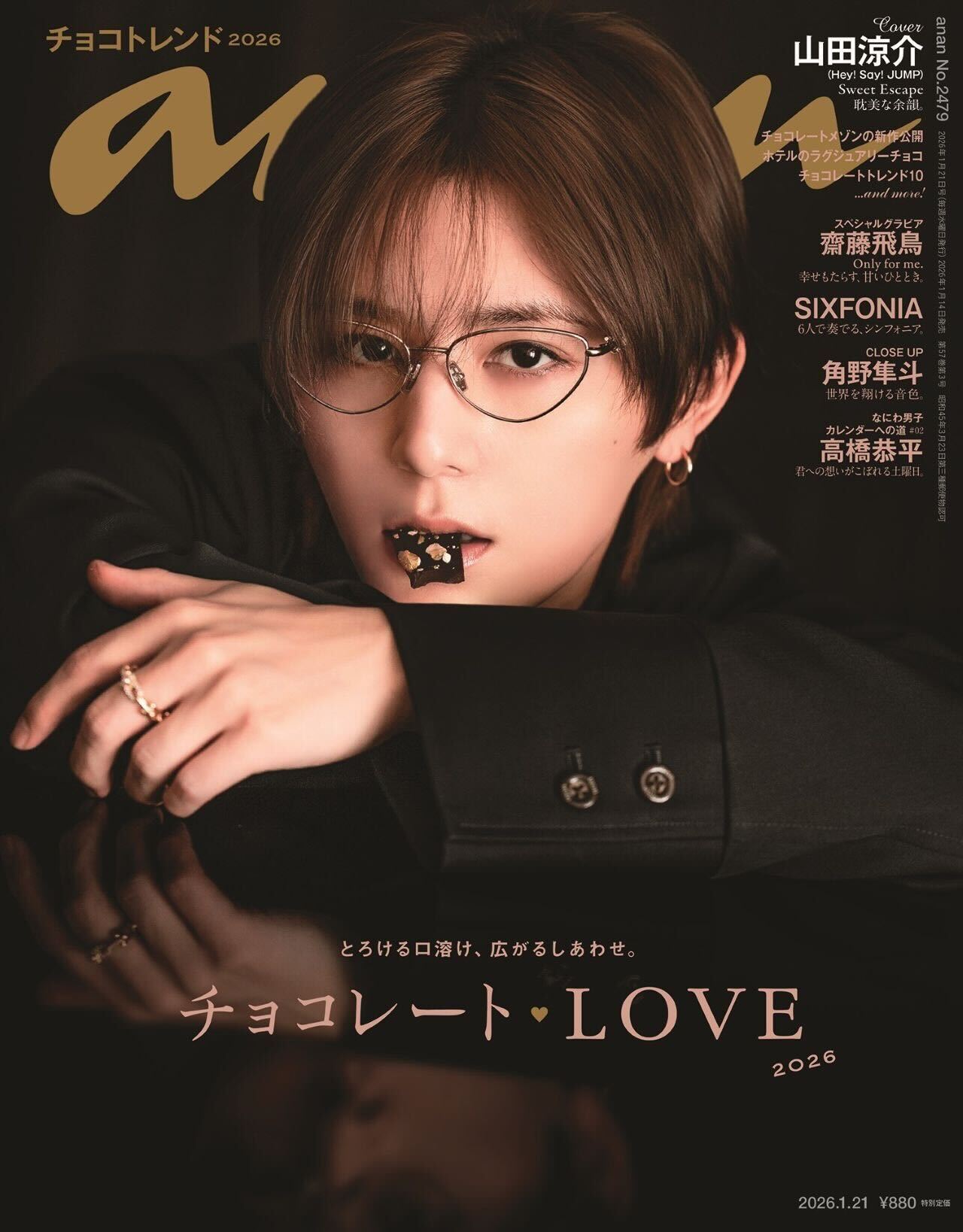雑誌『フィール・ヤング』で『君がまた描き出す線』を連載中のマンガ家、加藤羽入さん。理不尽な現実に向き合い、あらがいながら生きる人たちを描くそのストーリーは、同じような思いを抱えた人たちの心を捉え、共感の声が高まっています。“少女マンガ”という概念との距離感や、ご自身にとっての“あらがう”の意味、またマンガを通じて伝えたいことなどを伺いました。
Index
少女マンガに対して「ビジュアルとセリフが合ってない!」と違和感を覚えた、小学生時代
2023年の短編集『ビルド・ア・チェア』は、「私の居場所は私が作る。」をテーマに、“女の子の椅子”に座りづらさを感じる女性たちを、また現在雑誌『フィール・ヤング』で連載中の、マンガが生まれる世界が舞台の『君がまた描き出す世界』では、自分らしくあることを目指し、もがきながら生きる人たちを描いている、マンガ家の加藤羽入さん。ちなみに昨年発売したanan2410号の「私たち、こんな”女バディものが見たい!」という企画で、女バディが歳を重ねていく素敵なイラストを描いてくれました。
── 加藤さんが描かれる作品には、一般的に、少女マンガや女性マンガに不可欠と言われがちな“恋愛要素”があまり含まれていない印象があります。少女や女性向けに描かれたマンガには、あまり触れてこられなかったのでしょうか?
いえ、マンガを好きになったスタート地点は、いわゆる少女マンガでした。私は姉がいるのですが、姉が『りぼん』を、私が『なかよし』を買ってもらっていて、小さい頃からマンガが完全に生活の一部でしたね。小学校6年生のときにノートに描いた、3人の女の子が変身して戦う、みたいなマンガが今でも何冊も残ってます(笑)。
ただ、少女マンガとの関係は小学4年か5年のときに一度終わるんです。当時少女マンガを読んでいて、主人公の女の子が「私なんて地味でかわいくないし」とか言う割に、絵的にはすごくかわいい描写を見ると、「お前はかわいいじゃないか!」って思ってしまい、だんだん感情移入できなくなってしまったんです。
── 主人公が自虐するスタンスがあまり好きではなかった?
それもあったかもしれませんし、「セリフ通りのビジュアルを見せてほしい」という気持ちが大きかったんだと思います。かわいくない、地味だと言うなら、そううところを見せてよって。特技もなく美人でもなく、クラスでは陰キャという自覚があった私としては、セリフでは私と同じようなことを言っているけれど、全然違うじゃん、と。徐々に「少女マンガには私の居場所はないのかな」と思うようになった気がします。
一方で、習っていたピアノの先生のおうちで、藤崎竜先生の『封神演義』という、中国の古典奇怪小説を原作にした少年マンガを読む機会があって、それがもう衝撃的な体験だったんです。登場人物は誰も自分の容姿のことを言わないし、描いてあるセリフと絵に差異がなく、すんなり楽しむことができた。その上、戦う女の子のキャラが本当にかっこよかった。「こんな世界があったのか!」って感じで、母に頼んでマンガを買ってもらい、そこから「私には少年マンガが合ってるんだ」と思っていました。それは中学、高校、大学生を卒業したあたりまで続きましたね。
── 中高のときは、女子の友達の間ではどんなマンガが流行っていましたか?
もちろん恋愛マンガでした。私の仲良しがそういうマンガが好きで、いろいろ貸してくれるので読みましたが、一応人気のマンガなのでストーリーとかはすごく面白いんですけれど、“なぜ主人公の女子は、この男子を好きになるの?!”みたいなところが、本当にわからなくて。私が、自分自身の“女性性”みたいなものとあまり上手く折り合いがつけられない時期が長かった、というのもあるとは思うのですが、恋愛マンガが得意ではなくて。私が当時少年マンガに熱狂していたのは、“恋愛以外の達成目標が描かれている”からで、そこが読んでいてとても楽しかったんだと思います。でも、大学を出てしばらくして、槇村さとる先生の『Real Clothes』というマンガに出合って、女性向けに描かれたマンガに対する認識が、文字通り180℃変わるという事件がありまして。
女性向けマンガへの固定概念が崩れた、槇村さとる『Real Clothes』との出合い
── おそらくご自身で買ったりしたわけではないと思うのですが、どういうきっかけで手に取ることになったのですか?
大学でその先の進路を決めるとき、いろいろ考えて、やっぱり私は絵を描くこと、特にストーリーの中で絵を描くのが好きだということに改めて気がついたので、マンガ家を目指すことに決めました。実はその頃母が病気になって入院することになり、姉と私で看病のために病院に通っていたんですね。でもまあ看病ってすることがなく暇なので、姉がマンガをドサッと買ってきまして、その中に『Real Clothes』があった。私は当時、百貨店で働いていて『Real Clothes』はまさに百貨店の物語だったこともあり、本当に本当におもしろくて、姉と二人で時を忘れて読み漁ったんです。
出てくる女性たちのが一生懸命働きながら、彼氏と別れたり愛する人を見つけたり…というストーリーは、私はその年になるまで一切通ってこなかったんですが、だからこそ、“女性向けのマンガって、こんなに面白いんだ!”と衝撃を受けた上、ものすごく元気ももらえたんですよ。『Real Clothes』に触れたことがきっかけで、自分が持っていた女性というものや、女性向けに描かれた物語などに対する凝り固まった部分が徐々に和らいでいったのをよく覚えています。

百貨店の婦人服売り場で働く女性販売員の、仕事と恋に懸命に生きる姿を描いた物語。連載は2006年から2011年まで続いた。『Real Clothes』槇村さとる 文庫版 全6巻 各¥869 /集英社 ©槇村さとる/集英社
── そこから女性向けマンガを読むようになりました?
はい。まず槇村先生の作品をわーっと買って読みました。あと、森薫先生など、女性作家の作品もたくさん読むようになりました。その後、結局は母は亡くなってしまうのですが、ほぼ同時にマンガ家デビューが決まり、2年くらい連載もさせていただいて。で、連載が終わったとき、担当編集の方に突然、「加藤さん、たぶん女性向けマンガのほうが向いているよ」と言われたんです。びっくりしました。
── 女性向けマンガを読むようになったとはいえ、描くとなると話は別ですよね?
その通りです。やっぱり自分としては、“恋愛を描かなきゃいけないんでしょ? それはやりたくない”って思っていたので、自分では無理だと思っていたんです。でも、『Real Clothes』は面白かったし、振り返ったら美内すずえ先生の『ガラスの仮面』も大好きだったし、『美少女戦士セーラームーン』も、『魔法騎士レイアース』も好きだった。もしかしたら、女性向けのマンガも描けるのかも…と、徐々に気持ちが変わっていた感じはありますね。
── 今挙げて下さったマンガはすべて、戦ったり、挑む女性を描いている作品ですね。
確かに。私が好きな、“目標設定がしっかりあって、そこを目指すストーリー”というのは、女性向けマンガにもあったんですよね。そしてその目標設定は、女性向けマンガのほうが、リアルな現実に近いのかもしれません。それから、自分が歳を重ねるにつれて、いま目の前にある問題や、社会的な課題を解決する、みたいなことに目がいくようになってきた、というのも大きいと思います。
女性誌なのに、“恋愛を描け”と言われなかったことにびっくり
── 現在雑誌『フィール・ヤング』で連載をされていますが、この雑誌も、どちらかというと既存の少女マンガや女性向けマンガにあらがっている、そんな存在ですよね。どういう経緯で連載をすることに?
きっかけは、私が2021年描いた少女向けの同人誌で、それをいわゆるメジャーの少女マンガ雑誌に売り込みに行ったんです。でも行く先々で「うちではちょっと」みたいな感じで。それで、ものは試しにと少年誌や青年誌にも持っていったら、なぜかみなさんに「『フィール・ヤング』が合ってるんじゃない?」と言われまして。さらに、マンガ好きな友達も同じことを言うんですよ。正直『フィール・ヤング』こそ恋愛マンガの印象があったので、難しいだろうなと思っていたんですが、立て続けに言ってもらったので”これは行くべきかな”と思い伺ったら、ありがたいことに拾っていただけました(笑)。
── 『フィール・ヤング』にはどんな印象を持っていましたか?
読者として読んでいるときから、とても自由な雰囲気は感じていて。私が売り込みに行く少し前に、和山やま先生の『女の園の星』の連載が始まり、表紙になったりもしていたので、すごく懐が深い雑誌な印象もありました。恋愛モノも、恋愛モノじゃない作品も掲載されているということは、いろんな女性を描いて、いろんな女性に届けたいと思っているのかな、とも。そういう意味で編集者や友人は、「君も仲間に入れてもらえるかもしれないよ?」と薦めてくれたのかもしれません(笑)。
最初に打ち合わせをさせていただいたときに、「恋愛を描くべき」と言われなかったことに驚き、同時にとても嬉しかったことをよく覚えています。そして、連載作品をいろいろ読ませていただくと、恋愛マンガというのは、一対一で人と向き合って生きる、そのことを描いている作品であるということがわかりました。デビューしたころ、女の子同士のままならない関係を描こうとしたけれど、技術不足で上手く描けなかった経験がある私からすると、そういった人との関わりを描くことがどれだけ素晴らしく、尊いものなのかを、改めて理解したというか。そこから、また新たにスタートを切ったという感じです。

女性向けマンガ雑誌『フィール・ヤング』は1989年に創刊。2007年からのキャッチコピーは「恋も仕事も!」。キラキラだけではない恋愛のさまざまな側面を描いた作品が掲載される一方、2010年代中頃からは恋愛に触れない作品も掲載されるようになり、キャッチコピーも「あなたの心はどこまでも自由。」と変わった。写真は2025年7月号で、表紙は和山やまさんのイラスト。毎月8日発売 ¥790/祥伝社 ©祥伝社
── 今の加藤さんにとって、女性向けの漫画とはどういうものですか?
社会の中で人は1人では生きていけませんから、誰かとぶつかることもあれば、一方でつながったりすることも多々ある。他人同士が向き合って一緒に生きていくとはどういうことなのか、それを描いているものだと思います。ときには教科書的に教えてくれたり、ときにはチアリーダーのように応援をしてくれる存在でもある。あと、遠い目標ではなく、生活の中にある、明日明後日、1年後くらいのためにどうしていくか、そういう形のエンパワーメントのためにあるものだと、今は思っています。
── いろんなストーリーの女性向け作品がある中で、加藤さんの作品も含め、既存の概念や“らしさ”みたいなものにあらがうような物語を描いている作品が増えている印象がありますが、そのあたりはいかがですか?
新しい物語が増えているという実感はありますし、それはずっと“恋愛だけを描いていない女性マンガ”を求めていたかもしれなかった自分にとっては、すごく嬉しいことです。“恋愛しなくてもいいじゃん”という視点で書かれたストーリーや、主人公がアロマンティックの物語なども増えていて、それが例えば本屋さんやウェブ書店などの、見えるところに存在していることだけでも、個人的にはとても嬉しいです。
それから、恋愛と仕事を描いている作品でも、仕事の比率が高い作品も増えている感じがして、それもいいな、と思います。一方で、恋愛マンガが一番好き、という人も間違いなくいるので、それも尊重されるべきだと思うんです。私の理想は、いろんなタイプの女性の人生が描かれている作品がたくさん存在する、ということ。その1つに、自分のマンガが加われるならば、とても幸せなことだと思います。

加藤羽入というペンネームで初めて出版した短編集『ビルド・ア・チェア』。タイトルには「私の居場所は私が作る」という思いを込めたそう。“普通”にあらがって、あるいはあらがいたい、と思っている女性たちの物語。¥1,056/祥伝社 ©加藤羽入/フィール・コミックス
いろんな女性を描き続けることが、私にとっての“あらがい”
── 今回の特集のテーマの〈あらがうマンガ〉でいうと、加藤さんは作品を描くに当たって、何に一番あらがっていると思いますか?
う〜ん、なんだろう…。まず、“いわゆる少女マンガ”と呼ばれるものにはあらがいたいな、と思っています。市井の人の会話で「少女マンガっぽよね」とか「女性向けコンテンツでしょ?」というとき、キラキラとかピンクとかをぱっと思い浮かべる人が多いと思うんです。私自身もそうでしたから(笑)。そこにはあらがいたいですね。でも、「そうじゃないマンガもあるんだよ!」って叩きつけるガッツはないので、下からそっと、「すいません、少女マンガ実は多種多様で、こういうのもあるんですよ?」と差し出すあらがい方ですが(笑)。
以前連載をさせていただいた雑誌の編集者さんから、「マンガというのはターゲットがあって、うちの雑誌は20代の会社員女性がそれなんです」と言われたことがあって、「それ、広すぎないか?」って思ったことがあるんですよ。そのときに、例えば“20代女性”や“30代主婦”といった肩書と、実際に今生きている女性の人生って、リンクしてないのでは…という感覚が芽生えました。
人生を振り返ると私はふてくされていた時期が結構長くて、そのときに、「普通ぶってて、みんな嫌い!」みたいになっていたんです(笑)。でもいろんな人と話をすると、“普通の主婦”とか“普通の女性”っていうのは、言葉としてはあるけれど、それが意味するものは、よくわからないですよね。とはいえ、「普通なんてものはないんだ!」とか、大上段に構えた事を言うのも上滑りしている気がするので、決してそうではなくて、「世の中にはいろんな人、いろんな女性がいるよね」ということを描きたい、という気持ちが強いです。
── そういう意味では、当たり前とか、普通ということにも、そっとあらがいたいということですか?
はい、そっと(笑)。私がそういった潮流に寄与しているかどうかはわからないですけれど、その波の一部になれているのであれば、とても嬉しいです。
── ご自身の作品を、読者の方に、どんなふうに読んでもらえたら嬉しいですか?
そうですね…、「仲間がいた」って思ってもらえたら、一番嬉しいかな。私がマンガに描いたエピソードを読んだ方から、「私もそうだった」とか「私も同じ思いをして、悲しかった」とか、あるいは「同じ経験をしたけれどマンガのようになったら私も嬉しかった」といった声をかけてもらうことがあって。エピソードとしてマンガに描くことで、「少なくともそう思っている女の人がここにいるよ!」ということは、世の中に言い続けていきたいですね。そんなふうに生きている自分自身が私は好きですし、それこそが私の“あらがい”だな、と思っています。
Profile

加藤羽入
かとう・ういり マンガ家。京都府出身。2022年雑誌『フィール・ヤング』1月号に短編が掲載されデビュー。現在『フィール・ヤング』にて、『君がまた描き出す線』を連載中。単行本は短編集『ビルド・ア・チェア』、『君がまた描き出す線』1〜2巻(いずれも祥伝社)が発売中。