流行語の移り変わりから、私たちのコミュニケーションがどのように変化してきたかが見えてくる? 年代別に使われてきた言葉から知る、想いの伝え方の変遷とは。
自分も相手も傷つかないように配慮した言葉が生まれている。
時代とともに生まれる新語・流行語。そこから読み解ける、コミュニケーションの変遷とは? 言語学者の椎名美智さんに聞いた。
「既存の言葉では表現しきれない事柄や、より強調したい、新しいニュアンスを加えたいといった事情から新しい言葉が作られます。そして、時代に合ったコミュニケーション、刻々と変わる人間関係や距離感を反映する表現を使いたいという想いが、新語・流行語の普及に深く関わっています」
新しい言葉を作る方法は、5つのパターンに分けられるという。
「1つ目は既成の言葉を基に意味や音を変化させ、意味の拡張や縮小、悪化や良化をさせるパターン。『尊い』や『刺さる』がそうですね。2つ目はカナ表記にして、新しいニュアンスや意味を感じられたり、不気味さを緩和したり、コミカルなニュアンスを付け加える方法。『気持ち悪い』を『キモい』と短縮して表現する方法もこれにあたります。3つ目は外国語(英語)を取り入れ新しいニュアンスを加えたり、キツさを緩和するパターン。『チョベリグ』を想像するとわかりやすいでしょう。4つ目は文法的に破格の言い方をして、新しいニュアンスを生み出す方法。『ありよりのあり』や『~み』がこれにあたります。5つ目はオノマトペなどを使ってこれまでにない新しい言葉を生み出す方法。『ぴえん』や『きゅん』が該当します」
新語・流行語の変遷を振り返ると、メディアの変化も関係しているという。
「1990年代はTVの影響が大きく、ドラマで使われていた言葉が普及することが多かった。2000年代に入るとインターネットを主とする、所謂オタクカルチャーの言葉が一般化していきます。2010年代はインスタグラムなどのSNSが人気になり、『映(ば)える』といった特有の言葉が生まれました。2020年代は投稿をきっかけに広まった『きゅんです』などTikTok発の流行語が生まれています」
そして新しい言葉には、日本人の性質や若者のニーズが深く関わっているという。
「日本人はもともと自分の意見を強く主張しない傾向があり、『~的な』や『フツーに』に代表されるような、ぼかし効果を持ったクッション言葉がどの年代でも生まれているのは興味深い。こうした新しい言葉を生み出すのは主に言語感覚の鋭い若者。なぜかというと、彼ら特有の新しいニーズがあるから。そして、彼らはコミュニケーションにおいて、相手と一定の距離を置き、相手への配慮を示したい欲求が強いからでしょう。近年はより、相手との上下関係を強調せず、横の関係で話をしようとする傾向が強い。かといって、必ずしも近距離でのコミュニケーションが好まれるわけではなく、やはり一定の距離感を保ち、自分も相手も傷つかないように配慮した言葉が生まれている印象です。私はよく、“言葉は生物(なまもの、いきもの)”と伝えています。時代の流れの中で言語やコミュニケーションは常に変化していくからです。認識している言葉の使われ方と違ったり、知らない言葉でも否定せず、受け止められるようにしたいですね」
何気なく使っている流行語には、実は私たちの想いの伝え方が深く関わっている。これから出てくる新語・流行語にも、その観点から注目してみよう。
【1990年代】ギャルを中心に広まった新語が世の中を席巻。
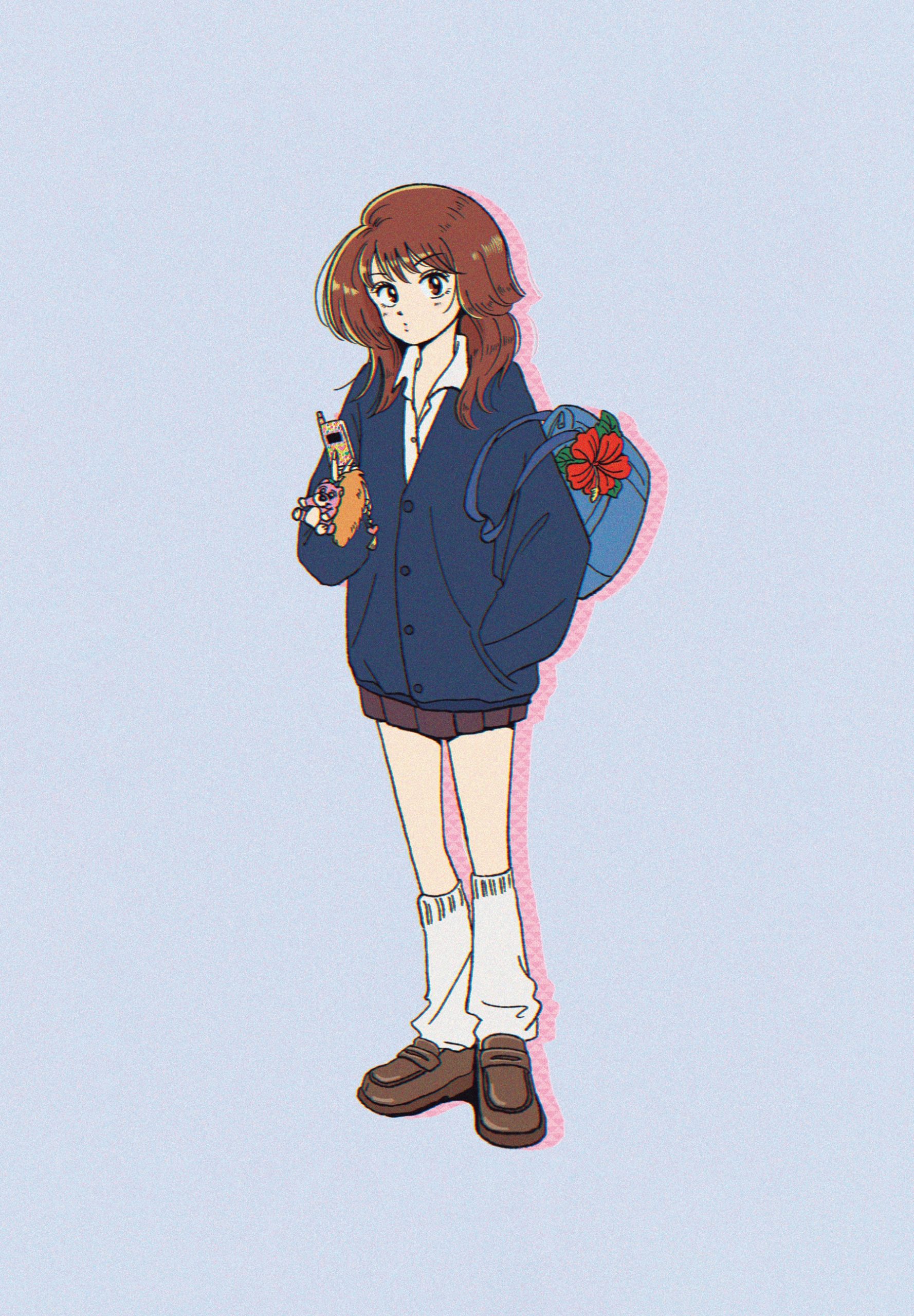
【チョー】
語意を強調するために、言葉の前に付ける「超」をカタカナ表記にしたもの。「『とても』『すごく』といった強調語はもともとありましたが、使われるうちに効力が弱まってしまい、それらよりもより強い意味の『超』が一般化。カナ表記にすることでよりポップな言葉としてギャルの間で広まり、定着しました」。類似した表現に「めっちゃ」「激」「鬼」「バリ」「ゲロ」など。
【アウト・オブ・眼中】
“out of”は英語で「~から外れて」「~の中から外へ」、眼中は「目に入る範囲」「意識や関心が及ぶ範囲」を意味し、興味や関心がないこと、論外であることを表す言葉。恋愛対象にならない人や、興味のない人・コトなどに向けて使われることが多い。1990年代に連載が始まった人気漫画『頭文字D』の登場人物のセリフに使われたことでも知られている。
【キモい】
「気持ち悪い」を略した言葉。不快な様子や見苦しい様子などを指す。「『気持ち悪い』よりも『キモい』と3文字になることでリズミカルでポップな感じになり、カナ表記にすることで軽やかな印象になります」。「気色悪い」の略である「キショい」も、同様の意味で用いられる。“(カナ)+い”は、「ウザい」「エグい」「エモい」「ダサい」「ハズい」などがある。
【チョベリグ】
「超ベリー・グッド(very good)」の略で、非常に良いことを指す。対語である「チョベリバ」とともに1996年の新語・流行語大賞トップテンに入賞。同年に発表されたSMAPの人気曲『SHAKE』にも「チョーベリベリ最高」といった歌詞がある。また「チョベリバ」は、木村拓哉と山口智子が共演した人気ドラマ『ロングバケーション』(1996年)でも使われた。
【2000年代】インターネットの普及とともにオタク用語も一般化!
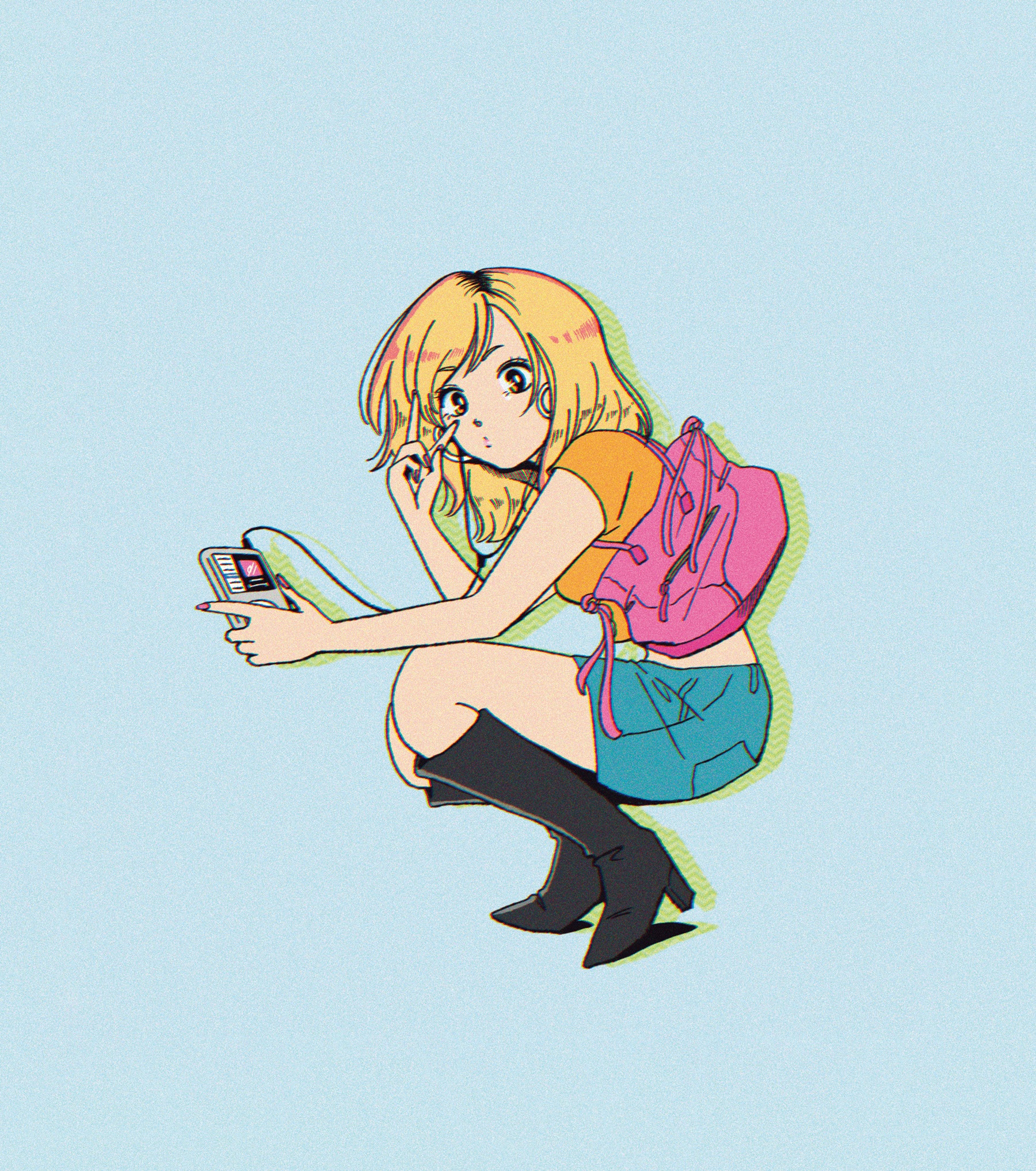
【~的な】
「個人的な意見にすぎないことを示しながら、発言の力を弱めたり、ぼかしたりするときに『私(わたし)的に』と使われるようになり、さらに応用範囲が広くなって『そんなことないよ的な』というようにいろいろな言葉の後ろに付くようになりました」。文末に使うことで「みたいな」「とか」と同様、自分の発言力を弱めるぼかし言葉として使われる。
【萌え】
アニメやゲーム、漫画やアイドルなどある特定のキャラクターや人物、対象に深い想いを抱くことを指す言葉。1990年代よりアニメファンが使用していたが、『電車男』のヒットなどオタクカルチャーが広まった2000年代には、大衆にも浸透。「萌え袖」「萌え断」など派生語も出現し、2005年に「萌え~」がユーキャン新語・流行語大賞トップテン入り。
【盛る】
「過剰で盛りだくさんにする」「通常より良く見せようとする」ことを指す言葉。「メイクで盛る」「プリクラで盛る」のように、何か手をかけることで、より可愛く見せることを表す際に用いられる。また、表現を大げさにしたり、話しを付け足したりして大きくする=「話を盛る」といった使い方も。2000年代よりギャルや女子高生を中心に広く使われた流行語。
【ぶっちゃけ】
「打ち明ける」の意味を強め、さらに崩した表現「ぶちあける」の副詞化で、「本当のことを言うと」「さらけ出すと」という意味。1980年代から使用されていたと考えられるが、2003年放送のテレビドラマ『GOOD LUCK!!』で主演の木村拓哉が多用したことで、若者言葉、新語・流行語として紹介され、一般化。使用例として「ぶっちゃけどうよ?」「ぶっちゃけた話」など。
【2010年代】インスタグラムなどのSNSが新たな言葉の発信地に。
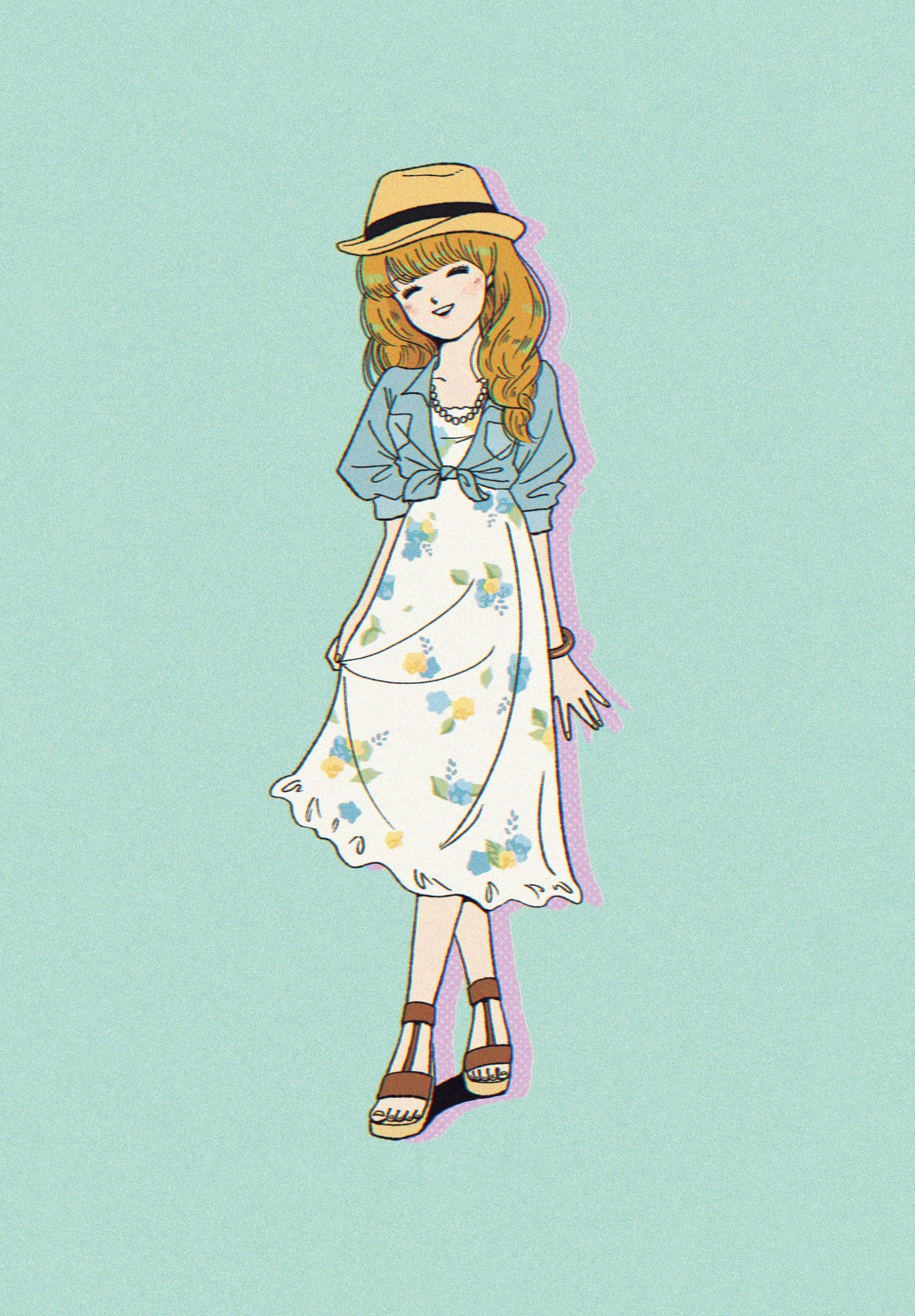
【映(ば)える】
写真や動画を投稿するSNS「インスタグラム」で、多くの「いいね!」をもらえるような「見映え」の良い投稿をすることから、「インスタ映え」という言葉が誕生。派生して、SNSや写真で良く写っている状態などを指すものとして、「映え」という概念が普及したとされる。風景やスポット、食べ物などで、写真に残したいほど際立ったものを対象に使われる。
【ありよりのあり】
全面的に肯定的な「あり」の意味で使用される。反対の意味として「ありよりのなし」があり、「かなり迷うけど、どちらかといえばなし…」という意味。「『あり』と『なし』はどちらか一方しか選択できず、段階がないものですが、そこに段階をつけようとする言い方。『ある』については、『これってアリ!?』や『会社あるある』といった新しい使い方をされてきた歴史も」
【~み】
「ヤバみ」「食べたみ」など形容詞や形容詞型活用の助動詞、さらに「わかりみ」など動詞に付き、名詞化して用いる新語。「本来のルールでは付かない語に『~み』を付けた新しい用法。従来であれば『ヤバさ』『食べたさ』というふうに『さ』を使うところですが、逸脱的な表現『~み』を使うことで、冗談めかしたネタとして、自分の感情や欲求を見せることができます」
【尊い】
「素晴らしい」「最高」「言葉では言い表せないほど好き」といった、最大級の賛辞や想いを表現する際に使われる言葉。もともとは、好きなアイドルやアニメキャラクターへの想いを表す言葉として使われ始めたといわれている。使い方は多様で、「すごい」という意味で「尊いがすぎる」と使用することもあれば、「尊みが深い」というように変化させて使用することも。
【2020年代】TikTokや絵文字から新しい言葉が次々と!
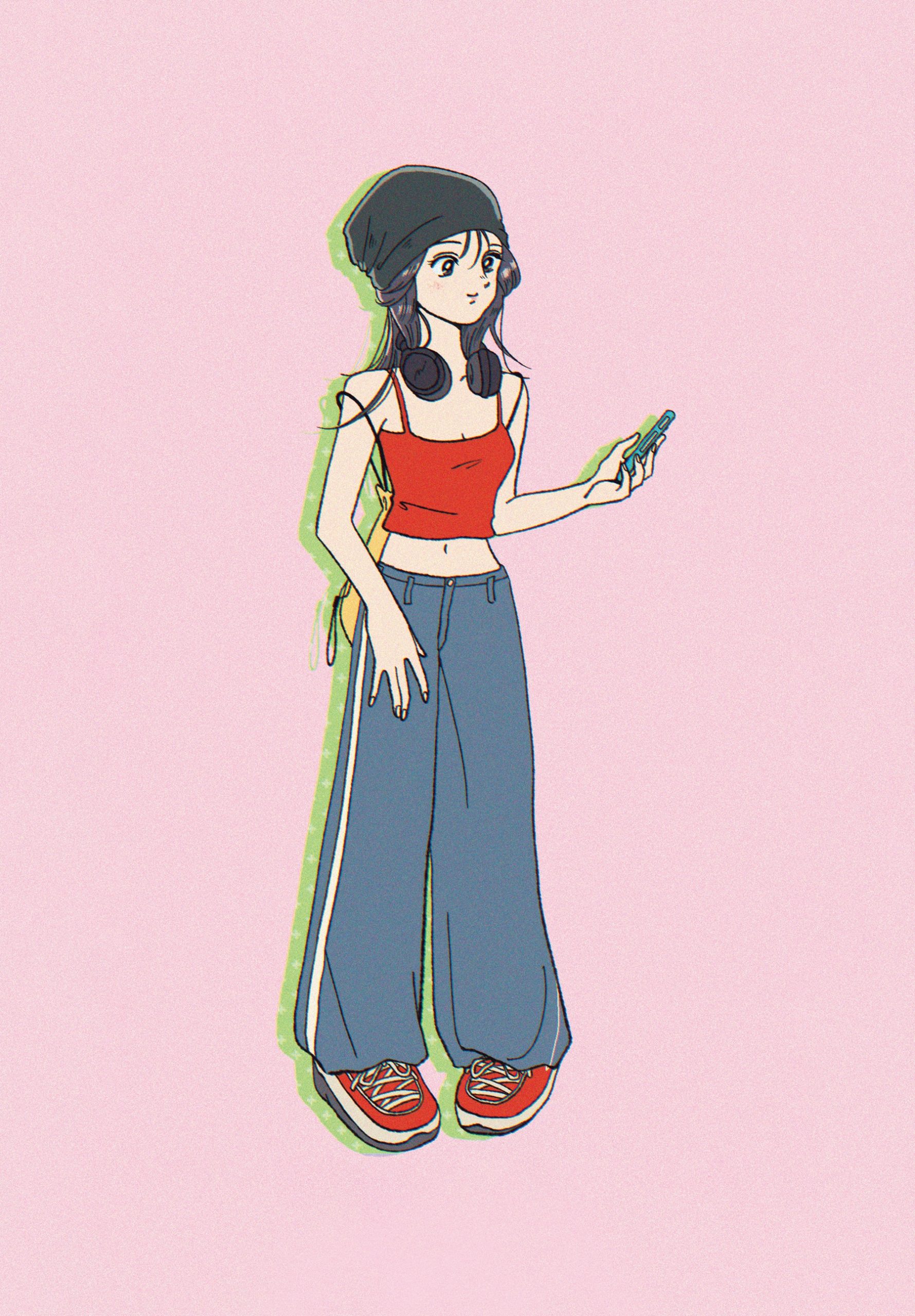
【ぴえん】
悲しさや嬉しさで泣きたい気持ちや、泣いている状態を表す、若者言葉の一つ。「人間は悲しくても嬉しくても、泣き出してしまうので、両義的に使われるのも特徴。文末で使用されていましたが、『ぴえんだね』など形容詞的にも使われるようになりました。また、『ぴえん』が使用されるようになった背景として、絵文字環境の標準化が挙げられます」
【~しか勝たん】
「それより勝るものはない」と対象を褒める表現。SNSなどで「推し」を称賛する表現として使われている。語源は2000年代後半よりアイドルに関する「推しメン」や「推し活」などの言葉とともに、「推ししか勝たん」という表現が若者世代に普及したこととされている。現在ではアニメキャラ、飲食物やコスメなど、自分が「最高!」と思うものに対して広く使われる。
【~界隈】
特定の趣味やコミュニティを指す言葉として使われ、「アニメ界隈」など自分がどのジャンルやアーティストを推しているかを伝える言葉だったが、Z世代の間で、特定の趣味やその人の状況を一括りにするワードとして使われている。お風呂に入ることが面倒な人たち=「風呂キャンセル界隈」、山や川、海などに出かけて友人やパートナーと楽しむ人たち=「自然界隈」など。
【~まである】
基準や予想が上回るさまを指すときに使われ、褒めを強調したいときなどに用いられる言葉。以前は「好きすぎる」「可愛すぎる」というように、「~すぎる」という表現がよく使われていたが、予想を超えるレベルを示して、際立っていることを強調するときに使われる。使用例として「犬が好きすぎて、犬になりたいまである」など。「~すぎて」と併用されることが多い。
Profile
椎名美智さん
言語学博士。法政大学教授。ランカスター大学大学院博士課程修了、放送大学大学院博士課程修了。著書に『「させていただく」の使い方』(角川新書)などがある。
anan 2433号(2025年2月5日発売)より







































