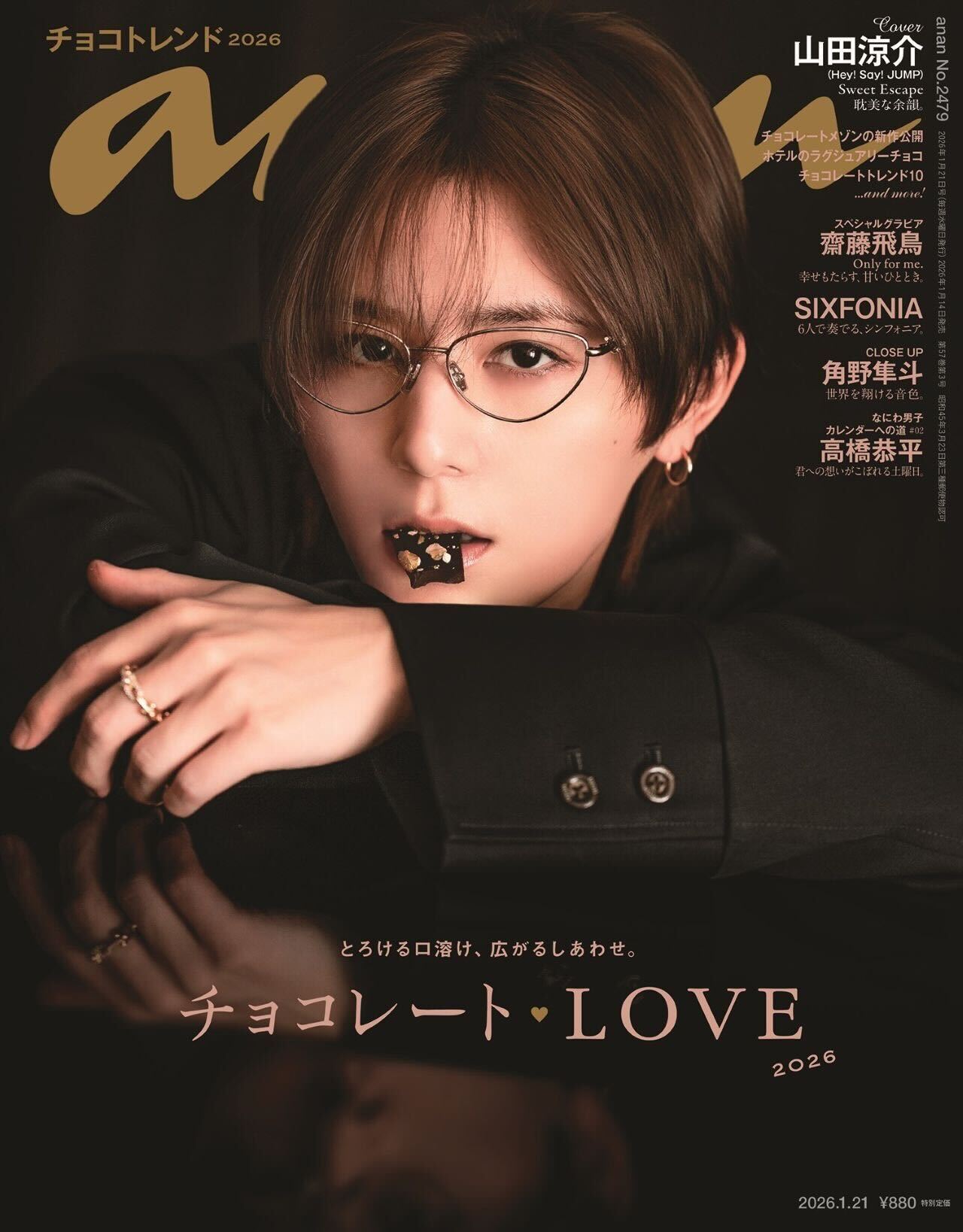昨年の秋にスタートした新しいコミックブランド『CandleA』。今まであまり取り上げられなかった、あるいは日が当たりにくかったテーマを描いている作品を積極的にピックアップする、そんなモットーのブランドです。サイトを覗くと、あらがっている作品がズラリ! いったいこんなチャレンジングな企画、どういうきっかけでスターとしたの? 編集を担当しているKさんに、お話をうかがいました。
Index
『作りたい女と食べたい女』のヒットがきっかけで、チャンスが巡ってきた
── コミックブランド『CandleA(キャンドレア)』が生まれた経緯やきっかけについて教えて下さい。
ゆざきさかおみさんのマンガ『作りたい女と食べたい女』のヒットを受けて、なにか“新しい場”を作れることになった、というのが、最初のスタート地点です。ただKADOKAWAにはすでに大人の女性向けのマンガレーベルがいくつかあったため、そことは被らないように…ということを考える中で、せっかくならば、今まで日の目を浴びにくかった作品を表に出す環境を作りたいと思い、『CandleA』の企画を立てました。
── “日の目を浴びにくい作品”、とは?
マイノリティを扱う作品はそれだけで企画が通りづらくなっている、という話を、複数見聞きしていたんです。なので、そうしたものを描きたい作家さんや、作りたいと思う編集者が挑戦できる場になれたらいいな、と。
また、 LGBTQという存在がことあるごとに透明化されてしまったり、あるいはそうした存在を匂わせて商業主義道具にしてしまう〈クィアベンディング〉に関して、エンタメを生み出しお金を稼ぐ立場の人間としては、もともと後ろめたさのようなものを感じていた、というのがあります。またこのブランドのコンセプトを考えていた時期にイスラエルのガザに対するジェノサイドが始まり、それについて個人的に勉強をしていた折に、〈いないことにされてしまう誰か〉というのは不均衡における弱者であり、例えば誰でも“そこに生まれた”というだけで弱者の立場になることがあると、改めて感じた、というのも大きかったかもしれません。
── 『CandleA』は昨年の10月にスタートしました。改めてどんなコミックブランドなのか、教えていただけますか?
ローンチの時に、私たちは以下のメッセージを出しました。
CandleAは、社会的あるいは文化的に「いない」ことにされている存在や関係や感情について描かれる作品を積極的に掲載していくコミックブランドです。
「いない」ものとして扱われてしまう存在は、往々にして弱い立場の誰かです。
そうした存在を世界から、あるいはエンターテインメントの場から消したくない。
暗闇のなかで「ここにいる」とろうそくの光のようにやさしく教えてくれるような──あるいは、激情と怒りに燃える炎のような物語を。
名称は、何も見えない暗闇でそっと誰かを照らすというイメージから、まずキャンドルを連想しました。また、炎には激しさや怒りといったイメージを託せる、そんな印象もあったので、そこから『CandleA』と名付けました。
── 『CandleA』で連載をしている、あるいは取り上げる作品の共通点はなんですか?
基本的には、“いないことにされがちな何か”を扱っている、ということが共通点かと思います。
あらがってきた先輩たちのバトンを、未来に繋いでいきたい
── かつてに比べると作品のバリエーションや取り巻く状況も変化はしていますが、いわゆる〈少女マンガ〉や〈女性向けマンガ〉と言われる作品群と、『CandleA』が光を当てようとしている「いないことにされている存在や感情」を扱った作品の間には、今はどんな関係性があると思いますか?
そもそも〈少女マンガ〉というジャンル自体が、当事者であるはずの女性を欠いた状態で始まっているんです。というのも、かつてスタートした時代に関わっていた編集者もほとんどが男性で、そうした不均衡から、女性作家の内なる欲を宿した企画が通りづらかった歴史がありました。そういう意味でいわゆる女性向けのマンガというのは、フェミニズムと切っても切り離せないものだと、私は認識しています。
長く時間が経ち、そうした状況はかなり変化したと思いますが、女性という存在や、女性が抱く感情はやはり、長く「いない」ことにされてきたものだとも感じています。マンガ家や編集者など先人が必死にあらがってきた結果、今があると思うので、私たちもこのコミックブランドを通し、少しでも未来にバトンを繋いでいけたら嬉しいです。
── 今回の特集企画は、“あらがう”というキーワードで今の少女マンガや女性向けのマンガを考えてみよう、という取り組みなのですが、『CandleA』のスタンスにも“あらがい”を感じます。編集担当のKさん的には、あらがうという行為や言葉に対してどう考えますか?
これは私個人の意見なのですが、マンガ業界や社会の構造には常にあらがいたい、と考えています。エンターテインメントがいつも、“みんな”を楽しませてくれるものだったらいいな、と思いますが、きっと世界はまだ道半ばで、その“みんな”に含まれない存在のことを、置いていってしまっていることがあると思うんです。世の中の作品が多様であるという“うねり”が起こることや、こんな作品や存在があってもいいはずだ、と宣言していくところから、少しでも現状にあらがっていけたら、と思っています。
マンガ家のみなさんからは、「『CandelA』という存在、注目しています!」というお声をいただくこともあり、とても嬉しいですし、ありがたいと思っています。ただ同時に、「こういったテーマは、執筆に覚悟がいる」といったことを伺うこともあるので、そういった思いも含め、なにかいい形にすることはできないか…と、日々考え続けているところです。
── いわゆるマスではない層の声に耳を傾けるような、そんな声を拾うような物語に光が当たることには、どんな意味があると思いますか?
そういった物語に触れることで、あらゆる人が少しでも息がしやすくなる世界になったらいいな、と思っています。私は幼い頃、物語を通じて「この世界で起きていることは自分と無関係ではないんだ」ということを学びました。物語は現実ではありませんが、読まれることで現実に還元されて、誰かにとって、明日を生き抜く糧になると信じています。
責任編集Kさんが推薦! 今読んでほしい『CandelA』のあらがうマンガたち
私は私らしく生きる。還暦のレズビアンの物語
Top Pick #1

『ひとりみです』 森島明子
「還暦を迎えた独り身のレズビアンを描いた作品です。レズビアンやゲイの物語というと、どうしてもカップルでいるところを想像されがちですが、ひとりの人間として考えたとき、別にパートナーと添い遂げる選択をしないひともいるし、そうしたひとたちにもそれぞれの人生があるのだという当たり前の事実を伝えてくれる作品です。男女の雇用がいまよりずっと不均衡だった時代から、悩み、傷つき、あらがって生き抜いてきた女たちの存在を、パワフルに色鮮やかに描いていて励まされます」
©森島明子/KADOKAWA
鮮やかに描かれる“わたしたちの生きづらさ”が胸に来る
Top Pick #2

『くらやみガールズトーク』 漫画:ウラモトユウコ 原作:朱野帰子
「女性たちの、言えなかった本心と呪いからの解放を描く、朱野帰子さんによる短編集のコミカライズです。最初のエピソードが結婚して苗字が変わった女性の話なのですが、法律婚をすることで苗字というアイデンティティを半強制的に奪われていく過程の描写が、自分が死んでいくようなくらい感情が胸に迫ります。“私はここにいるのに”という胸に秘めた確かな想いは、“あらがい”だなと思います」
©ウラモトユウコ、朱野帰子/KADOKAWA
TVドラマにもなった、ごはんでつながるシスターフッド
Top Pick #3

『作りたい女と食べたい女』 ゆぎさきかおみ
「たくさんご飯を作りたい女性とたくさんご飯を食べたい女性が、ご近所さんとして出会い、お互いを尊重しながら仲を深めていく作品です。定食屋で女性が、悪気なくご飯の量を減らされてしまうことや、料理を作るのが趣味というだけで“いいお嫁さんになれる”と言われてしまうことなど、食に関する社会規範ゆえの不自由さに登場人物たちがあらがい、少しずつ解放されていく姿に、自分の心も少しだけ救われたような気持ちになれます」
©ゆぎさきかおみ/KADOKAWA