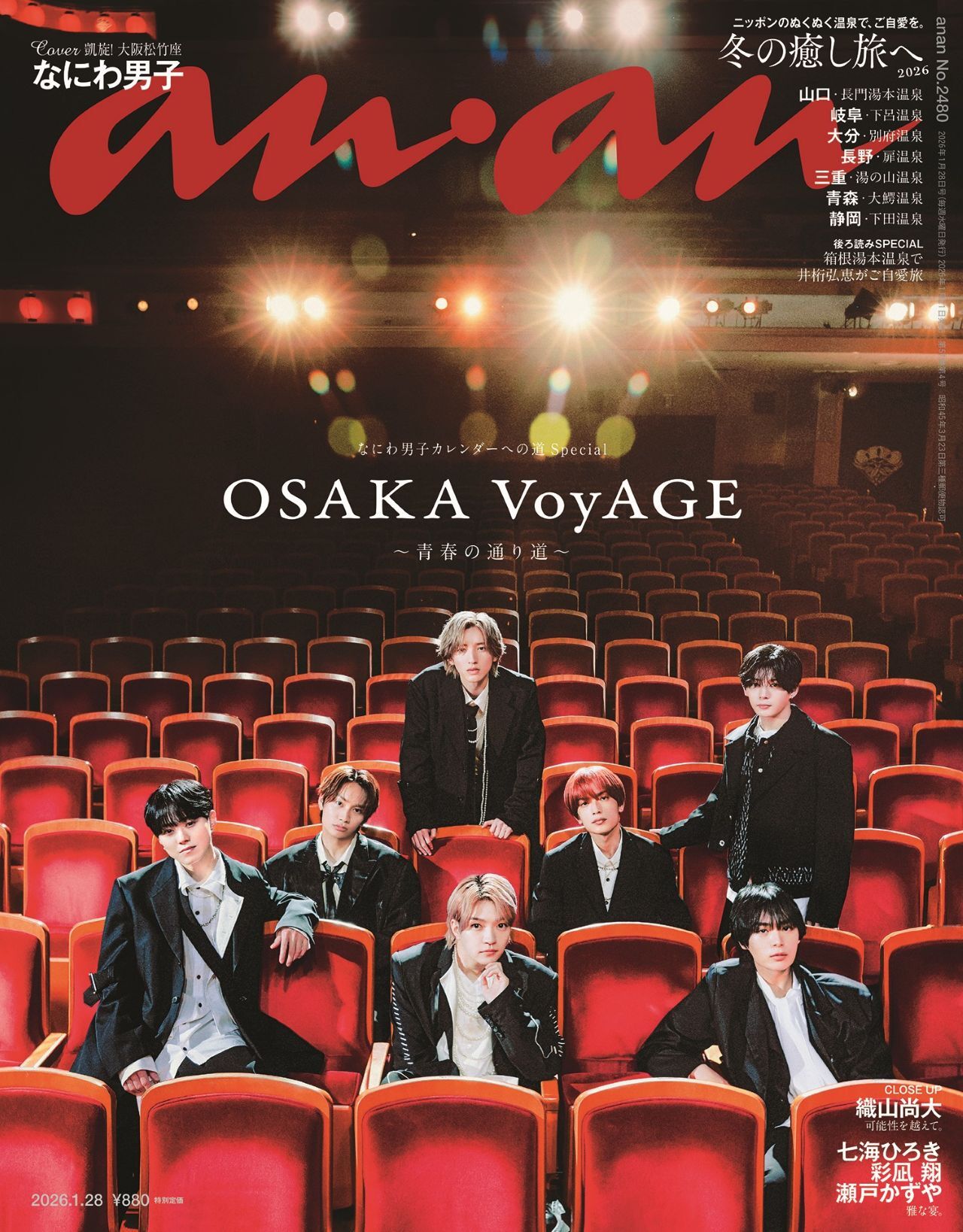コロナ禍が過ぎ、物理的に人に会うことが、また“普通”に戻った昨今。ストレスフルな人間関係は手放したいけれど、自分らしくいられる関係の相手がいないと寂しい…。そんな新しい繋がりが求められる、今どきの心地よい人間関係の距離感とは? 職場、友人、家族etc…さまざまな関係における“最適解”を多角的に考察。まずは、人間関係のモヤモヤの現在地から解き明かします。
仕事、友人、家族…より良くあるための【人間関係の距離感】
人間関係は“数より質”を重視。
コロナ禍で物理的に人と触れ合えなかった時期はもはや過去。日常的に人と会う状況がほぼ戻った今、人間関係に対する悩みはどう変わってきたのか。anan読者世代の人間関係の悩みの傾向について、臨床心理士の塚越友子さんに伺った。
「かつては自分を囲む人たち全員とうまくやりたいけどどうしたら…という悩みが多かった印象ですが、まず会社の人間関係を気にする人がすごく減った気がします。職場やなんとなく自分の周りにいる人との関係を考えるよりも、自分が必要だと思う友人や家族との繋がりを大切にしたい。そう思っている人が増えたような気がします」
マンツーマン雑談サービスを主宰し、さまざまな悩みと向き合う桜林直子さんは、互いに安心できる関係性=2025年における“優しい関係”なのでは、と言います。
「今の“優しい関係”とは、自分を出さずに相手に寄り添うことで平穏な関係を保つことではなく、自分の気持ちや意見を安心して言える関係性のことなのでは? 会う頻度や距離感はそれぞれですが、お互いに正直でいられる存在を求めている人が増えている、そんな感覚は確かにあります」
それに関しては、塚越さんにも同じような実感があるとか。
「この一年で大きく変わったと思うのが、“親友が欲しい”という悩みが増えたこと。友達はたくさんいらないけれど、密度の濃い、しっかりとした付き合いができる、そんな相手が欲しい。かつてはそれが“恋人”でしたが、今は親友がそれに代わったのかもしれません。“みんな仲良く”がよしとされた時代と比べると、人間関係自体は狭くなっているのかもしれません。でも大切な人とだけ繋がることで人間関係にメリハリが出て、結果的に煩わしいことが減り、心地よく暮らせるのかもしれません」
親友とは若干異なるものの、好きなコンテンツで繋がる“推し友”のようなコミュニティも、友人関係とはまた別の新しい関係性として大切にしている人が増えている。
「SNSによって、気軽に自分の好きを発信できるようになったので、同じ推しを持つ人同士が出会いやすくなった、というのがまず一つ。そして相手の性格やプライベートをそれほど深く知らなくても、コンテンツに対する熱い思いや価値観を共有できれば、強い結びつきが生まれやすい。今まで人付き合いが苦手だった人でも、コンテンツを通すことで居心地の良い関係性が築けることもありますよね」(桜林さん)
「人間は一人では生きられない生き物であり、集団への帰属意識があるものなので、推し友がいることで、どこかに所属しているという安心感が得られるのも大きいのかもしれません」(塚越さん)
面倒な関係は「フェードアウト」が主流。
以前より、20~30代の女性たちは、全体的に人との距離の取り方がうまくなっている印象がある、と塚越さん。となると、“深くコミットする必要はない”と思った人とはどう付き合っているのか…?
「人間関係をすべてバッサリ切って別の場所で一からやり直す、リセットタイプの人も一定数います。でも最近はふんわりとフェードアウトするのが主流。この人、今の自分としてはそんなに繋がらなくてもいいかな、と思ったら、例えば自分からは連絡をしないようにしたり、SNSを見ない、“いいね”はつけない…など、徐々に距離を取る、という感じにしているようです。相手によっては“あれ、距離を取られているかな?”と察するかもしれませんが、バッサリ切らないことでお互いにそんなに傷つかない。ただ、フェードアウトはするけれど繋がりを断つわけではないので、いつかまた再会することもあるかもね…という余白を残すのも今どきな感じだと思います」
桜林さんは、雑談で吐露される人間関係の悩みの中には、やはり“人と比べてしまい、自分はうまくやれない…”というものがまだまだ多いと感じるそう。
「相手にどう思われるのかが気になる人もいるし、相手に嫌な思いをさせているのでは…と思い悩む人もいる。人と比べてしまうのは、やはり圧倒的にSNSがあるからだと思います。もちろん、発信している方は誰かを傷つけようなんて意図はないわけですが、見ることで、知らなくていい情報も目に入りますし、知ることで無意識に自分と他者を比べてしまい、モヤモヤが募る。加害者不在なのに、被害者が山のように生まれてしまう。SNSには推し友ができるというようないい面もありますが、それによって人間関係が左右される人は、少し距離を取ることも必要かもしれません」
また実は大勢の人と仲良くするのは苦手、そんなに人と会わなくてもいいと思っている人は意外と多い、と桜林さん。
「人の目を気にして社交的に振る舞っていた人たちから、『コロナ禍のとき、堂々と家に一人でいられてすごく楽だった』と言うのを、本当によく聞きました。今また物理的に会うのが普通になりましたが、自分は“一人好き派”だということに気がついた人たちは、その経験があったことで、人目を気にすることなくうまく他者との距離をキープ、あるいはフェードアウトできるようになったのかな、とも思います」
「確かにコロナ禍の外出自粛によって、本当は行きたくなかった会社の飲み会のような“必要ない関係”がリセットされました。合う人とは会うし、合わない人とは会わない。その線引きがクリアになったのは、ある意味よかったですよね」(塚越さん)
人間関係は「自分で決めていい」時代に。
誰と、どんな距離感で付き合うか。数年前までは、“この人は、職場で毎日会うからいい関係を築かないと…”など、自分の気持ち以外の要因も含めて考えるのが当たり前だったかもしれません。でも桜林さんは、その距離感は自分で主体的に決めるべき、と言います。
「自分は誰の近くにいたくて、誰とは距離を取りたいか。この人とはこのくらいの感覚で付き合いたいな、というのは、自分が決めていい。雑談を通して思うのは、“自分はどうしたいのか”がわかっていない人が意外と多いということ。周囲を気にして自分の気持ちに蓋をして、“この人はどうしてほしいのかな?”と相手を優先した付き合いを続けていると、自分の意思が出てこなくなってしまう。さらにそれは見方を変えると、距離の取り方すら相手に委ねているわけですから、若干失礼な人間関係かもしれない。私としては、どんな距離感の相手でも正直に接するのがいいと思う。一つ一つ自分の気持ちを分解していくことで、自分がどうしたいのか、相手とどんな関係を構築したいのかが見つかるはず」
一方で塚越さん曰く、自分が距離を取ることを決めたものの、相手がそうさせてくれない、という悩みも生まれているそう。
「今までは、“相手とどうしたら深く繋がれますか?”という相談が多かったのですが、最近は“近しい人とはいい関係が築けているので、それ以外の人とは距離を取りたい。でも相手がそれをわかってくれない、どうしたら…”という悩みをよく聞きます。まるで恋愛関係の悩みのように聞こえますが、相手は職場の人だったり、ママ友、あるいは学生時代の友人からしつこい連絡が…といった相談です。先ほど、親友が欲しいという人が増えているという話がありましたが、昔の友人から連絡が来て、“自分は今はそこまで近しい関係になろうとは思っていなくて、困っている”という話もありました。解決策としては、わかってもらうまで、距離を取り続けるしかないわけですが、これも新しい悩みかもしれません」
なるべく揉め事を起こさず、波風を立てず。そのためにちょっと自分が我慢するのは当たり前…という時代はもう終わり。2025年の人間関係は、相手への思いやりよりも、自分に優しく、を一番に考えることが大切なのかも。
「お金や地位や名声があるよりも、自分にとって心地よい人間関係を持っていることのほうが幸せを感じる、という海外での研究結果もあります」(塚越さん)
「心地よさって本当に人それぞれで、毎日誰かに会わないと落ち着かない人もいるし、月に1回誰かと会えばいい人もいる。自分にとってベストなスタンスとはなんなのか。自分と向き合うことで、それを見つけられるといいですね」(桜林さん)
Profile
塚越友子さん
つかこし・ともこ 臨床心理士、公認心理師、博士(教育学)。「東京中央カウンセリング」代表。著書に水希名義での『自分を傷つけずに不毛なマウンティングをかわす力』(KADOKAWA)など。
桜林直子さん
さくらばやし・なおこ 〈雑談の人〉としてマンツーマン雑談サービス「サクちゃん聞いて」を主宰。ジェーン・スーさんとのポッドキャスト『となりの雑談』も人気。共著『過去の握力 未来の浮力』(小社刊)も発売中。
anan 2447号(2025年5月21日発売)より