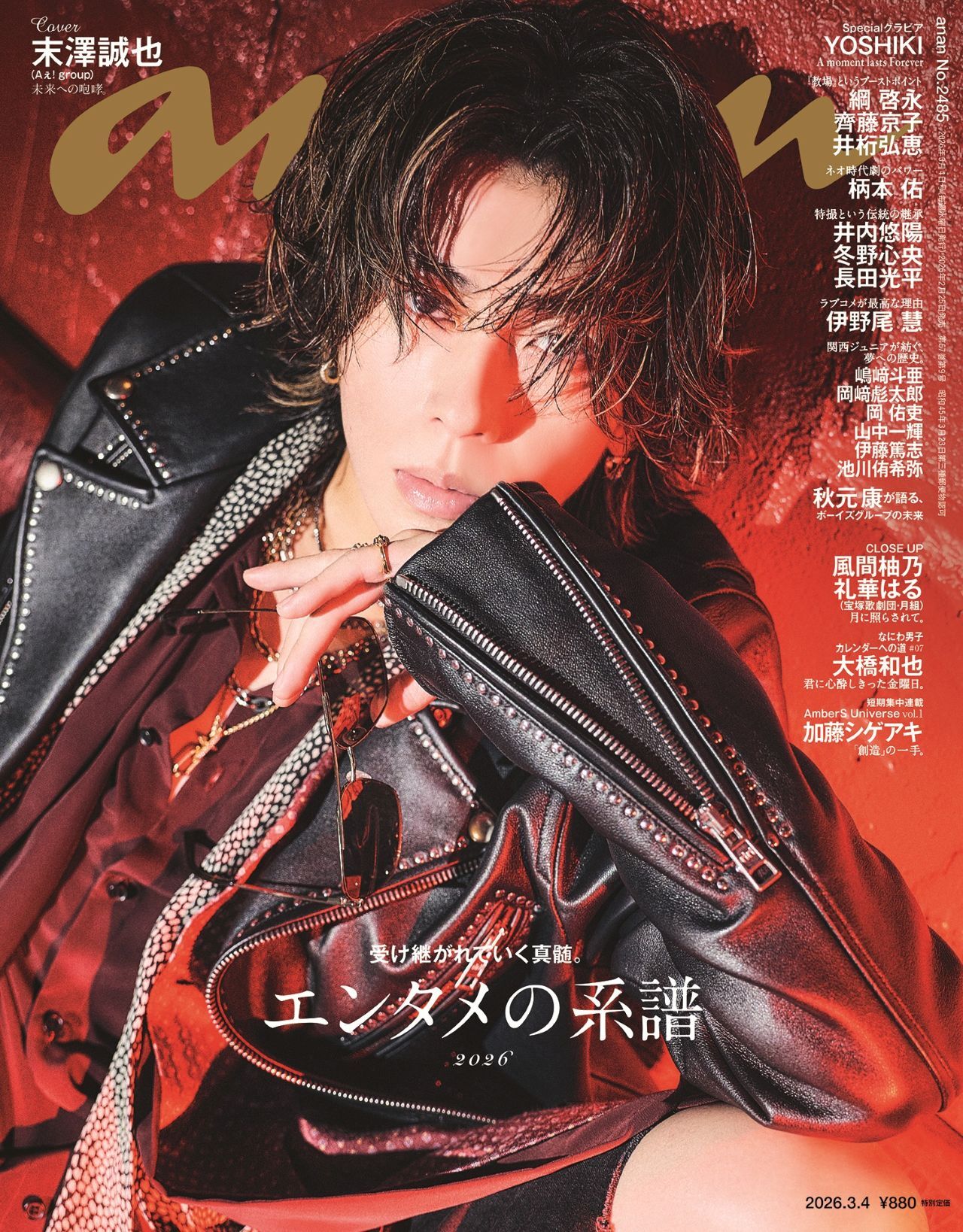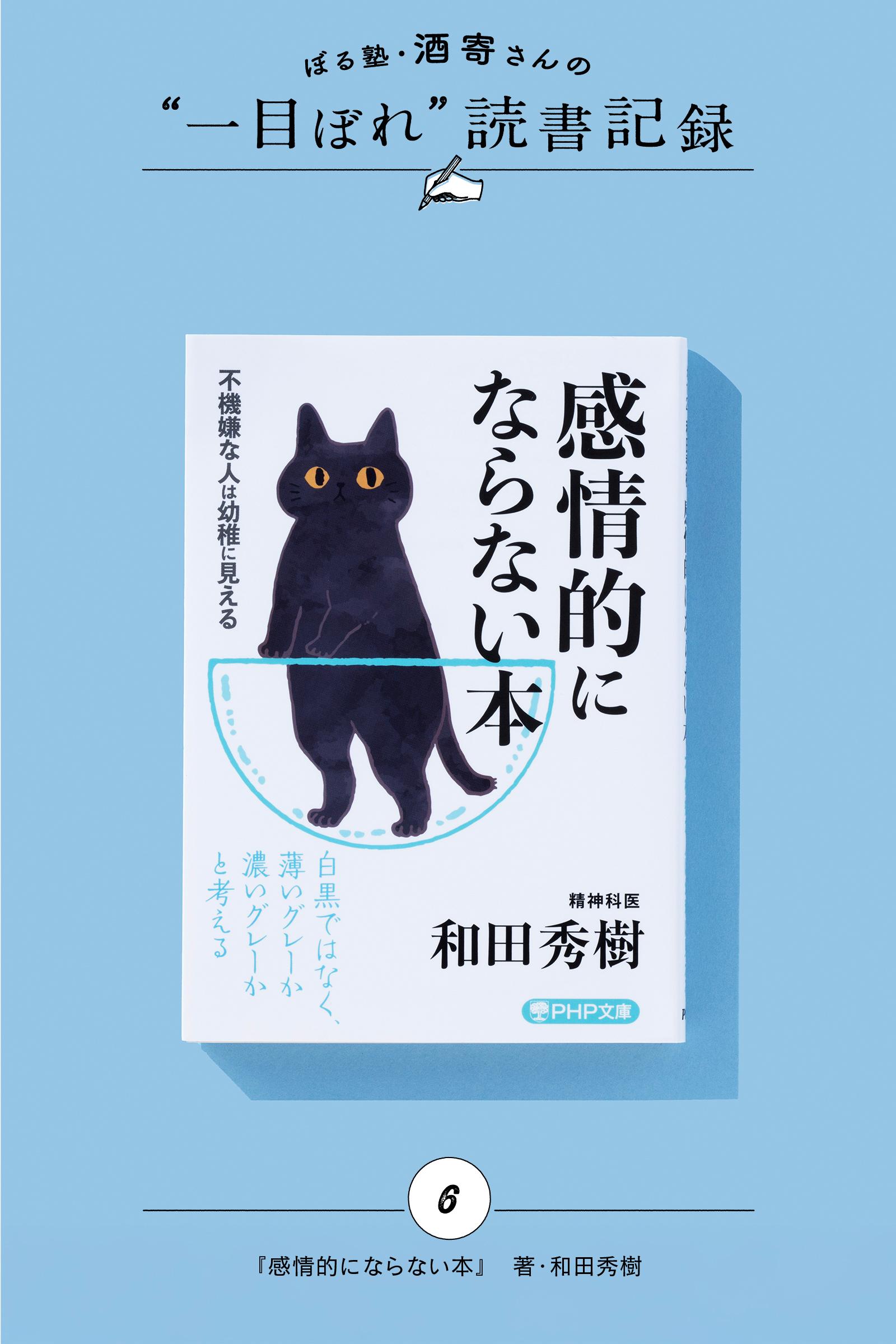「子供の頃、少女漫画誌を読みながら、編集部はどうやってこれを作っているんだろうと思っていました」と、小説家の大島真寿美さん。『週刊マーガレット』や『別冊マーガレット』を愛読していたという。
絶大な人気を誇った少女漫画誌。その編集部にいた人々の思いとは
「2014年の『わたしのマーガレット展』の頃に、すでに少女漫画編集部の話を書きたいなと思っていたんです。でもどうやって書けばいいのか分からなくて。5年ほど前、かつて少女漫画編集部にいたという年上の方と会う機会があって、そのお話が面白くて。いろんな人に話を聞いて書けばいいんだと気づきました」
そこから数年にわたり多数の元編集者や漫画家に取材し書き上げたのが、新作長編『うまれたての星』。少女漫画という文化を切り拓いてきた人たちの思いが伝わる作品だ。
1969年。出版社に就職した辰巳牧子は、「週刊デイジー」「別冊デイジー」編集部に経理補助として配属される。少女漫画の面白さに目覚めてハマっていく牧子のほか、さまざまな男女の視点で、当時の編集部の様子が活写されていく。
「編集部をまるごと書きたかったので、最初から視点人物は複数にするつもりでした。取材した方々をモデルにしたというより、どの登場人物にも、お会いしたいろんな方々が混ざっている感じです」
事前にプロットを練るというより、天啓のように降りてきたものを書き進めていくタイプの大島さん。今回も取材内容をインプットした後、物語の要請に従って筆を進めた。
「話の流れからいうと次はこの人の視点かなと思っても、書き始めると違う人が喋りだすんです。カラオケで次のマイクを握るのは誰だ、みたいな感じでした(笑)」
当時は、漫画家を担当するのは男性編集者だけで、女性編集者は懸賞ページ等を担当するのが当たり前だったという。
「私も取材するまで、そこまで男性と女性で役割が分けられていたとは思っていなくて。社会が女性の可能性を信じていなくて、女性もそれを内面化していたところがあったと思う。女性たちの悔しい思いは確かに存在したものなので、書かないわけにはいきませんでした」
そんな編集部内の女性たちも、年代によってものの考え方が少しずつ異なり、時代の移ろいを感じさせる。また、若い女性漫画家たちが作品に新しい風を吹き込もうとしている姿も印象的だ。たとえば、「週刊デイジー」でフランス革命を題材にした漫画の連載が始まり、一世を風靡していく様子などは痛快だ。
「当時、超天才の漫画家たちがあの雑誌に集まっていたんだなと思います。新しい時代の幕開けですよね。文化の入り口のひとつとして、少女漫画誌が機能していくようになった。実際、元編集者の方も、少女たちに何を与えられるか真剣に考えていた、と語っていました。当時の誌面を見ると、それがよく分かります」
どの世代の人も本書を読めば、幼い頃に読んだ漫画が自分の血肉になっている、そう実感するはず。
Profile
大島真寿美
おおしま・ますみ 1992年「春の手品師」で第74回文學界新人賞を受賞しデビュー。2012年に『ピエタ』で第9回本屋大賞第3位。2019年に『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で第161回直木賞を受賞。
Information

『うまれたての星』(集英社)
1970年代、150万部を突破するほど人気を博した少女漫画誌は、どのように作られていたのか。編集部で働く人々のさまざまな思いを熱く描く。¥2750
anan 2471号(2025年11月12日発売)より