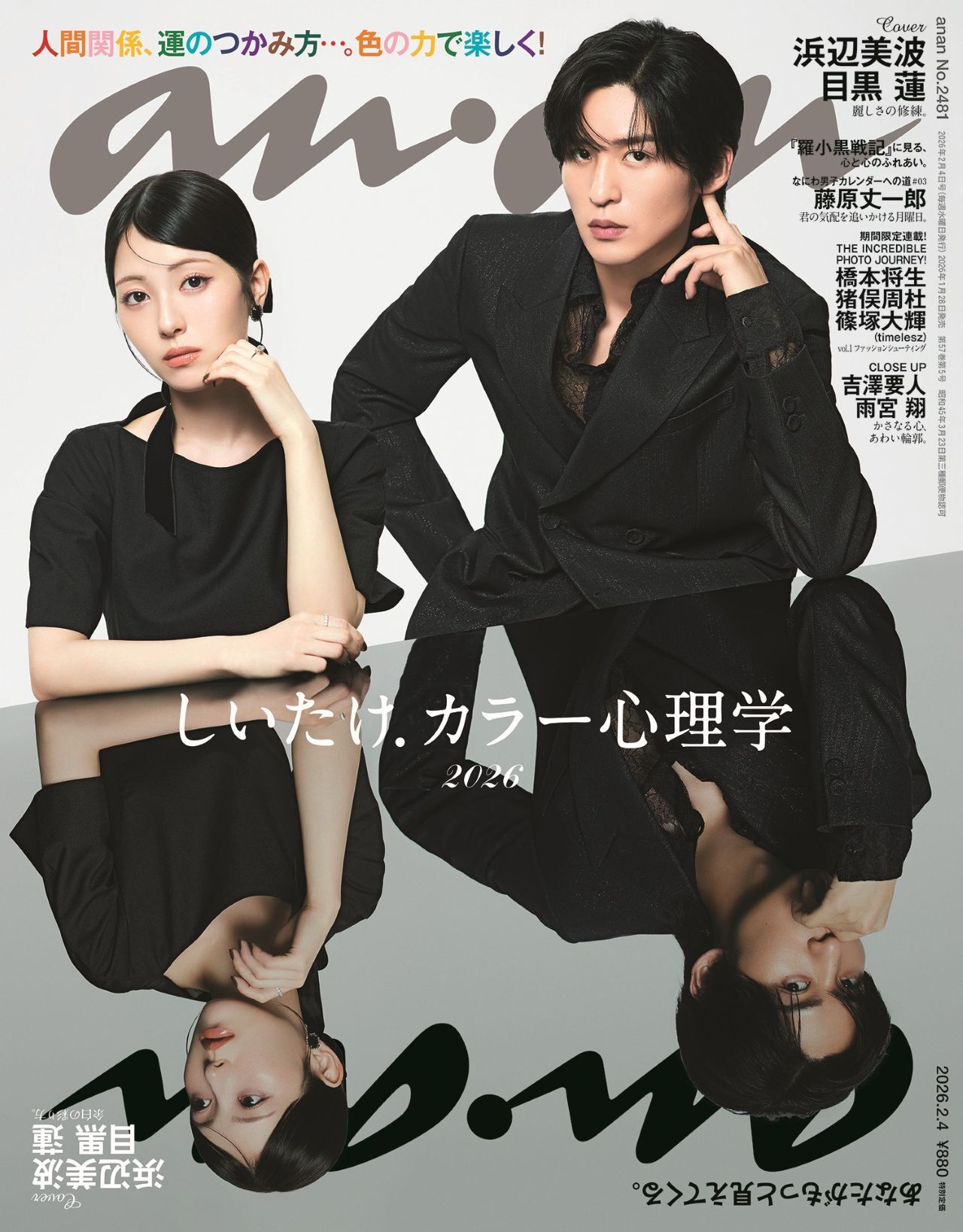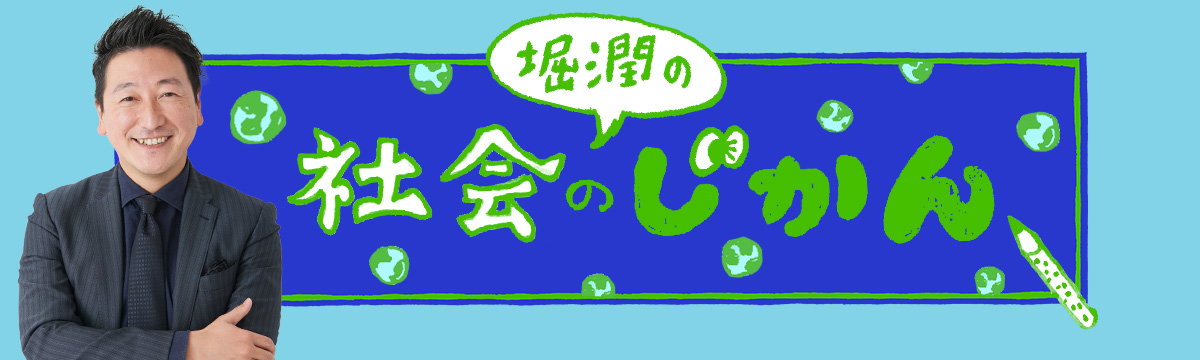
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「備蓄米」です。
米の消費の減少が大きな問題。長期目線で解決を。

政府備蓄米の売り渡し方式が、これまでの一般競争入札から随意契約に変更され、全国のスーパーやコンビニなどで、備蓄米の販売が始まりました。
米の問題の根本には、消費量の激減があります。令和6年の農林水産省の発表によると、主食用米の需要量は平成8年の944万tから702万tに減少。パンや麺を食べる人が増えたためと思われるかもしれませんが、小麦の1人当たりの年間消費量は昭和40年から令和2年の間で約3kgしか増えていません。実は食の多様化により、昔は漬物とご飯で空腹を満たしていたのが、肉や魚などおかずが増えて、主食の米の消費量が減っていきました。
米が不足している理由を取材すると、国と生産現場で見解が分かれました。農水省や農政族議員は、「米はあるが、流通過程で止まっている」と返答。業者が出し渋っているため米が市場に回らず、価格が上がってしまった。小泉農水大臣が古古米、古古古米を市場に出すことにしたのは、米の値段を下げることが大きな目的でした。
ところが生産者に聞くと「米はない」と言います。気候変動で良い米が穫れなくなっている。精米すると白い部分が多かったり、虫食いにより、一般に流通する一等米の量が減った、と。二等米でも十分おいしいので買ってほしいと言います。しかし、二等米は一等米の半分程度にしか値がつきません。米を作る技術が上がり、一等米と二等米の差がほとんどなくなっているのに、等級付けの選別方法が長年変わっていないという問題もあるんですね。
これまでは「日本の米はおいしい」というブランド力を保つよう、注意を払われてきました。ところが今回、古い米が広く流通するようになると、そのブランド力が下がり、米離れを加速させる恐れも出てきます。ただでさえ生産者が減り、後継者不足に悩んでいるところに、ますます米市場は狭まってしまうでしょう。かつては家族全員が米を三食食べていたのが、1日おにぎり1~2個では消費量は比べ物になりません。私たちがもっと積極的に食べるとか、輸出を増やすなど、米の消費量を増やす努力をしないと、根本的な解決にはならないと思います。
堀 潤
Profile
ほり・じゅん ジャーナリスト。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。『堀潤 Live Junction』(TOKYO MX月~金曜18:00~19:00)が放送中。新刊『災害とデマ』(集英社)が発売中。
anan2453号(2025年7月2日発売)より