海外文学を読み始めた頃。

島本:小さい頃は海外の児童文学も読んでいましたが、大人向けの海外文学を読み始めたのは中学生の頃ですね。カポーティの『遠い声 遠い部屋』などが好きで、そこからジョン・アーヴィングやカート・ヴォネガットといったアメリカ文学を読むようになりました。日本とは違う土地の広さとか匂い、空気を感じさせるものや、乾いた文体が好きでした。
上田:僕は中高生の頃に趣味で海外のファンタジーを読んでいましたが、大学生の時に村上春樹さんが訳したり影響を受けている海外小説を読み始めるというベタな人間で、僕もヴォネガットやカポーティ、フィッツジェラルドを読みましたね。そういえば、春樹さんの『風の歌を聴け』に、デレク・ハートフィールドって作家が出てくるじゃないですか。
島本:出てきましたね。
上田:彼の作品も読んでみたくて探したら、そんな作家は実在しないっていう(笑)。
島本:私も、そういう作家が本当にいるんだって思っていました。
上田:あれは、あの頃の文系少年少女がハマるトラップですね(笑)。僕はそれから大学生の時に作家になるために勉強しようと思って、体系的に200冊くらい読んだんです。その時にベーシックなものとしてシェイクスピアやドストエフスキー、ミラン・クンデラなどを読みました。
島本:海外のものが多かったんですか?
上田:そうですね。夏目漱石も読みましたが海外小説が多かったです。性格的に世界史と日本史だったら世界史を選ぶタイプですし。日本は世界の一部なので、グローバルスタンダードというか、読書も世界の基準に合わせたほうがいいんじゃないかなと思っていました。あまり文体の研究とか今の日本文学に何が起きているかは気にしなかった。今も読むのは海外文学が7割です。
島本:上田さんの小説には海外文学の雰囲気があるなと思っていました。少し重力が違うというか、自由な感じがして私、スペインに行く飛行機の中で上田さんの『私の恋人』を読んだんです。それがもう、しっくりきて、それこそ作中の世界の果てまで一緒に行ったような気がしました。
上田:ありがとうございます。
島本:私自身は海外小説と国内小説の割合は半々くらい。でも文体を学ぶのは海外小説が多かったです。日本の近代文学は私小説が多いですが、私は個人の内面よりも情景描写を書きたくて。それこそ一時はカポーティのような潮騒とかの比喩を書きたくて「さざ波のように」って表現をかなり使いました(笑)。
上田:サガンの『悲しみよ こんにちは』は読みました?
島本:はい。でも私、サガンよりもマルグリット・デュラスのほうが好きなんですよね…。
上田:僕、仕事の必要があって最近読み返したんです。あれって、アラフォーの恋愛を17歳の女の子の目線で描いているじゃないですか。19~20歳で読んだ時は少女の視点で読んだけれど、今読むと40歳のほうの目線になるので、大人たちが打算込みでいろいろやっているのがわかる。17歳からは今の僕もこんなふうに見られているのかな、って怖くなりました(笑)。
島本:確かに私も昔、100%少女の視点で読んだので、今読むと感じ方が変わるかもしれない。
上田:サガンよりもデュラスが好きというのは?
島本:昔読んだ時はサガンの主人公はただ生意気だなと思って。デュラスは同じ恋愛を書くにしても、絶望して達観した中に情熱や官能を秘めている。基本的に恋愛ものは絶望があるものが好きです。
上田:絶望のある恋愛もの…。
自分好みの海外恋愛小説。
島本:上田さんの『私の恋人』もそうですけれど、男の人が一方的に女の人を追いかける話も好きで、アンナ・カヴァンの『氷』は、氷の壁が迫ってくる世界で、超法規的な手段を使って地の果てまで好きな少女を捜しに行っては、フラれてすごすご帰る話。設定の大胆さとリアリティとのバランスが不思議な一冊です。グレアム・グリーンの『情事の終り』は嫉妬深い作家が、自分を振った女性に他の男ができたと思って調べ始める。信仰が絡んでくる話なんですが、キリスト教と恋愛小説の親和性って高いなと感じて、自分も宗教と恋愛というものを書いてみたくなりました。
上田:フランスのミシェル・ウエルベックやイギリスのイアン・マキューアンは読みます? この二人は僕にとって、淀んだヨーロッパの2大巨頭なんです。西洋文化はこの500年くらいのトレンドですけれど、今はもう煮詰まっている。その問題を書いている二人ですね。ウエルベックのほうが露悪的で原始的で欲望に忠実。たとえば『服従』はヨーロッパがイスラムのマネーや文化に服従していく話なんですよ。
島本:難しいけど面白そう。
上田:マキューアンの『土曜日』なんかは、脳神経外科医が認知症の母親をシステマティックに面倒を見たりする様子や、テロの脅威が描かれていく。彼らの作品のように“現実ってこうですよね”と突きつけてくるものが僕は好きだし、影響を受けていると思います。
『遠い声 遠い部屋』著:トルーマン・カポーティ 訳:河野一郎 590円(新潮文庫)
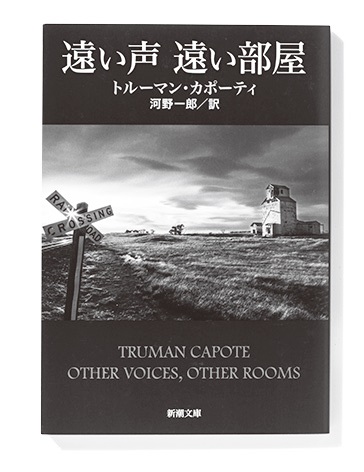
『ティファニーで朝食を』などで知られる、戦後のアメリカ文学を代表する作家が、23歳の時に書いたデビュー作。父を捜すためにアメリカ南部を訪れた少年を主人公にして、繊細なその心の内や街の風景を、鮮烈な比喩を用いながら綴った半自伝的小説。
『悲しみよ こんにちは』著:フランソワーズ・サガン 訳:河野万里子 490円(新潮文庫)

フランスの女性作家、サガンが18歳の時に発表したデビュー作。17歳のセシルが父と彼の愛人と過ごすコート・ダジュールの別荘にやってきた亡き母の友人、アンヌ。はじめは彼女を慕うセシルだが、父を取られると感じて反発、やがてある計画を思いつく…。
『氷』著:アンナ・カヴァン 訳:山田和子 900円(ちくま文庫)

著者はイギリスの小説家で、SFや幻想文学の色の強い作品で知られる。異常気象で寒波が押し寄せるなか、一人の男が異様な執着心で一人の少女を捜し求める。冷たくも美しい氷のイメージの中で、幻想と現実を交錯させながら描き出すディストピア小説。
『情事の終り』著:グレアム・グリーン 訳:上岡伸雄 670円(新潮文庫)
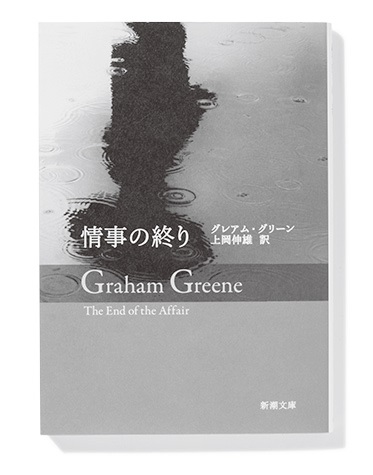
第二次大戦直後のロンドン。小説家のモーリスは、知人のヘンリーから妻のサラが浮気をしているのではと相談される。実は以前、モーリスはサラと不倫関係にあり、彼は一方的に別れを告げられた身。サラの今の浮気相手を知ろうと調べ始めるのだが…。
『服従』著:ミシェル・ウエルベック 訳:大塚 桃 920円(河出文庫)
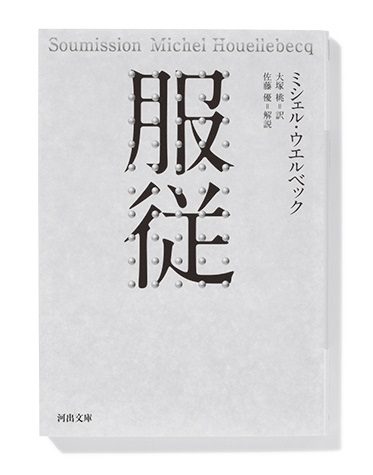
センセーショナルな作品を発表し続けるフランスの現代作家の長編。舞台は2022年、極右政党を倒して穏健派のムスリム政党が政権を握ったフランス。文学教授の「ぼく」は、パリを去ることにするが…。テロ、移民といった現実問題を盛り込んだ予言的な作品。
うえだ・たかひろ 作家。1979年、兵庫県生まれ。2013年「太陽」で新潮新人賞受賞。'15 年『私の恋人』で三島由紀夫賞、今年『ニムロッド』で芥川賞受賞。新作は世界文学的大作『キュー』。
しまもと・りお 作家。1983年、東京都生まれ。2001年に『シルエット』で群像新人文学賞優秀作に入選。'03年『リトル・バイ・リトル』で野間文芸新人賞、'18年『ファーストラヴ』で直木賞受賞。
※『anan』2019年7月10日号より。写真・小笠原真紀 取材、文・瀧井朝世
(by anan編集部)

※旅好き女子が大注目!次の海外旅行をメルボルンにする5つの理由って?
[gunosy]
#男の本音 について、もっと深く知りたい![/gunosy]



































