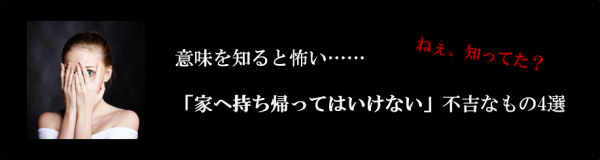11月某日、彩の国さいたま芸術劇場稽古場。「違うよ。この言葉を言う意味をもっと考えろ」。吉田鋼太郎さんのよく通る大きな声が響く。この劇場を拠点に、蜷川幸雄さんが続けてきた「彩の国シェイクスピア・シリーズ」を、2代目芸術監督として引き継いだ吉田さん。高校生の時に観たシェイクスピア劇に感銘を受けて俳優を目指し、出演するばかりでなく、自身が所属する劇団で数多くのシェイクスピア作品を演出してきた、名実ともにシェイクスピア俳優。絶賛稽古中の『アテネのタイモン』が、記念すべき就任第1作となる。
――稽古場で、ときおり語気を強める場面もありながら、場がピリッとした途端、「ごめんごめん」と笑いながら空気を和ませていらっしゃる姿が印象的でした。
吉田:蜷川さんがよくデカい声で怒鳴っていたので、それがないと蜷川さんの稽古場じゃない気もして。まあ…それを口実に怒鳴っていたりもするんですが(笑)。
――ただ、吉田さんが声を荒げていたのは、俳優が何の考えもなく動こうとした時ですよね。
吉田:シェイクスピアの戯曲って、美しい詩の形態をとっているから、セリフを口にした時点で俳優は満足してしまうところがあるんです。その言葉が、誰に対して、どういう気持ちで発せられたのかが、ないがしろにされがちなので、そこを僕は丁寧にやりたいんですよ。
――そもそもこのシリーズは、シェイクスピアの全37作上演を目指して蜷川さんが始めたものです。誰かが引き継がなければいけなかったとは思いますが、この大きすぎるバトンをご自身が受け取ることに迷いはありませんでしたか?
吉田:僕は蜷川さんのこのシリーズにたくさん出させていただき、いくつも主演もさせていただいています。シェイクスピアをやり続けてきた自分の役者人生にとって、このシリーズは大きな位置を占めているもので、これを止めたくないという気持ちが大きかったんです。5本を残して蜷川さんは亡くなられましたけれど、もし蜷川さんが生きていて、全作達成されたとしても、そこで終わってしまうのは嫌だった。それくらいこのシリーズには愛着があるので、その後を自分が引き継がせてもらえるのは願ったり叶ったりでしたし、そうじゃなくちゃいけないとも思いました。もちろんプレッシャーはありますけれど、それは蜷川さんの後継だという部分。シェイクスピアを演出することに関してのプレッシャーはなかったです。
――ただ、残った5本はシェイクスピア作品のなかでも、あまりメジャーではない戯曲ばかりです。
吉田:確かに、ただ読むだけでは面白さが伝わりづらい戯曲かもしれません。ただ、僕は芝居になった時の面白さを知っていますから、この機会に、その面白さを伝えられたらと思っています。
――ちなみに、このシリーズだけでなく、劇場の芸術監督も引き継ぐお考えはなかったんですか?
吉田:そんな話もなかったし、もしあったとしても絶対に引き受けないですよ。そうなったら、役者業をやる暇なくなっちゃいますから。このシリーズには俳優として出演しますし、年に1本はシェイクスピアをやりたいという僕の希望とも合致するからやっているわけで。ただ、実際に演出と俳優を兼ねてみると大変で、演出だけ引き受ければよかったと思っています。
――そう思いながらも、やっぱり出たい気持ちはあるわけですか?
吉田:そりゃあ、演(や)るのが本業ですからね。ただ、シェイクスピアに関しては、自分の好きなように演出してみたいっていう欲がすごく強くあるんです。他の戯曲は、これっぽっちも演出したいと思わないのに。だから、演出するのはシェイクスピアオンリーです。

――シェイクスピアの何がそんなに魅力的なんでしょう?
吉田:ト書きがないから制約がないし、解釈も自由。だから自分の状態や年齢で、同じ戯曲でも違う見え方になってくるのが面白いですねぇ。
――世界各国に、いろんな演出のシェイクスピア劇が生まれていますが、それも刺激になりますか?
吉田:昔はありましたよ。でも…他の方の演出で面白いと思ったことはほぼないです。日本で上演されたもので面白いと思ったのは、蜷川さんのシェイクスピアくらいです。
――それは何が違うんでしょう?
吉田:シェイクスピアを演じる時の俳優のありよう、というのかな。蜷川さんは、俳優にマックスを求めるんですね。それは感情も声も、とにかく体全体、持てるもの全部を使ってやらないとシェイクスピア作品は表現できないんだっていう考え方で、僕はそれとまったく同意見。リアリズムだけでは成立しない、それを越えたところに生まれるものを舞台の上に立ち上げることが大切なんです。そこの共感があるから、僕なら蜷川さんの後を継がせてもらえるかなと思ったんです。
――その共感は、最初に蜷川作品に出演した時からありました?
吉田:やろうとしている方向性は同じでしたが、蜷川さんの現場はスケールが違いました。いままでの1.5倍は頑張らないと通用しないから、毎日が死に物狂い。でも、蜷川さんの洗礼を受けてそれを乗り越えると、俳優としてひと回りもふた回りも成長できる。それは小栗旬も、松坂桃李も、溝端淳平も感じていたと思います。そんな現場って他にない。しんどいんだけれどまたやりたくなるっていうのは、そういう理由なんです。
――蜷川さんは、それだけ大きな存在だったということですよね。
吉田:いままさに、存在の大きさをあらためて実感しているところです。稽古で蜷川組の面々と対峙すると、彼らがものすごく大きなものを持ってくるんですね。それに相対するには、連日自分のエネルギーを1段上げないといけない。いまの僕は、ものすごく厳しい父親に、大きな試練をひとつ課されて去られたような、そんな感覚です。
吉田さんが演出・主演を務める舞台、彩の国シェイクスピア・シリーズ第33弾『アテネのタイモン』は、12月15~29日、さいたま芸術劇場 大ホールにて上演。’18年1月には兵庫でも公演あり。出演者には吉田さんのほか、藤原竜也さん、横田栄司さんら蜷川組常連キャストが名を連ねる。SAFチケットセンター TEL:0570・064・939
※『anan』2017年12月20日号より。写真・内田紘倫(The VOICE) インタビュー、文・望月リサ
(by anan編集部)
【人気記事】
※肌荒れ予防や脂肪をつきにくくする食物繊維 アボカドはそのまま食べずに…