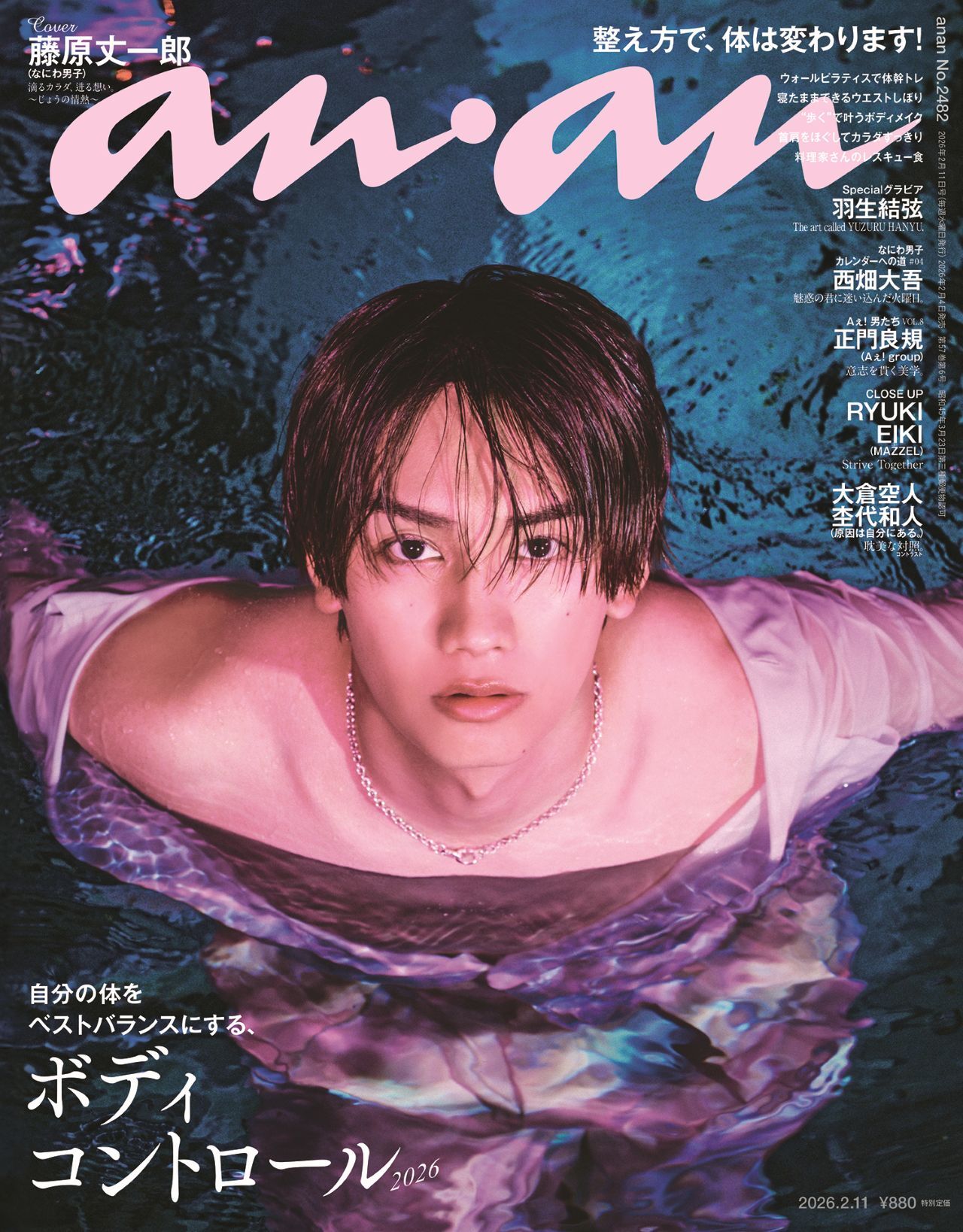昨年、韓国のハン・ガンさんがアジア人女性として初めてノーベル文学賞を受賞し、大きな話題となりました。また、柚木麻子さんの『BUTTER』は王谷晶さんの『ババヤガの夜』と共に英国推理作家協会賞(ダガー賞)の翻訳小説部門の最終候補作に選ばれたほか、イギリスで3冠を受賞、40万部のベストセラーとなっています。
そうした東アジアの作家の活躍は、いったいどうして起こっているのか? その秘密が知りたい! と思い、出版関係者3人と柚木麻子さんに取材を行いました。
まずお話を聞いたのは、日本ユニ・エージェンシーの浦田理子さん。浦田さんは日本の作品を海外展開するお仕事をされています。印象的だったのは、ひとたび英訳されると、そこからどんどん他の言語にも翻訳されていくというお話。私は、日本語から異なる言語へと直接翻訳されるものとばかり思っていたので、英訳されたものがまた別言語に翻訳されるというのは、目から鱗でした。また、今回本誌では紹介しきれませんでしたが、日本のレシピ本も海外では人気だそうで、その理由は分量や手順がきっちりと書かれていることにあるよう。日本人のある種の真面目さがつまったレシピ本が海外で受け入れられる、というのは面白いと思いました。取材後には、保管されている日本の作家の翻訳本を少し見せていただくことに。同じ作家の同じ作品でも、言語などによってカバーが異なるのも面白い! 恩田陸さんの『ユージニア』は、日本語の文庫版では赤い花と旧家のような少し暗めの写真ですが、海外版では少女が背中に花を持っている後ろ姿の写真。海外書影と比較するのも楽しいのでおすすめです。
続いてお話を聞いたのは、翻訳家の竹森ジニーさん。竹森さんは村田沙耶香さんの作品を数多く翻訳されていらっしゃいます。過去、文学研究の文脈で男性作家の作品ばかりが翻訳されていた(男性作家の翻訳作品10冊に対して、女性作家の翻訳作品は1冊強だった)中で、その潮目が変わったのは、実は竹森さんのようなプロの翻訳家の方々の地道な活動にあったのです。竹森さんは同じく翻訳家の仲間と「Strong Women, Soft Power」を結成。東京でシンポジウムを開催するなど徐々に活動を広げていき、実際に女性作家の翻訳本も増えていったのだそう。今、日本の女性作家たちが海外で広く読まれている背景には、翻訳家の方々の力があることも忘れてはいけません。
そして紀伊國屋書店でパシフィック・エイシアン地区を統括し、マレーシア店の店長も務める里見幸一郎さんからはリアルな読者の動向を教えていただきました。印象的だったのは、すでに日本のマンガやアニメなどのコンテンツが受け入れられる土壌があった中で、コロナ禍を経て文学にも手を出す人が増えたのではないか、というコメント。ちょうどTikTokなどで本を紹介するインフルエンサーが増えた時期とも重なりそうです。複合的な要因が絡み合って、いまの東アジア文学の広がりが生まれていることに驚きと面白さを感じたと同時に、今後どのようになっていくのかを注視していきたいと思いました。
そして、海外で話題の作品を生み出した当事者の方にもぜひインタビューをしたい、ということで柚木麻子さんにもお話を伺いました。柚木さんはこの日、ニュージーランドで購入した「BUTTER」のキャップに、イラストレーターのご友人・澁谷玲子さんが作った「BCF(Butter Cream Fan club)」のTシャツ姿で登場。誌面ではモノクロの写真が掲載されていますが、ananのXではカラー版も公開予定なのでぜひお楽しみに。インタビューでは、オーサーズツアーや文学祭で訪れたイギリス、オーストラリア、ニュージーランドなど各国で感じたことをたっぷりと語っていただきました。軽快なトークで取材場所を笑いで包んでくださり(海外ドラマを吹替で見るのが好きという柚木さんは、海外で話しかけられると、ご自身の脳内で吹替風にアテレコしていらっしゃったそう!)、気づけばあっという間に時間が過ぎ去っていました。4000文字にも及ぶロングインタビューを、ぜひ誌面でご覧ください。(HM)