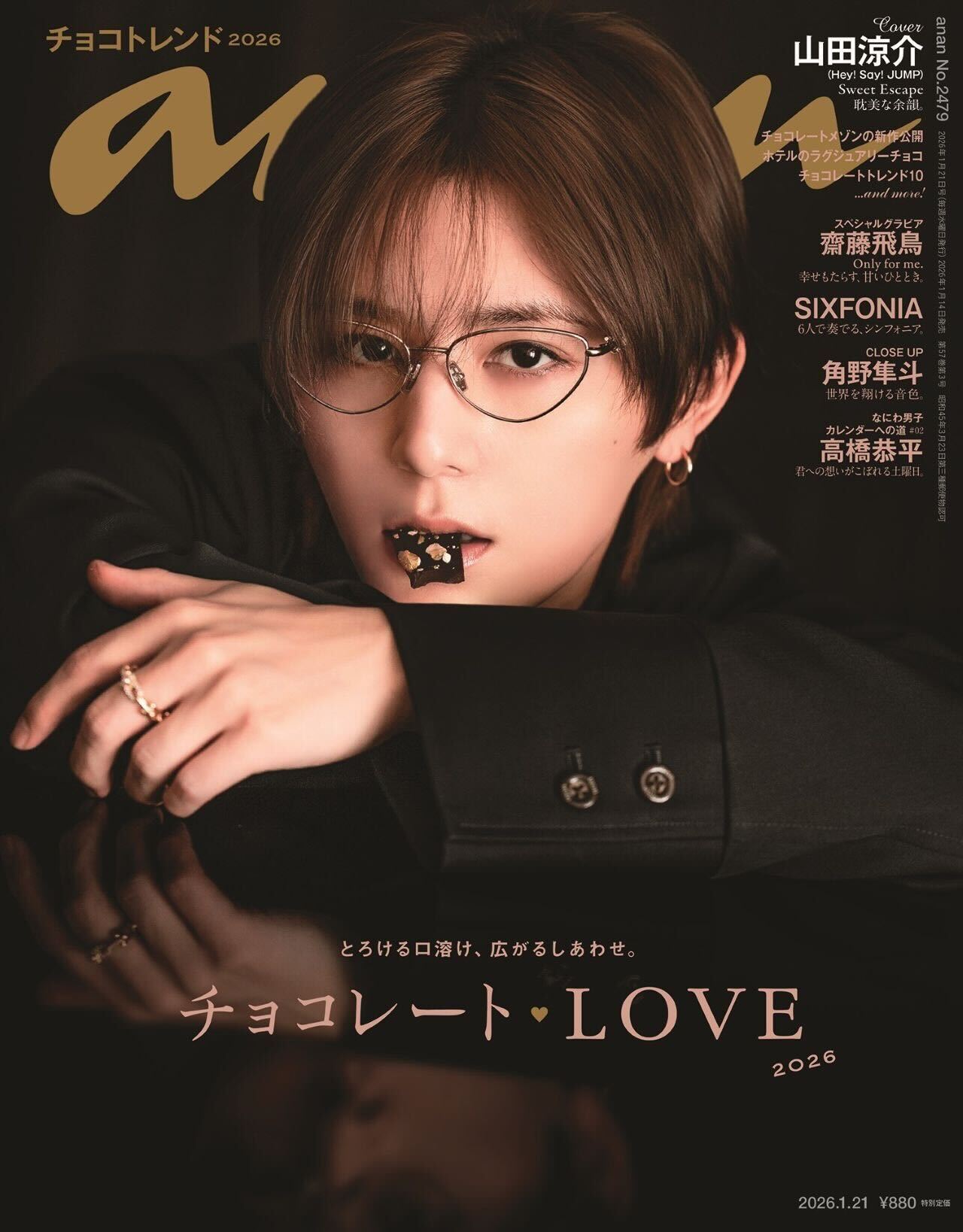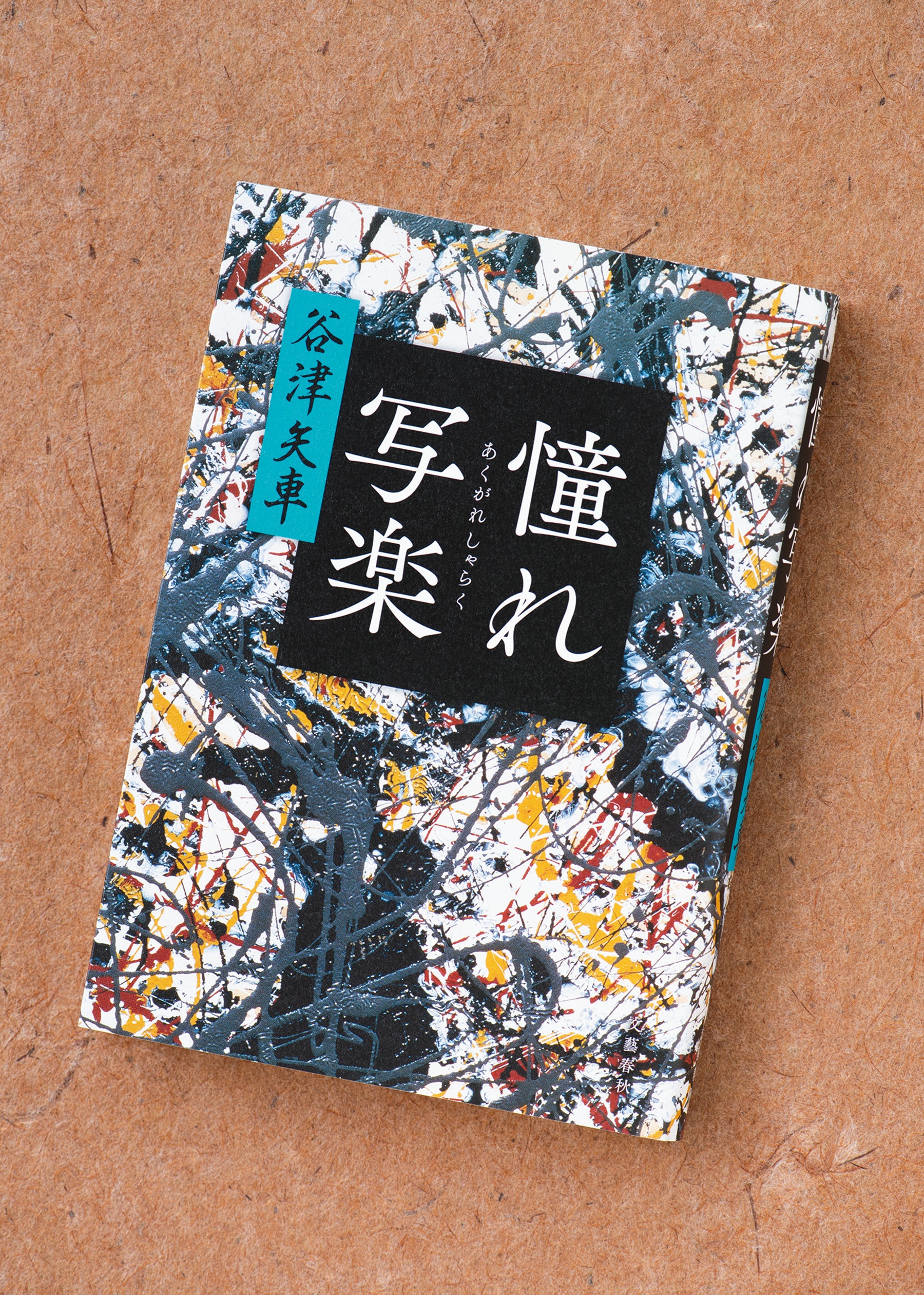
谷津矢車『憧(あくが)れ写楽』
江戸中期の寛政6年、鮮烈な役者絵で一世を風靡した東洲斎写楽。だが、彼のデビューも突然なら表舞台から姿を消したのも突然。活動期間も短い。あまりにミステリアスな存在として、これまでにも写楽の謎をめぐる作品が生まれてきた。
写楽とは何者なのか。新たな視点で照らす、時代小説×アートミステリー。
「研究が進み、今日の歴史学では写楽=猿楽師の斎藤十郎兵衛(さいとう・じゅうろうべえ)説で決まりなんですよね。歴史ファンとしての僕はそれでよかろうと思っていますが、物語ファンとしては、たとえば海外の『シェイクスピア別人説』や『切り裂きジャックの正体』みたいなものが何度も蒸し返されるのは楽しいわけです。高橋克彦さんや泡坂妻夫さん、島田荘司さんなど先達が挑んだように僕も僕なりの写楽の正体を描いてみたいと思いました」
谷津矢車さんの『憧れ写楽』で語り手となるのは、江戸の老舗版元「仙鶴堂」の主、鶴屋喜右衛門(つるや・きえもん)。周りから〈鶴喜さん〉と呼ばれる彼が、斎藤十郎兵衛に新作の依頼をしたところ、斎藤から「写楽の代表作『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』をはじめ幾枚かの肉筆画は自分の作ではない」と打ち明けられ仰天。本物の写楽は別にいると見立てた喜右衛門は、喜多川歌麿(きたがわ・うたまろ)とともに「本物の写楽」捜しに乗り出す。だが、なぜか写楽を世に出した「耕書堂」の主、蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)が妨害してきて…。誰が写楽かという特定だけでなく、写楽の正体が隠されなくてはならなかった理由にも迫っていく点が読みどころ。
「進行上難しかったのは、探偵役であり狂言回しも担う喜右衛門の人物像をつかまえることでした。蔦重、歌麿、山東京伝(さんとう・きょうでん)、狂歌師の大田南畝(おおた・なんぽ)や唐衣橘洲(からころも・きっしゅう)…本作に登場するのはほぼ全員、逸話がある江戸期の有名人。仙鶴堂は三代目がわりと傑物として知られているのですが、当の二代目についてはほとんど記録がないんです。逸話を中心に組み立てていけば人となりが見えてくるのとは違い、喜右衛門だけは僕自身が組み立てていく必要があったので大変でした」
また、版元たちや絵師たちなどの物語としてだけでなく、倹約や風紀にうるさかった時代の出版事情や世相についても浮かび上がってくる。
「一世代上の蔦重は、今でいう出版バブルを知る世代なんです。ところが喜右衛門のころになると浮かれていられない。そんな世代間格差も書き残したかったんですよね」
何重にも楽しいエンタメだ。
Profile

谷津矢車
やつ・やぐるま 1986年、東京都生まれ。作家。2013年に『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』でデビュー。大河ドラマ『べらぼう』の主役である蔦屋重三郎の人生に迫った『蔦屋』ほか著書多数。
Information
谷津矢車『憧(あくが)れ写楽』
写楽の正体をめぐるトリックに関しては、石森章太郎のマンガ『佐武と市捕物控』の中で、写楽が出てくるストーリーに着想を得たそう。文藝春秋 1980円
anan 2435号(2025年2月19日発売)より