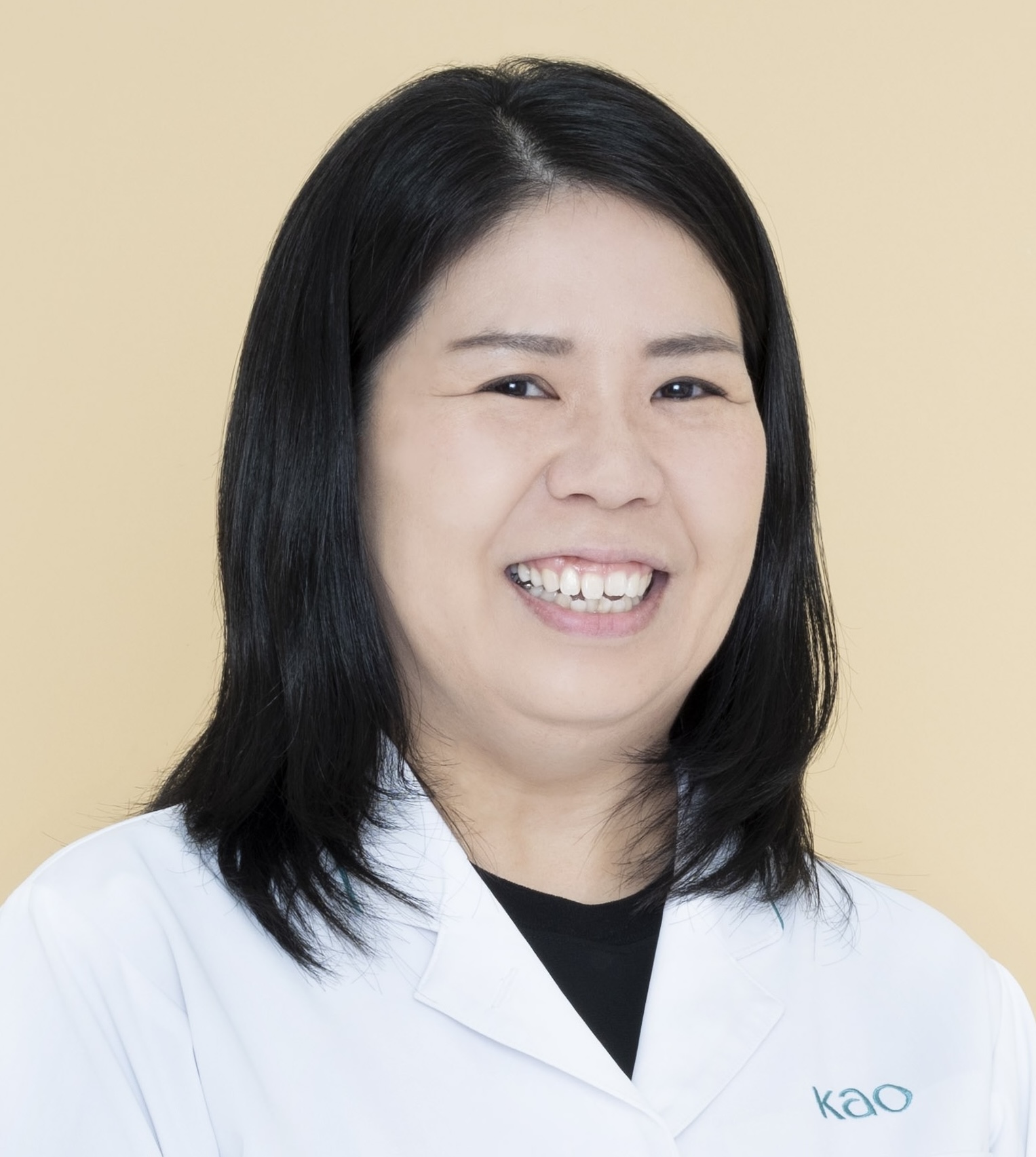anan総研メンバーが学びます!
左から、anan総研No.410・奥山夏織さん(36歳・会社員)。「一年中冷え症で、月経時には体調を崩すことも。むくみやすいのも悩み」/anan総研No.018・柴本愛沙さん(43歳・気象予報士)。「生活が不規則だからか、眠りが浅かったり、眠っても疲れが取れない。カラダを温めたくて生姜を摂るようにしているけど、正直あまり好きではなくて…」/anan総研No.187・渡辺由布子さん(41歳・ヨガインストラクター)。「ヨガを仕事にしているから運動不足ではないはずなのに、肩と首のコリが一向に改善されません!」
anan総研とは?
anan総研は、ananの誌面やデジタルで活躍する読者代表組織。女性たちのライフスタイルやいまの考えをデータと座談会で表現するリサーチ連載など、ananの各所で活躍しています。
anan総研メンバーの「なんとなく感じる不調」
仕事やプライベート、日々忙しく過ごすなかで「なんとなく不調だな…」と感じることってありますよね。まずはanan総研のメンバーたちに、最近どのような不調に悩んでいるのか、女性たちの本音を聞いてみました。
眠りが浅いのか、睡眠をとっても疲れが取れていないなと感じることがよくある。慢性的な肩こりも悩みで、頻繁にマッサージに行ってるんだけど全然良くならないんだよね。
わかる〜。私も、肩と首のコリが悩み。日常的にヨガをしているから、ストレッチもできていると思うんだけど、なかなか改善されない。最近は、目の疲れや歯の食いしばり癖も気になる。
私は、手足の冷え。オフィスで特に冷えるなと感じることが多くて、月経期間は体調不良になることもあるんだよね。お風呂で湯船に浸かる時間がないのがいけないのかもしれないんだけど…。むくみやすいのもなんとかしたいな。
冷えるのはよくないってわかっていても、職場だとどうすることもできないよね。私も不調を感じても、忙しいとそのままにしてしまうことが多いかも。
ライフスタイルや日々の習慣によっても、不調は変わってくるようです。不調に関して、anan総研メンバー200人に調査を実施しました。その結果は?
Q. あなたは今、どのような不調を感じていますか?
20代〜40代の女性が集まるanan総研メンバーたちの間で最も多かった不調は「疲労感」。そして同列では、「なんとなくの不調感」。「なんとなくカラダが重かったり、なんとなく体調がよくない日が多いです」(30歳・公務員)と、病状を言葉にしにくい、「なんとなく」調子がよくない人が多いようです。
私たちと同じ悩みを抱えている人が多いね。私も疲労感が取れないことが多いからすごくわかる。なんとなく調子が悪いなーと思っても、何をしたらいいかわからないってことも正直あるかな。
末端の冷えを感じている人も多いんだね。手先や足先が冷えて寝つきがわるくなったりもしそう。
「不調の原因は、血流の詰まりが原因?」。専門家に聞きました
カラダの不調って、原因がわからないこと、そもそもどのように改善したらいいかわからないという人は多いのではないでしょうか。そこで、内科医であり温活ドクターの石原新菜先生、そして、花王株式会社の研究員である田上恭子さんにお話を伺いました。花王は、30年以上も前から、血流循環や蒸気温熱による血めぐりケアの研究を行っているそう。
現代の東洋医学では、病名がつかないと病院で治療ができません。そのため、不調や疲れをそのままにしてしまっている人は多いと思います。ですが、肩こりやむくみ、手足の冷えなどの不調を頻繁に感じる場合は、健康と病気の間の「未病」である可能性があるんです。
私は手足の冷えが原因で悩むことが多いんですが、そのまま放置しないほうがいいのでしょうか?
未病は、「血流の詰まり」からくる「冷え」が原因なことが多いです。自分が未病の段階にいることに気がつかず放置してしまうと、病気につながってしまう可能性もあるので、辛いようであれば放っておかないほうがいいです。対策するには、とにかく「血めぐり」を良くすることが大切。血流が滞ってどこかに「詰まり」を感じていると、頭痛などの痛み、コリや冷えの症状として現れることもあります。健康の土台を底上げするためにも、まずは日々の生活のなかで「血めぐり」を意識してみてください。
「血流の詰まり」が、肩こりやカラダの痛みの原因になることもあるんですね…。「血めぐり」についてもっと詳しく知りたいです!
「血めぐり」って何?
「血めぐり」とは、カラダの中心から末梢まで全身に血液がめぐっていることを言います。その役割としては、カラダに必要な酸素や栄養分の供給や、二酸化炭素や老廃物、発痛物質など不必要な物質の回収などがあり、「血めぐり」は健康だけでなく、生命の維持を司る重要な循環システムといえます。
血のめぐりって、健康の基礎になっているんですね。まずはどんなことから始めたらいいですか?
湯船に浸かることや、食事に生姜を取り入れることなど、毎日の自分の生活に取り入れやすいことから始めてみるのがいいと思います。首もとや目もとを温めるのもおすすめですよ。
花王の研究では、「蒸気温熱で目もとを温めると、手や足の末梢部の血流が良くなる」というデータが実証されています。目もとを約40℃くらいの心地よい蒸気温熱で温めると、副交感神経活動が高まりリラックス効果が得られるんです。心身がリラックスすることで、手足の血管が緩み、血流促進が期待できます。
目もとを温めた場合、目もとだけが温かくなるんだと思っていました。目もとを温めることで、手足の末端まで血めぐりが良くなるということですか?
はい、その通りです! 目もとを温めると、末梢部の血めぐりが良くなるって、驚きですよね。その結果として、手足の冷えが緩和したり、それに伴って寝つきが良くなる効果も期待できます。その際、効果的に血めぐりを良くするには、「蒸気温熱」でカラダを温めるのがコツです。
温め方にも違いがある! 蒸気温熱と乾熱の違い
熱で温める方法としては、蒸気を含む温熱の「蒸気温熱」で温める方法と、蒸気を含まない温熱の「乾熱」で温める方法があります。身近なものに例えると、街の銭湯にあるドライサウナは「乾熱」、ご自宅によくあるミストサウナは「蒸気温熱」です。乾熱と蒸気温熱では熱の伝わり方が異なります。「乾熱」で温かい空気が拡散することで熱を皮膚に伝えるのに対して、蒸気を介して熱を皮膚に伝えます。空気よりも蒸気のほうが、熱伝導率が高く、多くの熱を伝えてくれるため、効果的にカラダを温めることができます。
自宅でやるなら、「簡単目もと温活ケア」がおすすめ
目もとを温めることで詰まりが良くなり、血めぐりケアができることを知ったanan総研メンバー。最後に、具体的にどんなケアをすべきかについても聞いてみました。

目もとを温めるなら、濡らしたタオルを電子レンジなどで温める蒸しタオルを使うのが便利だと思います。大切なのは、気持ちいいな〜と感じる状態をキープすること。血流によって詰まりが良くなると、いま抱えている不調に、効果的にアプローチをすることができますよ。
実は、目もと周辺や顔には、「三叉神経」と呼ばれる知覚神経が分布していて、冷感や温感を含む温度感覚や触覚などの感覚を脳に伝えていますが、目もとは心地よい温度をより感じやすい部位なのではないかと考えています。副交感神経を高めて心身ともにリラックスすることが大切なので、熱すぎるタオルではなく、お風呂のお湯のような40℃くらいの心地よい温度を保って行うといいですよ。
健康の土台を作ってくれる「血めぐり」。まずは目もとから!
目もとを温めるとリラックスできる感覚はすごくわかるし、温まるとホッとして落ち着きました。今までの不調は、詰まりがあったからだったと自覚できたので、これからは不調を放置しないように気をつけます。
今までは不調を感じても、その場しのぎのケアしかできていなかったけど、目もとを温めることは根本的なケアにつながるんですね。詰まりを溜めないために、ルーティンにしたいと思います。
私も、毎日のケアに取り入れていきたいと思います。血めぐりを意識して、冷えが解消されたらいいな。
とにかく健康を意識するなら「血めぐり」です。血めぐりを意識して、健康な人が増えてほしいです。
石原先生のお話にもありましたが「血めぐり」は健康の土台となる力だと、私たちも感じています。病気になってしまった場合には薬で治療することが重要ですが、「未病」といわれる段階では、日々のケアが何よりも大切です。自分自身で健康になる力を高めて、健やかな毎日を送っていただけたらと思います。
「なんとなく不調かも…」と感じたときこそ、「血めぐり」を意識してみてはいかがでしょうか。