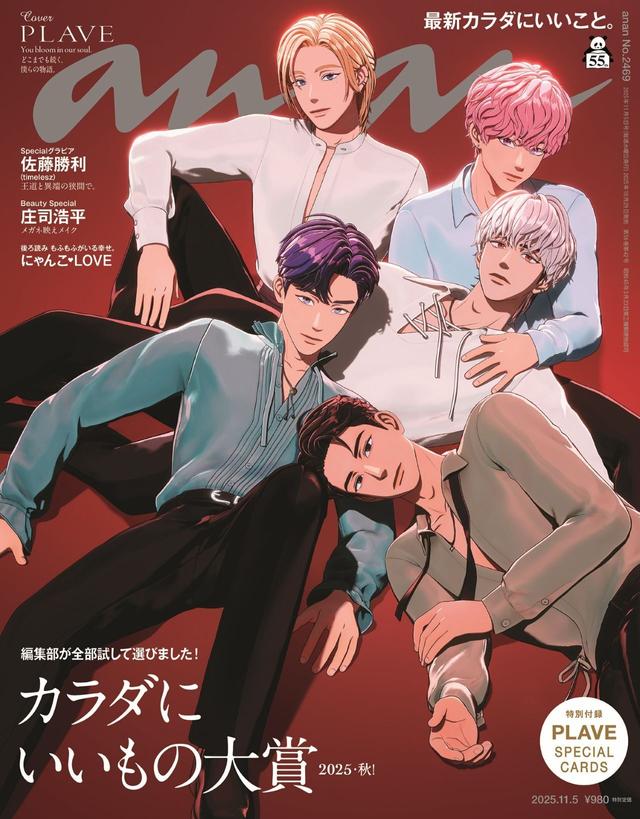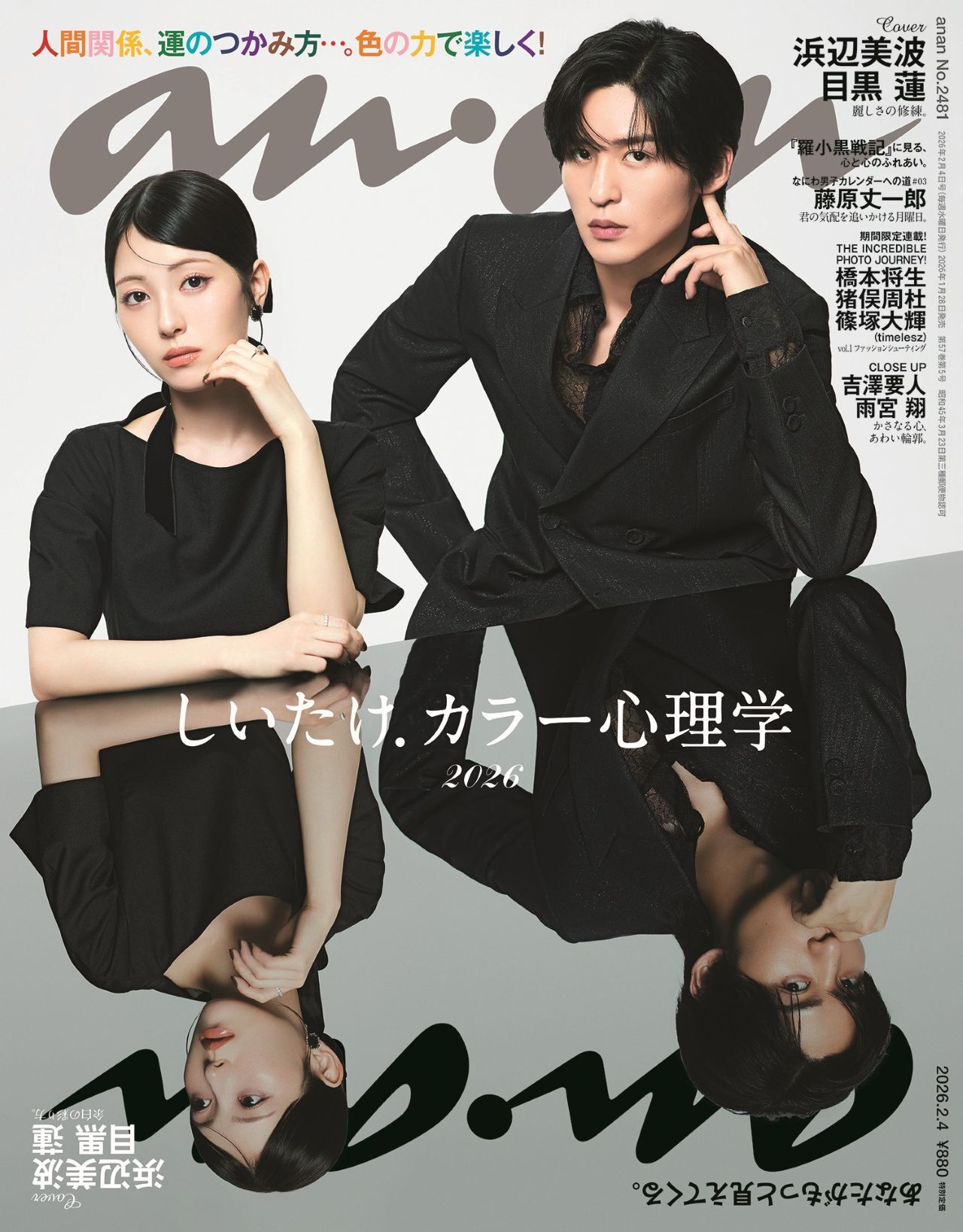猫を迎えたいと思っている人だけでなく、すでに同居中の人も改めて見つめてほしい、愛する猫との健やかで幸せな暮らしを守るために飼い主がすべきこと。
Index
健やか&幸せなにゃんこ暮らし入門

1、【生活環境】猫が安心安全に暮らせる空間を作ることが大切
「猫は人よりも家につく」とはよくいわれるけれど、実際に猫は場所に強いこだわりを持つ。そんな猫と暮らし始めるなら、安心安全な生活環境に整えることは飼い主の重要ミッション。
「猫がストレスなく過ごせる空間を作ることが大切です」と語るのは、獣医師の窪木未津子さん。
「たとえば、猫にとって優先度が高いのは走り回れる広さよりも、上下運動ができること。猫は基本的に高い所が好きですし、若いならばなおさら。キャットタワーを設置したり、家具の高低差を生かして、猫の欲求を満たせるようにしてください。そして、温度や湿度にも気配りを。人間が快適と思える温湿度を目安に、夏や冬は外出時でもエアコンで調整してあげましょう」
また、常に新鮮な水が飲める器や、頭数+1つのトイレ…。日々使う必需品は色々あるものの、忘れてはならないのがケージ。
「家に迎え入れる時は必須。猫は初めての広い空間に、いきなり放り出されても戸惑うだけ。むしろケージがあったら自分のテリトリーとなって、安心して周りの様子が窺えるし、私のこれまでの経験上、飼い主さんとの距離も縮まりやすい気がします。そして、留守番の時には、イタズラや誤飲防止にも。狭い所に閉じ込めるのは可哀想と言う人もいますが、知らぬまに危険なものを口にしたらそれこそ一大事。猫が家に慣れるまで、飼い主さんもその子の性格がある程度わかるまでは、ケージはあったほうがいいですね」
2、【災害対策】避難所生活に対応できる体調管理と備えを日頃から
地震、台風などによる水害…災害はいつ何時、起きるかわからない。だからこそ、家族の一員として迎える以上、猫のためにも日頃から備えを。
「フードやトイレ用品などはもちろんですが、持病がある子は薬も忘れずに用意を。災害時には薬は入手しにくくなるので、ローリングストックしながら2週間分くらいは余裕を持って常備して」
また、自宅避難が難しい時のために、ペットと同行避難できる一番近い避難所を確認しておくことも必要。ただし、避難所では猫はキャリーやケージ内での生活を強いられるケースが多い。
「猫が安心して過ごせるように、キャリーやケージに慣らしておきたいですね。普段からリビングに置いてベッド代わりに使うなど、リラックスできる場所として認識してもらいましょう」
そのほか、ワクチンやノミ・マダニなどの予防医療も普段から施しておきたいもの。
「ペットを連れて同行避難をするならば、感染症対策するのは大前提。完全室内飼いの猫でも、病気リスクはゼロではありません。また、マイクロチップをつけておくと、万が一飼い主とはぐれた時に見つけやすくなります」
3、【健康管理】異変に気づけるように日々の観察と定期検診を
愛猫にできるだけ元気で長生きしてもらうためには、飼い主による健康管理が欠かせません。
「日頃からスキンシップをとり、毛艶や目やに、そして食欲、排泄、呼吸、活動量など愛猫の様子を観察することが大切。特に体重はバロメーターになるので、こまめに量ってください。記録しておくと、異変に気づきやすくなります」
さらに、外に出ることがない猫は動物病院が苦手な子が多いけれど、健康診断も年に1度くらいは受けておきたいところ。
「病気の早期発見のためにも、元気な時から健康診断を受けて、ベースとなるデータをとっておくことが大事。具合が悪くなってからの受診では遅いんです。信頼できるかかりつけ医を見つけ、猫も顔見知りになっておけば、診察のストレスも少しは軽減できると思います」
また、病気への備えとして、ぜひ検討してほしいのがペット保険。
「猫が病気やケガをした時、状態によっては手術や入院を余儀なくされたり、治療費が高額になることも。そんな時、保険に入っていると経済面でのサポートになるし、治療も前向きに検討できるのではないでしょうか。もちろん、日常生活で少しでも気になることがあった時、保険に入っていると病院でドクターに相談しやすくなるのも大きなメリット。病気を発症してからや高齢になると保険には加入しにくくなるので、若くて元気なうちに検討してください」
4、【万が一の時】信頼できるお世話人をきちんと見つけておくこと
不慮の事故や病気などによる緊急入院、突然の災害に巻き込まれるなど、もし自分の身に万が一のことが起きた時、愛猫はどうしたらいいのか? 猫と一緒に暮らす以上、その対策をきちんと考えておくことも飼い主の責務。
「家族や友人に預けたり、信頼できるペットシッターを頼んで自宅でお世話をしてもらう、医療ケアが必要ならばペットホテル併設の動物病院に預けるなど。方法はさまざまあるので、猫の体調や性格、そして予算などを考慮して決めてください。いずれにしても実際に緊急事態が起きてしまった時に、初めましてでは遅すぎます。旅行する時などに面倒を見てもらったり、病院なら健康診断へ行くなど、普段から時々、愛猫とコミュニケーションをとってもらうことが大事です」
さらに「飼い主もそのような事態に備えて、猫が自宅にいることや緊急連絡先を記したメモを財布などに入れて、常に携帯してほしい」とも。
考えたくないことだけど、元気なうちにちゃんとシミュレーションをして、対策を講じておくこと。それが、いざという時に自分も周囲も慌てず、猫を守ることにつながる。
お話を伺った方
Profile
窪木未津子
獣医師。「富士見台どうぶつ病院」院長。2024年には猫専門の「ねこの森 富士見台どうぶつ病院」も開業。保護猫活動の拠点としても力を入れ、譲渡も行っている。
anan 2469号(2025年10月29日発売)より