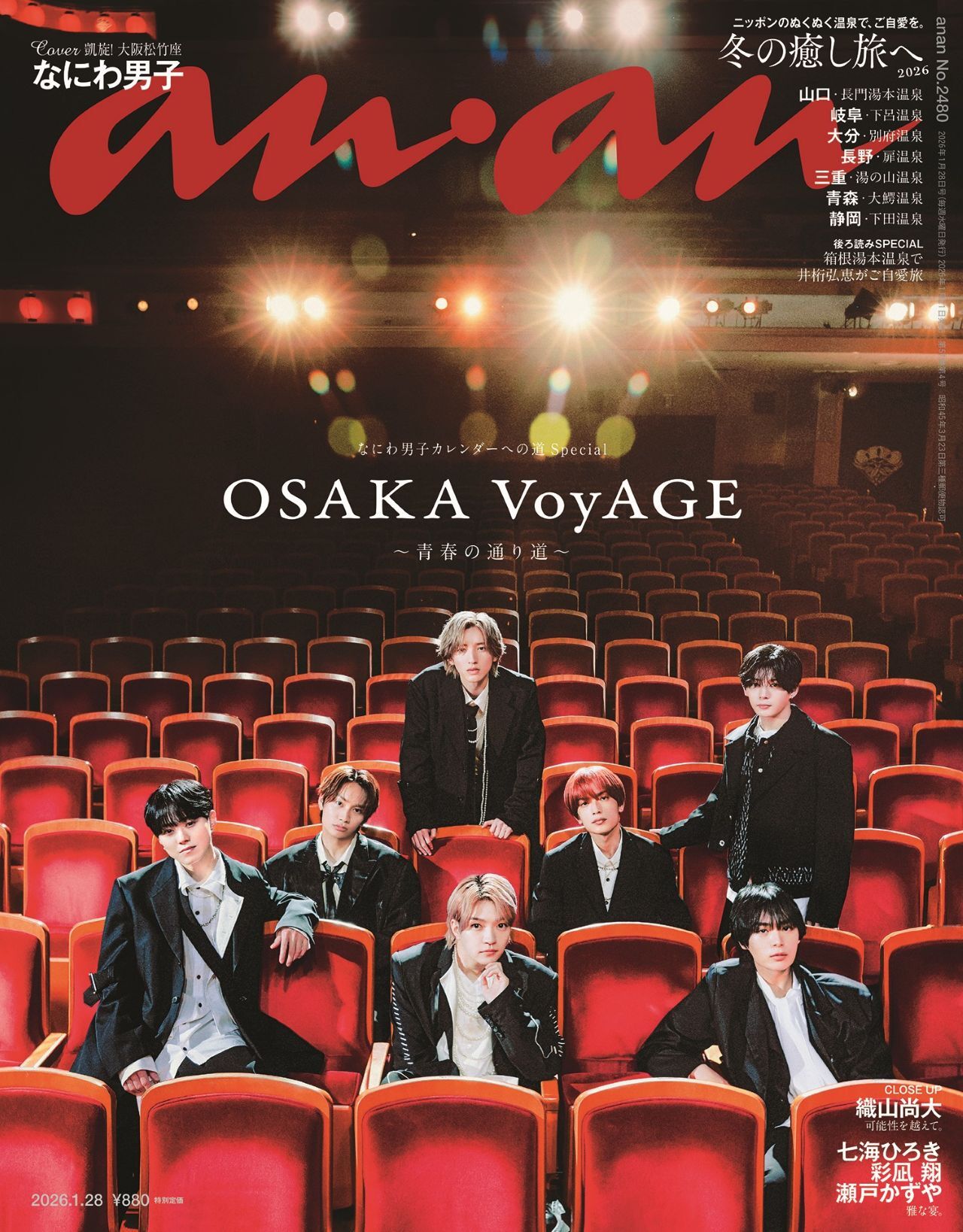4年目を迎えたanan総研の「anan総研神社部」が2024年も始動! 新メンバーが加わり、 「神嘗祭」と関わりのある 「初穂曳」「式年遷宮」について全3回にわたって深堀りします。第2回となる今回は、神嘗祭をお祝いするために行われる「初穂曳」に参加するべく、伊勢へ総研神社部の2名が訪れます。
「初穂曳」に参加するために三重県・伊勢へ!

左から、黒川美南さん(anan総研No.401)、市岡彩香さん(anan総研No.147)。
「初穂曳(はつほびき)」についてもっと詳しく知りたい! と、anan総研神社部を代表して、一昨年から神社部に参加している市岡彩香さんと、新人メンバーの黒川美南さんが、三重県にご鎮座する伊勢神宮へ行きました。
前回記事:
「式年遷宮」と関わりのある「初穂曳」とは?

「初穂曳」は、「伊勢神宮」に新穀を奉曳・奉納する行事です。新穀とは、その年に収穫した穀物、特にお米を指します。
20年に一度、社殿や御装束神宝などを新しくして、神様に新しい御正殿へお遷りいただくお祭り「式年遷宮(しきねんせんぐう)」の一環で、御用材を神域に奉曳(ほうえい)する「お木曳(おきひき)行事」、御正殿(ごしょうでん)の御敷地(みしきち)に敷き詰める白い石を奉献する「お白石持(おしらいしもち)行事」の伝統文化を継承し、次世代に伝えることを大きな目的として、昭和47年からはじまりました。
伊勢神宮奉仕会青年部部長・奥野さんに教えてもらいました!

伊勢神宮奉仕会青年部部長・奥野勇樹さん
今回お話を伺ったのは、伊勢神宮奉仕会青年部部長・奥野勇樹さん。「初穂曳」について教えてもらいました。
市岡 「初穂曳」とは、どんな行事ですか?
奥野さん 「初穂曳」は、その年に収穫したお初穂を、「伊勢神宮」へ奉納するために神域に奉曳・奉納する行事です。お米の稔りに感謝を込めて、毎年10月15日に奉曳車(ほうえいしゃ)で外宮(げくう)へ運ぶ「陸曳(おかびき)」、10月16日に初穂船で内宮(ないくう)へ運ぶ「川曳(かわびき)」が行われます。
黒川 陸曳は伊勢の街中から外宮まで、お初穂を積んだ奉曳車(ほうえいしゃ)を曳いて運ぶんですよね。
奥野さん 伊勢市民をはじめ、全国の伊勢神宮崇敬者の皆様などが曳手として毎年約1,200人参加します。その年の参加人数によって変わることもありますが、神宮が所有している3台(大・中・小)の奉曳車を約800m運行します。

市岡 3台の奉曳車を曳くのはなぜですか?
奥野さん 例えば、「大」の車にはお白石持行事に用いられる「樽」を、「中」には初穂曳の「米俵」を、「小」には神宮の御用材「お木」を積みます。これには、二十年に一度の「お木曳行事」と「お白石持行事」の荷締めの技術などを伝承する目的があります。
黒川 荷締めなどの練習の意味があるんですね。奉曳車の車輪や提灯に書かれている「太一」の文字にはどんな意味があるんですか?
奥野さん 「たいち」と読みます。中国の古代思想で「世界万物の根源、中心と言えるもっとも尊いもの」などを意味する言葉で、天照大御神のことを指します。そのため、天照大御神をまつる神宮の御料などの印に用いられるようになったとされています。
「初穂曳」について学んだ2人は、さっそく外宮へ奉曳・奉納する「陸曳」に参加しました。
神社部メンバーが「初穂曳」に参加!

特別に参加させてもらった総研神社部の2人。全身白い衣装をまとい、雨の中「エンヤ!!」というかけ声とともに、大きくて重い奉曳車を力いっぱい曳きます!
黒川 上下白の服を着用するのにはどんな意味があるのでしょうか?
奥野さん 神領民として、神宮様にご奉仕する精神の表れであり、清らかな姿で臨むという意思があって、白を着用しています。清浄を重んじる日本の文化からきているのだと思います。

黒川 なぜ、街の中を通って外宮へ運び入れるのですか?
奥野さん 「初穂曳」は、20年に一度行われる「式年遷宮」のための「お木曳行事」と「お白石持行事」の伝統文化を継承するために毎年行われるようになりました。その初穂曳で通るルートは、「お木曳行事」で実際に通るルートとなっています。

市岡 参加している人たちが歌っている歌や、「ヨーイトコセー」というかけ声にはどんな意味がありますか?
奥野さん 木の持ち手に白い和紙をつけた采(ざい)を手にした木遣り子(きやりこ)が歌ってるのは、「木遣り唄(きやりうた)」です。「ヨーイトコセー」は、江戸時代に伊勢街道で唄われた「伊勢音頭」の歌詞に見られる「よいとこいせ(良いとこ伊勢)」からきていると言われています。

市岡 外宮に到着したあとは、稲穂を奉納するんですよね。この稲穂は、どこから運ばれてくるのですか?
奥野さん 全国で収穫されたお初穂が御正宮に運ばれてきます。昔から稲穂を神社に奉納する慣習があり、今でもお米の稔りに感謝を込めて奉納します。


外宮へ到着後、お初穂を奉納して「初穂曳」を無事に終えた2人。雨の中、約800mにわたって奉曳車を曳いたこともあり、関わりのある「式年遷宮」のことをもっと知りたいと思った様子。
黒川 一般道で、大勢の人が奉曳車を曳くというまたとない機会を目にすることができ、私たちもその一員になれたことに感動しました。
市岡 思っていたよりも奉曳車が大きくて、大迫力でした。綱が重くて大変だったけど、みんなのかけ声があったから頑張れました。一生忘れない思い出になりました。
黒川 「初穂曳」は、20年に一度行われる「式年遷宮」につながっていることを知って、もっと詳しく「式年遷宮」について学びたくなりました!
外宮前にある「せんぐう館」へ行ってみよう!
市岡 外宮前には、「式年遷宮」について詳しく知ることのできる「式年遷宮記念 せんぐう館」があるんだって。
黒川 何のために「式年遷宮」が行われるの? 「式年遷宮」のための木材はどこからやってきて、その後どうなるの? 知りたいことがたくさん!
「初穂曳」に参加したことで「式年遷宮」への関心が高まった2人。次回は、「式年遷宮記念 せんぐう館」へ行って「式年遷宮」について学びます!

mini column 02:「神宮大麻」は、どこで受けられるの?
「神宮大麻(じんぐうたいま)」とは、全国の神さまの中心であり日本人の総氏神として仰がれる、伊勢神宮の神様・天照大御神(あまてらすおおみかみ)の力を宿し、「自宅でもまつることができるように」と奉製されたお神札のこと。
「神宮大麻」は、神職がいる日本全国の神社で受けることができますが例外もあります。
毎年、新しい「神宮大麻」を受けると共に、地域をお守りくださる氏神様や、崇敬する神社のお神札を一緒に神棚におまつりして、ご家庭の一年の無事と幸せを祈るのが、日本の習わしとなっているので、「神宮大麻」は、氏神神社や崇敬神社で受けるといいでしょう。
氏神神社は、居住地の神社庁(東京都なら東京都神社庁)に電話をして住所を伝えると、知ることができます。昔の区割りで分かれているため自分では判断しにくいので、ぜひ一度問い合わせてみてください。