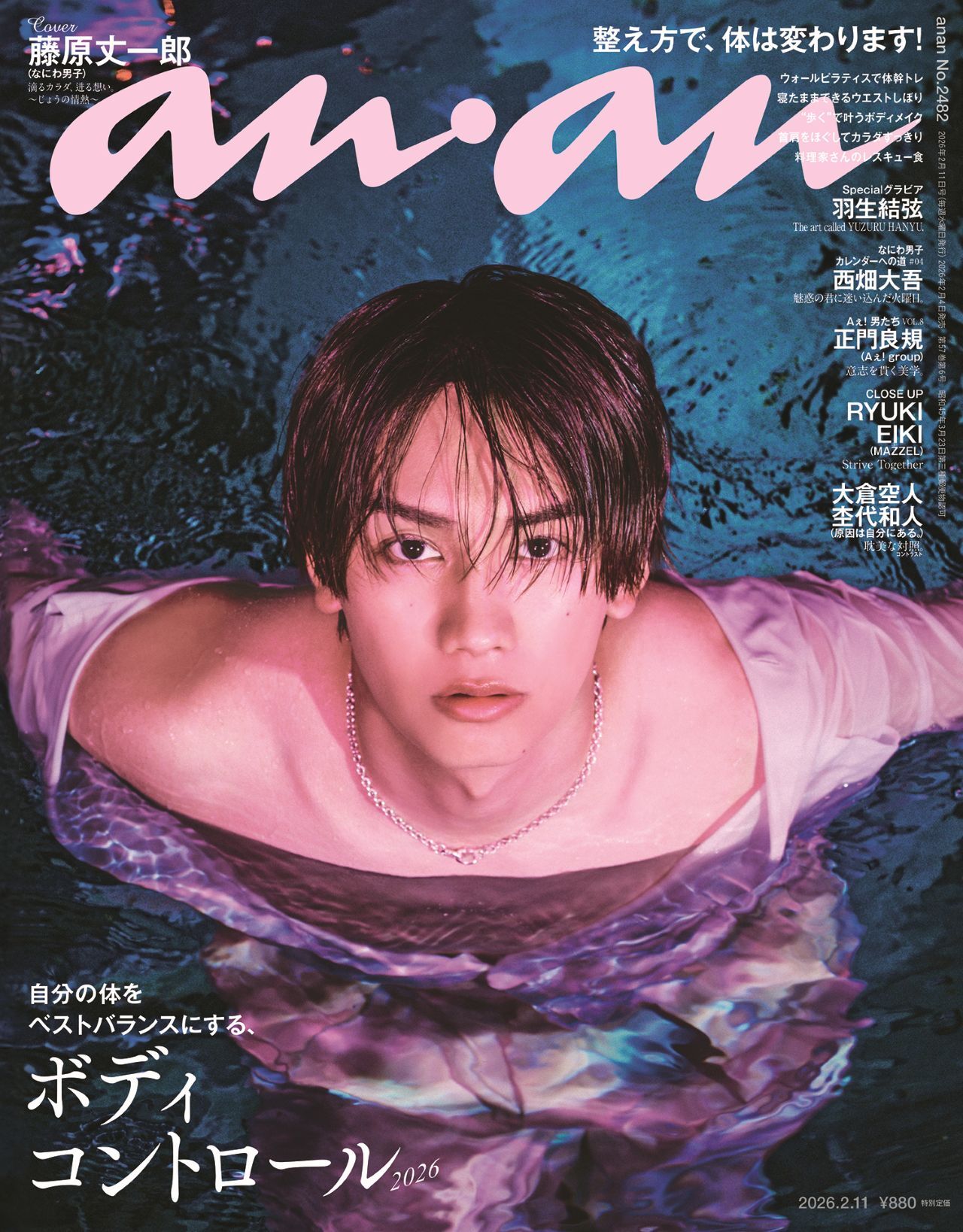左から、頓花聖太郎さん、大森時生さん、梨さん
喜怒哀楽に属さない、人のさまざまな恐怖心にフォーカスした『恐怖心展』が、渋谷・BEAMギャラリーで開催されている。そこで、展覧会を手がけた人気ホラー作家の梨さん、株式会社闇の頓花聖太郎さん、テレビ東京プロデューサーの大森時生さんを直撃! 来場者数が10万人を超えた『行方不明展』も大きな話題となった3人が新たに仕掛ける試みの、魅力や見どころを探ります。
Index
展示物とストーリーの掛け合わせで恐怖心が浮かび上がる
──『恐怖心展』という名前に興味をそそられる人も多いと思いますが、展覧会のテーマを教えてください。
梨 高所や閉所が怖い、集合体に関する恐怖心など、いろいろなものに対する恐怖心をいっぱい展示しています。展示物を通じて、なぜそれを怖いと感じるのか、その不思議さを楽しんでいただきたいということがコンセプトにあります。
大森 お金や名誉があれば嬉しいという気持ちは多くの人間に共通しているけど、恐怖心というものに関しては人それぞれにバラバラで、全く理解できないものも往々にしてあるなと。ある人にとっては怖かったり、嫌でたまらないものが、ある人にとっては何も感じないというところも、すごく面白いと思っています。
頓花 昨年、『行方不明展』を開催するにあたり、内容を決める会議をしている時に出てきた案の一つです。僕たち株式会社闇は、ホラー専門の制作会社という形でやっているので、恐怖心、恐怖症を並べて展示することで面白さを知ってもらえたらと。自分が何を怖いとしているかは、ある種、自分のアイデンティティに結びつく部分があると思うんです。そこに梨さんの物語をのせることで、世界観を膨らませられるのではないかというところから始まりました。
大森 恐怖心というのは基本的に文脈ありきだと考えています。たとえば閉所が怖いのは、何かしらのきっかけなどストーリーみたいなものがあると思うんです。だからこそ、展示を見て恐怖心を理解してもらうには、単純に狭い場所が置いてあるだけではなく、その人が恐怖に感じる理由を込みで見せることが重要で。梨さんが作るストーリーと組み合わさることで、恐怖心が立体的に浮かび上がるはずです。
僕が学生の頃に「蓮コラ(蓮の花托を人の体に合成したコラージュ画像)」が流行りましたけど、その時まで、「集合体恐怖症」という言葉はメジャーではなく、自覚してない人も多かったと思います。ブームをきっかけに、“体に穴があいているグロさ”ではなく、“物が集まっていること”が自分には気持ち悪く感じる、バッドに入る、不安に感じる…と繋がっていく。それは、ある種のストーリーがあるからこそだと思っているし、僕たちの中で共通して感じていることでもあります。
頓花 そういう意味で、今回は『恐怖展』ではなく『恐怖心展』。恐いものをバーンと展示したら『恐怖展』としては成り立つかもしれませんが、梨さんの物語で「心」の部分がどのようなものかがわかる仕組みになっています。
大森 恐怖物自体に価値を置くというより、鑑賞者の方々がどういう風に心としてその物体を見るか、見た時にどのように心が動くかというところを含めた意味での『恐怖心展』だと思っています。

「自分が何を怖いとしているかは、ある種、自分のアイデンティティに結びつく部分があると思うんです」(頓花さん)
みんなが不安に感じうるものを50〜60個ピックアップ
──展覧会を作るにあたり、まず何をするところから始めたのでしょうか?
大森 世の中にある恐怖症について調べるなど、みなさんが何となく通底して不安に感じうるものを50個くらいピックアップするところから始めました。本来は医学用語であった恐怖症が、今は日常語として使われているじゃないですか。たとえば、「高所恐怖症」。狭義でいうと、高いところに行くと動機がするなど身体的な反応が起こるまでを指しますが、我々は高いところに不安を感じたり、嫌な気持ちがする時にも使いますよね。
頓花 恐怖症といわれるものにはいろいろなものがあって、「FOMO(=Fear Of Missing Out)」みたいな情報に取り残されることへの恐怖、そういう現代的な恐怖心も今回の展示には入っていて、面白いなと思います。逆に、キリスト教の影響だと思われる「666恐怖症」みたいに、我々があまりピンとこないものは入れていません。
梨 日本でいうと数字の「4」に対する恐怖症である「テトラフォビア」が、英語圏のウィキペディアには記載されています。知らない文化圏の人からしたら面白いでしょうね。先ほど、恐怖には「心」が結びついているという話もありましたけど、結構、文化依存症候群的な面が強いと思います。「対人恐怖症」は、英語でも「Taijin Kyofusho」と呼ばれているそうで、完全に翻訳する言葉がないのでしょう。
大森 日本は、対人恐怖症的な感覚がない人のほうが少ないんじゃないかと。もしアメリカで展覧会をやる場合は、「対人恐怖症」ではなく、「666恐怖症」を入れ込んだほうがいいわけで。そうした違いも、今回の展示的にも繋がるところだなと思います。
モノ、社会、空間、概念。さまざまな恐怖心を展示
── 展覧会では50〜60種の恐怖心が、4つに分けて展示されているそうですね。
梨 恐怖の対象で会場を4つに分けました。ざっくりいうと、先端恐怖症など、そこにある「モノが怖い」。対人恐怖症や、視線が怖いなど「社会が怖い」。また、そんな社会を構成する場、高所や病院など「空間が怖い」。そして、一番最後は死や無限などの「概念が怖い」です。どんどんレンジを広げていくようなイメージで展示のフレームワークを作っていきました。
大森 それができたことで、急に展示の全体像が見えてきた感じがありましたね。恐怖心の分類がクリアになったというか、一つ一つの物体の恐怖心が像を結びやすくなった感覚があります。
── 梨さんはストーリーも手がけていますが、大変なこともあったのではないでしょうか。
梨 そう、今回は展示物が50〜60用意されていて、つまり、50〜60人に憑依しないといけないんですよね。
大森 梨さんがすぐにストーリーが思い浮かぶパターンもあれば、「これ嫌だよね」というものが先に思いついて、そこにストーリーを紐づかせていただくパターンもあるので、どうしても無茶振りになるようなところも…。
梨 大喜利です。そう、「デントフォビア」という概念があって、歯医者特有の匂いが怖いとか、抜け落ちた歯が怖いみたいな人もいるのですが、「歯に関する手紙」を作らないといけなかったりとか。でも、こちらのほうからアイデアを売り込むという逆のパターンもあって、特に、「概念が怖い」になってくると、その傾向が強いです。
それこそ、「モノが怖い」であれば、歯や着ぐるみとかみたいなものに紐づけて発想しましょう、みたいなことが多かったけれど、概念になるとそうはいかなくて。私が「幸福恐怖症というものがあるらしい」と発見して、それの文章を作ってきたから展示に入れよう! とゴリ押しすることもありました(笑)。

「僕と梨さんは恐怖症がないんですよね」(大森さん)
得意ジャンルの違う人たちが集い、作り上げた展覧会
── 一緒に展覧会を作り上げていくなかで、あらためてお互いをすごいと感じたことを教えてください。
大森 僕から見ると、まず梨さんは、シンプルなことですが、やっぱりストーリーがめちゃ面白いです。それが面白くないとお話にならないですから。その役割を担うために呼ばれて、一緒に高みまで行くためにお互いで調整しあえる作家さんは、実は珍しいと思っています。怖い文章とか面白い文章を作るのではなく、プロデューサー的な観点で全体を見て、展示として、体験として、恐怖心をちゃんと感じるように設計するところを向いてくれている。そういう作家さんは、あまりいないと思います。
梨 私的には、頓花さんがアドバイザー的な存在としていてくださることがとても助かっています。私と大森さんは、そもそも、恐怖症に相応するものに対する一人称的な感覚みたいなものがなくて。本当に申し訳ないなと思いながら、頓花さんに、「これ、怖いと思いますか?」といろいろ質問させてもらっています。
大森 あと、株式会社闇として、生の人間がそれを見た時にどうリアクションするかというところを、よく見ていらっしゃるなと。僕とは梨さんは本やテレビの場合が多いので、人の心の動線設計みたいなものに関して経験値が違います。それぞれ、得意ジャンルの違う人が集まっているなと思いますね。
恐怖心を知ることは“バッド”に入るものへの対抗手段
──ちなみに、みなさんが恐怖心を抱く対象はありますか?
大森 先ほどの話のとおり、僕と梨さんはないんですよね。もちろん、街で急に背中をパンパン叩かれたり、カーテンを開けたら誰かがこっちをみていたとかは怖いですけど(笑)。高所恐怖症とかもないですね。
梨 私は大学時代にバンジーを飛びに行きましたね。
大森 でも、「なんか嫌」は、いっぱいあります。視線であったり、後ろから笑い声が聞こえるみたいなこととか、生活に支障をきたすことではないけれど、何か不安な気持ちになったり、人の表情の微妙な変化でよからぬ想像してしまうことは結構あるなと思います。恐怖心というのは、ある種、予期不安みたいなものとすごく近いと考えていて、それに関しては、僕と梨さんは、人より強いくらいあるのかもしれないなと。
頓花 僕は、パニック症があるので、飛行機やバスにはできるだけ乗らないようにしています。こういう仕事をしていると、観覧車など狭い空間の演出をすることがあり、そういう時は歯を食いしばっています(笑)。でも、梨さんが書いた恐怖心のストーリーを読んでいると、完璧に心理がトレースされていて、すごいなと思います。
梨 展覧会を作るにあたり、いろいろ調べる中で私がなるほどと思ったのは、「広場恐怖症」です。広場に限らず、特定の場所で強い不安や恐怖を感じるというものですが、美容院でシャンプーされている時や歯医者さんで動けない時、最近では、マツエクをしている時に感じる人が多いらしいです。花火大会が終わった後の混雑した駅までの道とか。閉所じゃないけど、社会的に動けない場所が怖い、社会的な縛りが怖いというのは、確かに分かるなと思いました。
大森 でも、自分にとって何が嫌なことかをわかっておくことが、僕の中では恐怖心への一番の対抗策だと思っています。僕は、自分が“バッド”に入る瞬間が予期せず起こることが一番嫌なんですね。現代社会は、基本的に絶えずバッドになることやものに晒されるものだと思っているからこそ、事前に心構えをして最悪の事態を回避することが大事だなと。
梨 それこそ、『恐怖心展』を作っている時に、バッドに入るものへの対抗手段として、人は恐怖症という概念を生み出したのではと考えていました。恐怖症であると言うことのハードルが下がり、ラフに言えるようになったことで、“自分だけじゃない”と思えることが重要だったというか。
また、私、「〇〇恐怖症なんだよ」ということがコミュニケーションツールとなる、それ自体が一つの克服手段じゃないのかなって。恐怖症というのは必ずしもバッドに入るしかない、デメリットしかないものなんだよと思わない、恐怖症なんて取るに足らないものなんだと思っちゃうこと自体が、恐怖症を自分のなかで消化するためのものになるのではないかと。そういう意味では、展示というものに落とし込むことは、作例の一つにもなるのかなと思いました。
頓花 以前、梨さんが言っていたことですが、何かを思った時にSNSで検索して、自分と同じことを言ってくれる人を見ると、すごく安心できるんですと。だからこそ今回の展示も、みんなでワイワイ言いながら見て楽しむのもありなのかなと思います。

展覧会と連動したテレビ番組も放送中!
『恐怖心展』の開催にあたり、恐怖心をテーマにした番組『魔法少女山田』を、7月14日、21日、28日の24時30分からテレビ東京で放送。これは、「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」に続く「TXQ FICTION」第3弾で、監督を寺内康太郎さん、プロデューサーを大森さんと皆口大地さん、近藤亮太さんが務める。モキュメンタリーホラー好きにはたまらないメンツが揃う今作も合わせて注目を!
Profile
梨
なし ホラー作家。2022年『かわいそ笑』でデビュー。近著に『禍話n』(KADOKAWA)、『恐怖症店』(文藝春秋)。漫画の原作やテレビ番組の原案を手がけるなど幅広く活躍中。
大森時生
おおもり・ときお テレビ東京のプロデューサー。『祓除』『イシナガキクエを探しています』『フィクショナル』『飯沼一家に謝罪します』など、さまざまな番組を手がけている。
頓花聖太郎
とんか・せいたろう 株式会社闇代表。ホラーとテクノロジーを掛け合わせた「ホラテク」で新感覚の恐怖体験を作り出す。お化け屋敷など、さまざまな場所でイベントをプロデュース。
開催中!
information
『恐怖心展』
BEAMギャラリー 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F 7月18日(金)〜8月31日(日)
11:00〜20:00(最終入場は19:30) 会期中無休
2,300円(期間有効券と日時指定券があり)
チケットなどの詳細は公式HPをチェック!