日本文化にちなんだ不可解な事件を、留年生と留学生の凸凹コンビが解決。

「日本文化に詳しい外国人が探偵役というのは面白いかなと、まず決めました。あと、エラリー・クイーンの国名シリーズみたいなものを僕も日本の明治以前の国名、つまり藩でやってみたいなと思っていたんですね。伊勢海老とか紀州梅とか地名と名産物が結びついているものが結構あるから。ところが『薩摩芋』で書き始めてみたら、いくらなんでもマニアックすぎた。そこで日本文化にフォーカスすることにしたんです」
主人公の長瀬秀次は、やや不出来な留年生だが、男子寮の代表になるほど人望がある。寮で秀次と同室となったもうひとりの主人公ケビンは、日本かぶれと言っていいほどの日本大好きオタク。〈ミョーデス〉と言いながら、深い洞察で数々の難問を解いていく。第1話「SAKURA」は、大学の旧学生会館でOBの遺体が発見され、秀次の後輩が容疑者に。桜に託されたダイイング・メッセージがカギになるミステリー。
「この最初の話で、短編で取り上げる題材と結びつく海外の名文などをエピグラフとして提示するという形式にしてしまったので、それを探すのが結構ハードルが高いぞと(笑)、あとから気づきました」
収録されているどの短編も、密室やアリバイ等、いくつもの謎とトリックが絡み合って二転三転。そんな本格ミステリーの流儀を踏襲しつつ、文体はポップで軽妙、日本人でも膝を打つような日本文化の再発見ができるのも魅力だ。
「コロナ禍に連載していたため、取材などはなかなか進まなかったのですが、第3話に出てくる茶道は、浅草で体験してきました。茶室のにじり口ってトリックに使えるかなあと考えておいたことを確認できたり、それまでぼんやりとした知識しかなかった掛け軸のことや茶道具の棗のことなど、体験したからこそ参考になることも多かったです」
事件が解決しても、手放しで喜べない切なさが残る作品が多いのは、青柳さんのミステリーの特徴だが、本作でもその味わいはたっぷり。
『ナゾトキ・ジパング』 2度目の大学3年生というトホホな長瀬秀次とニッポンが大好きなアメリカ人留学生のケビン・マクリーガルが、コンビで事件の謎に挑む5編。小学館 1650円
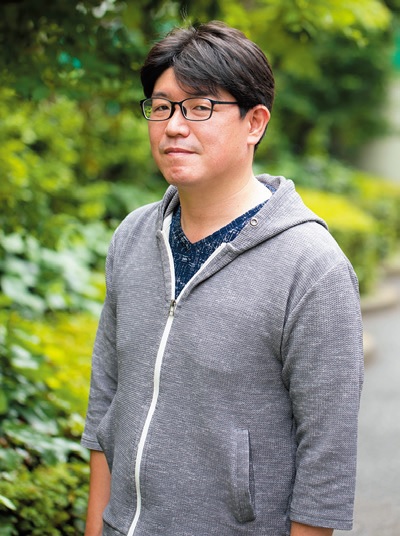
あおやぎ・あいと 1980年、千葉県生まれ。早稲田大学卒。2009年、『浜村渚の計算ノート』で講談社「Birth」小説部門を受賞し、デビュー。小説のほか、マンガ原作も手がける。
※『anan』2022年8月3日号より。写真・土佐麻理子(青柳さん) 中島慶子(本) インタビュー、文・三浦天紗子
(by anan編集部)





































