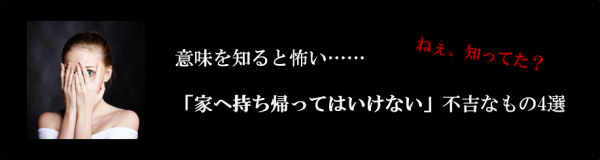――ご自身では、多忙な俳優生活をどのように見ていますか?
瑛太:まずは、仕事があることがありがたいですね。デビューしてしばらくは、自分が売れるのか、仕事がちゃんとくる俳優になるのかわからなくて、虚勢をはったりしながらもがいていましたから。
――ここまでやってこられた理由は、何だと思いますか。
瑛太:自分がストイックに努力してきたからここまで俳優を続けられてきた、とは思っていません。昔から人との縁を大事にしようと思っていたのと、その結果、プロデューサー、監督、共演者、スタッフなどリスペクトできる人たちと出会えたからでもあります。運がいいなとも思っているし。あとは、若いころに持っていた野心みたいなものが、違う方向に向いたのもよかったのかもしれない。
――野心とは、具体的には?
瑛太:デビュー同期世代でいえば、(松田)龍平や、新井(浩文)、(森山)未來、小栗旬、ムロツヨシがいて、みんなライバルで。その中でも、俺が抜きんでてやる、ってずっと思っていました。彼らも同じように思ってたんじゃないかな。よく芝居について口論してましたから、現場でも、プライベートで会ってても。作品に向き合うってことは、死ぬ気でやらなければいけないと誰もが思っていたと思う。みんな、一俳優として冷めてはいませんでした。それが正解ではないとしても、少なくともこの5人は全員、成功者ですしね。
――これまで、挫折を感じたり、辛かった時期はありましたか?
瑛太:僕にしかできないことができているかどうかという葛藤は常にありました。そんな中、大河ドラマの『篤姫』をやっていた時期、『ラスト・フレンズ』、映画『ディア・ドクター』『余命1ヶ月の花嫁』『ガマの油』を掛け持って、スケジュールを縫って撮っていた時期があったんです。時間が足りないあまり、仕事に対してガサツになっているんじゃないか、という疑問を感じながらも、毎日撮影は続くし、でももっと遊びたいし…って全部やろうとしていたら、肉体と精神がどんどんすり減っていきました。終わってみると、その作品たちがすごく評価されて、賞をいただいたりした。そして、自分でも突っ走ったという実感があったので、一度、ペースダウンしながら考え直してみたら、自分がやりたい作品を自分で選択して、責任を持って演じていきたい、という結論にたどりついたんです。そうしたら色々見えてくるものがあって。別に人気者になりたいわけじゃない、自分なりのペースでやっていけばいいんだとわかった。そこが、いうなればターニングポイントかな。そこから少しずつうまくいって、今に至るんですけど。

――この10月、11月で『リングサイド・ストーリー』『ミックス。』『光』と、主演2本を含めた3本の映画が公開されますが、それぞれ、全く違う雰囲気の作品ですね。
瑛太:3本とも、僕にしかできなかった役だと思っています。最初に撮った『リングサイド・ストーリー』は、武(正晴)監督の『百円の恋』という映画を観て、こういうのやりたいなってずっと思っていたんです。スポ根で、ある意味シンプルなんだけど深いことを感じさせてもらえて、なおかつ観やすくて俳優が際立つような。だから武さんとはいつか一緒にお仕事したいなって思っていたら、割と早めに、しかも俳優の僕が、俳優である村上ヒデオを演じるというおいしい役で叶った(笑)。
――ヒデオは売れない俳優なのに自信満々でバイトもせず、彼女のカナコ(佐藤江梨子)のヒモで…結構なクソですよね(笑)。
瑛太:あははは、ひどいなぁ(笑)。でも、女性はそう思うかもしれないけど、男性はまた違う意見を持つと思います。というのもこの映画は、男目線と女目線で、見方が変わる作品だから。カンヌに行くことを目標としているヒデオは、常に突拍子もないことをしてやろうと思っている男。情けないのに自分ではそう思わず、いつも前を向いて振り返らないし、おいしい仕事も断っちゃう。そんな根性や勇気、野心を僕は見習いたいです。
――なるほど。その次に撮影された『光』は、25年前の消滅したはずの罪が掘り起こされたことで、人間の闇の部分が狂気となって描き出されるという、三浦しをんさんの人気小説の映画化作品です。
瑛太:大森(立嗣)監督とは『まほろ駅前多田便利軒』から付き合いが長く、信頼関係ができあがっていることもあって、台本に収まる芝居で済ませちゃいけないな、という覚悟がありました。でも共演の井浦新さんが、裏切り行為を色々してくれて(笑)。
――どういうことですか?
瑛太:僕がこうやろうと思っていたところに、全然違うことを仕掛けてくるんです。お互いに、そんなアドリブに近い衝動みたいなものを仕掛け合ったことで、台本通りに演じていては決して叶えられなかったものが生み出せたし、新さんとだから実現したんだと思う。撮影中は役作りに集中していて一言も喋らなかったけど、昔から新さんのことが大好きで尊敬する方だったので、夢のような時間でした。
――人間の生々しい感情や弱さなどがものすごくリアルに描かれていて、役者さんたちの演技がすばらしく、心に残る作品でした。
瑛太:こういう映画が日本でも撮れるんだよ、と伝えたいですね。ジェフ・ミルズの音楽の力も強くて素晴らしいんですが、映画の世界観として、ただ悲しみを悲しく、怒りを怒りとして描いているだけじゃない。観ている側の心に、お前はどう思う? これ観て何を感じる? っていう強い投げかけがある。既成概念をどれだけぶっ壊せるか、このかっこよさは日本の映画にはあまりないんじゃないかな。
――そして今年1月に撮影されたのが『ミックス。』。田舎の卓球クラブが、男女混合のダブルス1本で大会に臨む、という話ですね。
瑛太:これはシンプルに、ガッキー(新垣結衣)とミックスできるから「やりまーす!」って感じで引き受けましたけどね。
――あははは。新垣さんとは初共演だそうですが、印象は?
瑛太:ガッキーは、いつでも、スッとした佇まいで受け身でいながら、一見すると近寄りがたくもあって、でもたまに話しかけてくれたりして。こっちが入り込めば入り込んだ気にもなるけど…実は入り込めてはいないんじゃないかとか、そんな雰囲気もある。今、何を感じてどこを見ているんだろう、って、ガッキーをずっと観察していたんだけど、わからないんですよね。だから一緒にいて楽しかったし、無意識に追いかけちゃって。それで初日に、何か突拍子もない質問をしたら「打ち上げの二次会で聞くようなこと聞いてきますね」って言われちゃいました(笑)。すごいかわいいのに、自分のかわいさわかってんのかな、って心配になるぐらいかわい子ぶらない人です。そんなガッキーと挑んだこの作品は、期待以上に面白いと思う。そもそも、ミックスペアってお互い信用し合っていないとできないと思うんだけど、その感覚は、クライマックスの大会のシーンまでには作れたんじゃないかなと、僕は思っています。予告編はコメディタッチでしたが、完成作を観て、改めて、すごくしっかり作られていると思いました。登場人物一人ひとりの思いが素通りせずに、観ている人の心に付着しながら最終局面を迎えられる映画です。
シャツ¥20,000(オールド パーク/HEMT PR TEL:03・6721・0882) パンツ¥25,000(ブフト/HEMT PR) その他はスタイリスト私物
主人公の村上ヒデオ役で主演の映画『リングサイド・ストーリー』(マンシーズエンターテインメント×彩プロ)は10月14日~、主人公の萩原久役で主演の『ミックス。』(東宝)は10月21日~、輔役の『光』(ファントム・フィルム)は11月25日~公開予定。
※『anan』2017年10月11日号より。写真・森滝 進(まきうらオフィス) スタイリスト・壽村太一 ヘア&メイク・KENICHI(エイトピース) インタビュー、文・若山あや
(by anan編集部)
【人気記事】
※下着コンシェルジュがおすすめ! 誰もがうなる「名品ブラ」3選