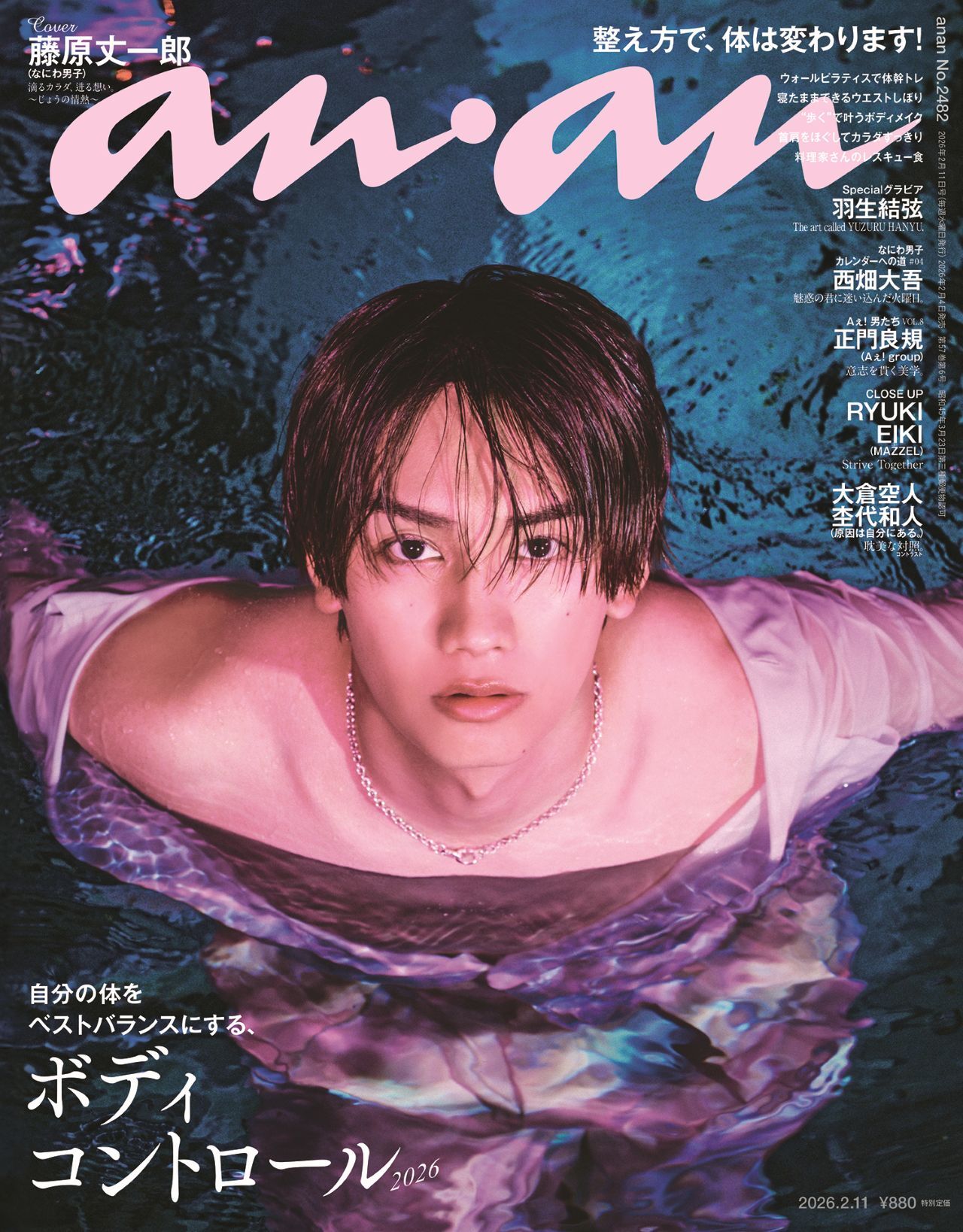消化促進やむくみ防止、発汗、殺菌など様々な作用があり、デトックスを促すことで知られている漢方だが、漢方同様、天然由来の植物で、もっと手軽に取り入れられるのがスパイス&ハーブ。食生活で自然治癒力を高めよう。
Index

悪いものを排出する意味で使われることが多い“デトックス”だが、医療の世界では体内で毒を分解する“解毒”を指すという。「解毒機能はもともと私たちのカラダに備わっている」と話すのは、薬学研究者の加藤雅俊さん。
「毒には、外から体内に入り込んだ有害物質やバイ菌、ウイルスなどと、自ら体内で作り出すがん細胞や活性酸素(老廃物)があります。これらの毒は防衛システムを担う肝臓や腎臓、リンパにより日々デトックスされ、便や尿、汗によって排出されます。ところが、現代人は潔癖の傾向があり、紫外線やウイルスに対して過敏になったり、カラダに悪いとされる食べ物を徹底的に排除しようとする。これらに過剰になりすぎると、カラダに備わっている防衛システムや浄化機能が正常に働かなくなり、皮膚炎やアレルギー、様々な疾患を発症する原因にもなるのです」
体内の浄化機能を正常化することはデトックスの第一歩。食、運動、生活習慣などから、デトックス機能の改善にトライしてみて!
なんでデトックスで癒されるの?
発汗によりカラダとココロ両方のデトックスをする=癒しに。
汗をかくことには解毒された老廃物を排出する作用があるが、加えて運動をして汗をかくことで得る爽快感がカラダとココロの両方の癒しに繋がる。
スーパーで売っているものでOK。スパイス&ハーブで簡単デトックス!
コリアンダー

パクチーの名前でお馴染み。排出力UPの最強デトックス。
エスニック料理に欠かせないセリ科の植物。レモンのようなさわやかさと甘い香りですっきり風味。胃の機能を正常に保ち、抗酸化作用を助け、冷え症やむくみ改善に。
ターメリック

カレーに欠かせない別名“ウコン”で肝臓をサポート。
ショウガ科の植物で、色素成分クルクミンはアルコールの分解や二日酔い防止のドリンクや錠剤に使われることも多い。肝・腎機能向上、代謝力アップ、整腸作用ほか。
クローブ

殺菌作用に優れ、バニラに似た甘い香りが特徴。
フトモモ科の植物で、開花直前のつぼみを乾燥させたもの。腹痛の緩和や鎮静作用、胃腸を温める作用がある。食べるとピリッと辛く、カレーの香辛料としても定番。
オレガノ

ヨーロッパなどで定番のハーブは“天然の抗生物質”。
トマトやチーズとの相性抜群で、ピザやパスタソースの香辛料としても活躍。免疫力アップや抗酸化作用、整腸作用、生理痛の緩和に。コショウに似た刺激と清涼感。
ペパーミント

西洋ハッカとも呼ばれ心身をリフレッシュ。
葉は生や乾燥で、また精油としてなど、取り入れ方は様々で、スーッとした強い香りと清涼感。胃の機能を正常化するほか、抗ウイルス作用、乗り物酔い防止に。
レモングラス

血行不良や消化不良を改善させるさわやかなハーブ。
トムヤムクンなどのタイ料理には欠かせない、イネ科の植物。レモンにも含まれる成分シトラールを含有し、さわやかな香り。抗ウイルス作用や心身の疲労を緩和。
シナモン

お菓子作りにも活躍、発汗作用でむくみの改善に。
ほのかな甘みの中に独特の香りを持ち、紅茶やトースト、クッキー、チョコレートなど様々な料理やスイーツにも使われる。抗菌作用のほかシワ、シミの改善にも一役。
市販のカレールウにちょい足し! レトルトカレーもたちまちオリジナルの薬膳カレーに。

市販のカレールウやカレー味の麺類などにターメリック、クローブ、コリアンダー、シナモンなどをちょい足しするだけで、デトックス作用の高い食事に。少量からスタートして、自分が美味しいと感じる好みの量を見つけてみて。
お話を伺った方・加藤雅俊さん
Profile
薬剤師、薬学研究者、体内環境師(R)。薬に頼らず食事や運動、東洋医学など多方面から症状にアプローチする考え方“ホリスティック”を提唱。著書に『眠れなくなるほど面白いデトックスの話』(日本文芸社)ほか。
anan 2453号(2025年7月2日発売)より