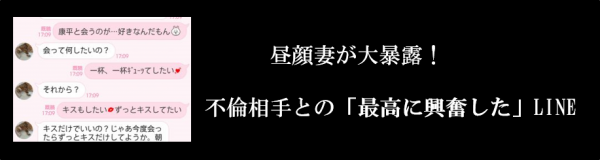自分を主語にして決断すれば、産んでも産まなくても後悔はない。

子どもを産みたいかどうか、多くの女性は一度は考えたことがあるのではないだろうか。苦労なく授かる人もいれば、子どもは必要ないという人もいるし、産みたくても叶わない人も。だけど、なぜ欲しいのか、あるいは欲しくないのかじっくりと理由を問われると、そこは意外と曖昧だったりもする。34歳で「子どもが欲しい病」にかかり、39歳で不妊治療をして、結果的に「産まない人生を選んだ」という吉田潮さんも、当初は深く考えていなかったという。
「過去の日記を掘り起こしたら、子どもがすごく欲しくて不妊治療をしていたはずなのに、妊娠していないとわかったとき、『ホッとした』って書いていたんです。あのときの自分は、不妊治療を頑張っていることを世間にアピールしたかっただけというか、自分ではないものに突き動かされていたのかもと思いました」
突き動かされていたものの正体は「女性は子どもを産むべき」という世間一般の価値観や、「親が喜ぶに違いない」という思い込み。“自分”がどうしたいかではなく、“世間”や“親”などに主語がすり替わり、不自由さを感じていたからこそ本音が漏れてしまったのだ。
「女に生まれたからには産んでおかなきゃっていう内なるプレッシャーがあった、という知人がいるのですが、彼女も自分が産みたいかどうかではなかった。勝手にリミットを設けて焦る人も多いと思うんです」
吉田さんは、封印しておきたかったであろう不妊治療のときの心境や、具体的な費用、夫とのやりとりを赤裸々に綴り、「産む・産まない・産めない」それぞれの立場の間に存在する溝や、両親や夫の胸の内、本書のタイトルになっているドキリとする疑問にも軽やかに切り込んでいく。
「『自分が主語』ってわがままに聞こえるかもしれないけれど、産む産まないに関しては特に、そうしたほうが気が楽になると思うんです。絶対正しい答えなんてない。一方からしか見ていなかったものは、反対側から見たら全然違う! っていうような気づきがあると嬉しいですね」
“自分が主語”という考えは、産む産まないに限らず、家族とのあり方、働き方など、生き方そのものについても共通なのだと気づかされる。豪快だけど繊細な吉田さんの優しさ溢れるメッセージは、女として最強の友を得たような気持ちになれる。

『産まないことは「逃げ」ですか』出産という女性にとって最大の命題を笑いも交えつつ軽やかに(そして泣ける!)綴ったエッセイ。ひとりで抱え込まず、パートナーにも読ませるべし! KKベストセラーズ 1200円
※『anan』2017年10月18日号より。写真・土佐麻理子 文・兵藤育子
(by anan編集部)
※寝ている間に“幸運体質”になる! Keiko流「3つのステップ」