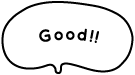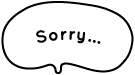志村 昌美
志村 昌美
「小津安二郎から常に学んでいる」日本の巨匠がドイツの名匠に与えた影響
『水を抱く女』

【映画、ときどき私】 vol. 368
ベルリンの都市開発を研究する歴史家ウンディーネは、小さなアパートで暮らし、博物館でガイドとして働いていた。ある日、恋人のヨハネスが別の女性に心移りしてしまったことを知り、悲嘆にくれていたウンディーネ。そんな彼女の前に、愛情深い潜水作業員のクリストフが現れる。
数奇な運命に導かれるように、惹かれ合うふたりだったが、次第にクリストフはウンディーネが何かから逃れようとしているような違和感を覚え始めるのだった。そして、彼女はついに「愛する男に裏切られたとき、その男を殺して、水に還らなければならない」という自らの宿命に直面することに……。
本作のモチーフとなっているのは、“水の精 ウンディーネ”の神話。古代ギリシャ時代からさまざまな作品にインスピレーションを与えてきた題材で、アンデルセンの『人魚姫』をはじめ、チャイコフスキーやドビュッシーといった芸術家たちを虜にしてきたテーマです。そこで、同じくウンディーネの物語に魅了されたこちらの方にお話をうかがってきました。
クリスティアン・ペッツォルト監督

これまでにベルリン国際映画祭銀熊賞(監督賞)を受賞するなど、ドイツの激動の歴史を描く社会派として知られているペッツォルト監督。今回は、多くの天才アーティストたちに愛されてきた神話の魅力や日本映画から受けている影響などについて語っていただきました。
―「水の精」を描いたこの作品を皮切りに、「火の精」と「地の精」という神話をテーマにした“精霊三部作”を作ろうとお考えのようですが、きっかけから教えてください。
監督 実は以前から、1度は三部作を作りたいと思っていました。ただ、僕はもともと怠けやすい人間なので、口に出さないと動けないタイプなんですよ。なので、今回は自分が働くための理由になると思って、最初から「三部作にする」と宣言しました。僕は一旦口にしたことは守るタイプですからね。そうやって言うことで自分にとって“足かせ”のような意味もあるんですよ(笑)。
―そんな背景もあったんですね。この神話は古代ギリシャ時代から現代まで、多くの芸術家が魅了されています。そこまで長年にわたって多くの芸術家を惹きつける魅力は何だと思いますか?
監督 ドイツでウンディーネが人気を集めたのは、産業革命の頃。自然が破壊され、人間に支配されるようになると、自然は“エネルギーの供給源”として見られるようになりました。そういったときにドイツロマン派の人たちから「自然の魔術的な力が失われないようにしたい」といった声が上がり、自然に対する憧れとしてウンディーネがテーマとして生まれたんです。そういったこともあって、ロマン派の絵画などには、自然回帰に関する内容の作品があるんですよ。
映画では、曖昧な記憶を描くほうがおもしろい

―監督はこのテーマを取り上げるうえで、意識したことはありますか?
監督 ウンディーネというのは、男性の視点から描かれているんですが、僕はエロティシズムの対象として描いたりするような男性目線のウンディーネにしたくないということだけは気をつけました。
―もともと監督も幼い頃からウンディーネの神話はご存じだったそうですが、あらゆることを間違って記憶されていたそうですね。ただ、記憶が曖昧だからこそ、それが監督の想像力を刺激するような部分もありましたか?
監督 そうですね。僕はその曖昧さこそがおもしろいところだと思っています。なぜなら、オリジナルの文学をそのまま再現するような映画は非常に退屈な作品になってしまいますからね。それよりも、曖昧な記憶について語るほうが興味深いものになるはずです。映画というのもまた、記憶なんですよ。
たとえばこの作品では、水中の世界を描いていますが、僕は潜水ができないので、本物の水中の世界に入ったことはありません。それでも、すべて僕らが想像するわけです。今回、水中のシーンはすべてスタジオに作ったものですが、そこで作られた水中の海藻や廃墟の壁などは実際にあるものを再現したわけではなく、想像をもとに作りました。そんなふうに、記憶や想像をもとに作るほうが僕は好きなんです。
―ウンディーネについての物語で、何か参考にされた作品はありましたか?
監督 先ほども言ったように、男性目線ではなく、女性の視点からウンディーネを描きたかったので、それに近かったのは、1961年に出版されたオーストリアの詩人で小説家のインゲボルク・バッハマンによる『ウンディーネが行く』という小説。この本を読んだときに、インスピレーションを受けました。
撮影前は、小津作品を毎回観るようにしている

―日本でも、三島由紀夫や手塚治虫といった巨匠たちがウンディーネをモチーフに取り入れた作品を描いていますが、日本の作品は読まれましたか?
監督 それらの作品は手に取っていませんが、撮影に入る前にキャストたちと水や海岸に関するいろいろな映画を観るなかで、小津安二郎や北野武の作品を観ることはありました。
そのなかでも僕にとって重要な作品は、小津安二郎の『晩春』。父と娘の関係を描いた物語で、特に自転車に乗って海に向かっていくシーンが非常に印象的な映画です。この作品は今回に限らず、僕が映画を作る際にはほぼ毎回観るようにしています。
―それはどういった理由からでしょうか?
監督 以前『東ベルリンから来た女』という作品を撮るときにも、キャストたちと一緒に観ましたが、『晩春』からは古いものと新しいものが共存した世界をたくさん学べるからです。
たとえば、アメリカが戦勝国であることがわかるような英語の標識が映されているいっぽうで、がんばって生きて行こうとする若い世代や父と娘という日本の家族についても描かれていますよね。そのバランスが絶妙なので、僕は映画を撮る前に観るようにしている作品のひとつです。
いつの時代でも共感できるものは愛

―非常に興味深いです。監督はこれまでの作品も今回も愛についての物語を描いているとコメントされていますが、映画で愛を描きたいと思う理由について教えてください。
監督 愛にはいろいろな愛があって、時代によっても異なるところはありますが、それでも共通しているところがあるので、いつの時代でも誰もが共感できるものだと感じているからです。
―確かに、愛にはそういうところがありますね。
監督 ちなみに、愛を毎回描いてはいますが、僕は映画のなかでセックスシーンを描くのが好きではありません。もしかしたら、若い頃に映画館でセックスシーンのある映画を観たあとに、家で両親からそういう気配を感じて恥ずかしい思いをしたことが理由かもしれませんが……。
ただ、今回の作品では1か所だけ、そういったシーンを入れました。なぜかというと、あそこではただ2人が裸でじゃれあっているのではなく、水中というメタファーに繋がっているからです。自分でもすごくいいシーンになったと感じています。
―非常に素敵なシーンだと思うので、ぜひ注目していただきたいですね。また、主演を務めたパウラ・ベーアさんとフランツ・ロゴフスキさんのおふたりも素晴らしかったですが、現場での様子はいかがでしたか?
監督 彼らとは『未来を乗り換えた男』でも仕事をしていますが、2人ともほかの俳優にはないようなやり方で演じるのが興味深いところです。新しく飼う猫を初めて家に連れてきたときの様子を思い浮かべてほしいのですが、猫は新しい飼い主の家のなかで、居場所を探そうとしますよね?
そんなふうに、この2人は見つめ合ったり、間合いを取ったりしながら感覚的な距離感を見つけていき、お互いのことを信頼していくのです。そこで生まれる大きな集中力を見たときに、すごい俳優たちだと感じました。
2人の愛が芽生える瞬間を見てほしい

―監督が観客にオススメしたいシーンはありますか?
監督 彼女のアパートでプレゼンの練習をしているところがありますが、あのシーンを撮ったときは、夜の素敵な景色も切り取れたので、2人の演技も含めてぜひ見逃してほしくないところですね。
あとは、冒頭で水槽が割れるシーン。ガラスの破片や金魚、海藻などがばーっと散らばり、まるで波打ち際のように水が押し寄せる瞬間に、愛が芽生えるので、僕個人としてもすごく好きなシーンです。
―では、今後はどのような作品を予定されているのか、最後に教えてください。
監督 次回作は、炎に関する「火の精」の物語で脚本もほぼできあがっています。ただ、俳優たちが触れ合うようなシーンを撮れるのは、来年になると思うので、撮影は少し先になるかもしれません。舞台はバルト海で、若者のグループがそこで夏を過ごしているのですが、森林火災が発生してしまいます。最初は楽しそうに始まるものの、徐々に彼らの心のなかにも燃え盛る炎があり、最後は……といった感じですね。
その次は刑事モノを撮って、さらにその次は大地をテーマにした「地の精」の作品を撮ろうと考えてるところです。ちなみに、大地の作品に関しては、ニュー・ジャーマン・ シネマのような作品ではなく、宮崎駿監督の作品のような雰囲気を出せたらいいなと思っています。
魅惑的な世界観の虜になる!

内に秘めた激しさと繊細な感情を表現している俳優陣の見事な演技と美しい映像、そして官能的な愛の物語から目が離せない本作。ミステリアスなウンディーネの魅力を前にすれば、まるで湖の底へと引きずり込まれるような感覚に陥るはずです。
取材、文・志村昌美
息を飲む予告編はこちら!
作品情報
『水を抱く女』
3月26日(金)より新宿武蔵野館、アップリンク吉祥寺ほか全国順次公開
配給:彩プロ
https://undine.ayapro.ne.jp/
© SCHRAMM FILM/LES FILMS DU LOSANGE/ZDF/ARTE/ARTE France Cinéma 2020