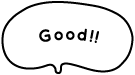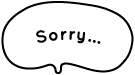志村 昌美
志村 昌美
岩井俊二監督「逆にエンジンがかかった」コロナ禍の心境を語る
世代を超えたラブストーリー『チィファの手紙』

【映画、ときどき私】 vol. 321
姉のチィナンを亡くしたばかりのチィファは、そのことを伝えるため、姉の同窓会へと向かっていた。ところが、会場で姉と間違えられたチィファは、姉が亡くなったことを言えないままその場を後にする。
そんななか、チィファの前に現れたのは初恋の人チャン。しかし、姉に想いを寄せていたことを知っていたチィファは、姉のふりをしたまま連絡先を交換するのだった。その後、チャンとの関係を誤解した夫はチィファのスマホを破壊。そこで、チィファはチャンに一方的な手紙を送りはじめることに……。
本作は中国で大ヒットしたのに加え、中国のアカデミー賞といわれる「金馬奨」でも最優秀主演女優賞、助演女優賞、脚本賞の3部門でノミネートされたほど話題となった作品。今回は見どころなどについて、こちらの方にお話をうかがってきました。
原作・脚本・監督を務めた岩井俊二監督

これまでに数々の作品で、多くの観客を魅了してきた岩井監督。本作は、今年1月に日本で公開され、人気を博した『ラストレター』と同じ題材を中国に舞台を移して描いています。そこで、監督にとって初の中国映画となる現場で感じたことや手紙の魅力、そしていまの心境について語っていただきました。
―今回、中国での映画制作は初となりましたが、本国で公開されたときの反響をどのように感じましたか?
監督 中国の映画市場は非常に巨大ですし、僕らが作ったのはあくまでもアート映画だったので、最初は上映してもらえればいいかなくらいでした。公開して2週間くらいはハリウッド映画の『ヴェノム』がスクリーンのほとんどを席巻していましたが、そのなかで2番手争いをしていたのは、実はこの作品と『名探偵コナン』だったんです(笑)。
でも、僕らの作品は中国映画だったので、日本人対決というよりも、中国映画として1位をキープできてよかったなという感じでしたね。
―監督はもともと中国でも人気が高いですが、そのなかでこの題材を選んだ理由を教えてください。
監督 中国には長年ファンでいてくださる人たちがいたので、感謝の気持ちが伝えられる映画がいいかなと考えていたんです。そのなかで今回の企画を選んだのは、1995年の『Love Letter』と重なるところがあったから、というのもありました。
実際にこの映画に取り掛かったのは、3~4年ほど前からですが、中国チームとやりとりをはじめたころから数えると10年越し。準備も含めるとけっこう長かったなと思います。
自分から挑戦しないと、よりよい作品は生まれない

―作品を仕上げるなかで、中国の方々にとって違和感のない映画にするために、かなり細かい部分までリサーチをしたそうですね。特に苦労した部分はありましたか?
監督 回想シーンは30年くらい前の話になるので日本でいうと平成のはじまり頃ですが、中国では文化大革命が終わったあと。いまとは風俗や景色もまるで違うので、ローカライズにはかなり時間をかけました。
セリフを1行ずつチェックされ、アドバイスを受けることも。そこで、自分のやりたいことが修正されたこともありましたが、終わってみるとその修正がネガティブな結果になったことはほとんどありませんでした。むしろ、それによって思いがけないエピソードが膨らんでいった部分もあったくらい。
たとえば、 日本版では主人公には子どもが2人、お姉さんには1人いる設定ですが、一人っ子政策や社会状況を踏まえて、中国版では主人公に子どもが1人、お姉さんには2人と逆にしてみたりしました。結果弟のシーンが膨らんで映画の重要な柱の一つになりました。
最初は苦行みたいに感じたこともありましたが、それによって一回りも二回りもよくなっていったので、いまでは自分のモノづくりにおいて「これでいいだろう」と思うのではなく、「自分から挑戦していかないと、よりよい作品は生まれない」と考えるようになりました。
―では、中国のキャストやスタッフと一緒に仕事をされてみて、何か学んだことはありましたか?
監督 一番思ったのは、スタッフの私語があまりないことですかね。日本の現場ってけっこうおしゃべりしていい空気があるんですけど、一般の職場だったらあまりしゃべらないですよね……。
今回プロデューサーを務めてくれたピーター・チャンが撮影している別の現場も見学させてもらいましたが、巨大なスタジアムがシーンとしていて、そのなかで聞こえているのは指示を出している人の声だけ。非常に緊張感のある現場で、すごいなと思いました。実は前から日本の現場はおしゃべりだなと少し気にはなっていたんですが、改めてそういうことを感じたところもありましたね。
でも、しゃべってる人たちに「おしゃべりするな」と言って歩くのもなんかやるせないし、感じ悪いので自分の現場で実践するとなるとなかなか難しいのかなとは思いますが(笑)。
手紙にまつわる仕草には情緒があり、惹かれるものがある

―確かに難しいかもしれないですね……。では、本作のモチーフにもなっている手紙についておうかがいしますが、これまでも手紙に関する作品を監督は撮られています。手紙にまつわる原体験があれば教えてください。
監督 僕は仙台で生まれ育ったあと、横浜の大学に入ったので、そのころは友達から手紙がよく来ていました。LINEも何もない時代でしたけど、お互いに手紙を送り合うのはけっこう楽しかったですね。そういうことは、手紙を振り返ったときの懐かしい思い出としてあります。あとは、書簡体の小説を読んだりとか、手紙をエピソードにした作品を目にしたりしているうちに、やってみたいという思いがだんだん積もっていった気がしますね。
―デジタルの発達によって手紙は廃れつつありますが、だからこそ惹かれるものがあるのでしょうか?
監督 『Love Letter』では主人公がワープロを使って手紙を書くスタイルでした。かつては手紙を書くという所作はありきたりだったので変化を求めたわけですが、今回は便せんにペンで書くという一番オーソドックスな手法を取りました。改めてカメラを通して見ると、手紙を書く仕草にも読む仕草にも情緒があるんですよね。歴史があるからなのか、失われつつあるせいなのか、見ていてしみじみと自分のなかに去来するものがありました。
スマホで同じことをしても、風情がないですよね。映画を作る側からすると、いろいろな仕草や佇まいが新しい端末によって相当変わってしまったので、名残惜しい気はしています。
たとえば、昔だったら電話のシーンで、まず誰かが受話器を取って、「○○ちゃん、電話だよ」と声を掛けて、人が来るみたいな動きがありましたが、いまだと一瞬で終わってしまって、人の交流がないですから。こうやってどんどんいろいろなものが失われていくのは、心配ではありますね。
時代の鏡となるものを作っていると改めて気がついた

―2020年は新型コロナウイルスという大きな出来事がありましたが、そのなかでも『8日で死んだ怪獣の12日の物語』など、新しい試みで作品を作られました。ご自身の映画人生においても、新たに気づかされることもありましたか?
監督 まだ振り返れる段階ではないと思いますが、ミニシアターの大変な状況を目の当たりにして、自分がいかにミニシアターと深く関わっていたのかということを改めて考えさせられました。
あとは、僕のように作品を作る立場の人間ががんばって現場を作っていかないといけないんだ、ということも意識させられて、自分のなかでは逆にエンジンがかかったように感じています。
―リモートで映画を作ることも、いままでなら考えられなかったことではないでしょうか。
監督 そうですね。でも自分たちが作っているものは、時代の鏡みたいなものなんだなと思いました。たとえば、通常ならいろいろなアングルで撮ろうとするところも、緊急事態宣言中に映像を撮るうえでは、不思議と必要性を感じませんでしたが、理由はそれがいまの状況にかみ合わないというか、このコロナ禍を映し出さないように思えたから。
そんなふうに、映像のアングルにまで影響を与えているという意味でも、今年はとんでもない年になってしまいましたね。いままではあまり強く意識していませんでしたが、こういうことが起こると、映画というのは時代が映り込んでしまうものなんだ、ということに改めて気づかされます。
―今後の作品づくりにおいて、影響を与えているところもありますか?
監督 世界中がそうですが、「撮影現場を簡単には組めないなかでどうしていくのか?」ということを考えなければいけないなかで、まだ答えが出ていないですね。行定勲監督とも電話で話しながら、今後の対策をお互いに相談し合っているところですが……。
いまは“やれること”と“やれないこと”がすごくはっきり分かれているので、工夫するしかないんだと思っていますが、本当に難しいですね。
文化を通して、プラスのイメージを伝えていきたい

―そういった制限があるなかで、いまやりたいこととは?
監督 自分なりのいまを描こうと思った部分に関しては、『8日で死んだ怪獣の12日の物語』で一旦形にはしてみましたが、次に関しては、持っていたアイディアがすべてコロナ以前に考えていたものですから、「はたしてこのなかから作品にできるものがあるのだろうか」というのは、いまの落ち着かない状況のなかだと見つけにくいところだと思います。
いままでも病気や災害などいろいろなことがありましたが、去ったら去ったで、人はわりと忘れやすいものだという気がしているので、もしかしたら10年後にはあまり思い出さないことのひとつになっているかもしれないですよね。
記憶として消す必要はないですし、消してはいけないものでもありますが、忘れることが必ずしも“悪”だと僕は思っていません。これからも繰り返されることはあるかもしれないですが、これもそのひとつなのかなと。いまのところはしばらく見守るしかないと思っています。
―こういった状況で、監督のモチベーションとなっているものを教えてください。
監督 自分が子どものころを振り返ってみると、ベトナム戦争があったり、公害の問題があったり、オイルショックがあったり、70年代は相当暗い時代でした。ただ、そういう居心地の悪いところからだんだんと右肩上がりになり、明るくなっていくのを子どもながらに体感したことは覚えていますね。
そういう兆しや浮揚感を小説や音楽、映画、漫画といったものから嗅ぎ取っていたので、文化として世に放つことの意味は、すごくあると僕は感じています。
80年代に、スティーヴン・スピルバーグとジョージ・ルーカスが子どもたちに夢を与えたいと言っていた記事を読んだことがありましたが、そんなふうに文化が時代のムードを作っていくことができるんじゃないかなと。さりげないものでもいいので、プラスのイメージを伝えられたらいいなと最近は思っています。
淡くて美しい物語に心が動く!

中国の実力派キャストが顔を揃え、日本版とはまた一味異なる物語を楽しむことができる本作。現代のデジタルなコミュニケーションでは味わうことのできない手紙の温もりと、そこで交錯するそれぞれの思いに、切なさとトキメキで心が満たされるのを感じてみては?
引き込まれる予告編はこちら!
作品情報
『チィファの手紙』
9月11日(⾦)新宿バルト9他全国ロードショー
配給:クロックワークス
© 2018 BEIJING J.Q. SPRING PICTURES COMPANY LIMITED WE PICTURES
LIMITED ROCKWELL EYES INC. ZHEJIANG DONGYANG XIAOYUZHOU
MOVIE & MEDIA CO., LTD ALL Rights reserved.
©Munehiro Saito
https://last-letter-c.com/