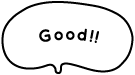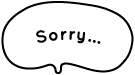志村 昌美
志村 昌美
「体に電気が走るよう」話題の監督が圧倒された“病の少女と不良青年の恋”
『ベイビーティース』

【映画、ときどき私】 vol. 362
病を抱える 16 歳の女子高生ミラは、ふとしたことから不良青年モーゼスと出会う。家を追い出され、孤独だったモーゼスをミラは自宅へと食事に誘うが、母アナと父ヘンリーは、モーゼスはミラにふさわしくないと嫌悪感を示していた。
そんな両親の猛反対をよそに、ミラは怖いもの知らずで自分を特別扱いせずに接してくれるモーゼスに惹かれ、どんどんのめりこんでいく。彼との刺激的でカラフルに色づいた日々を駆け抜けていくミラだったが、病は容赦なく彼女の体をむしばんでいくことに……。
世界各国の映画祭でグランプリや観客賞を数多く受賞し、映画評論サイト『ロッテントマト』でも現在94%という高評価を得ている本作。そこで、こちらの方にお話をうかがってきました。
シャノン・マーフィ監督

Variety 誌に「2020年注目すべき10人の監督」に選出されたこともあるマーフィ監督。長編デビュー作にして、大きな注目を集めています。今回は、本作の魅力や現場で心を動かされた瞬間などについて語っていただきました。
―本作が長編映画1本目となりましたが、この脚本を選ばれたのはなぜですか?
監督 実はここ2年ほど、長編デビュー作となる企画をずっと探していました。私は自分で脚本を書かないタイプなので、“自分の声”を持っていると感じられるような脚本を求めていましたが、なかなか見つけることができなかったんです。でも、そんななかでこの脚本を読んだときは、すぐに「これだ!」と感じることができました。
―原作は、オーストラリア出身の戯曲家で女優のリタ・カルネジェイスさんが手掛けた演劇ですよね。この物語のどのようなところに惹かれたのかを教えてください。
監督 最初に脚本を受け取ったとき、家のソファーに座って読んでいましたが、そのときにものすごく圧倒されたことをいまでもよく覚えています。なかでも、ミラ、モーゼス、アナ、ヘンリーという4人のキャラクターたちと過ごす時間がとても愛おしく感じました。でも、脚本を読み終えたら、その時間も終わってしまったので、それがとにかく悲しくて……。
だからこそ、この作品の監督をすることができれば、少なくとも2年間はこの4人と一緒に過ごすことができるんだと思い、何としてもこの仕事をものにしたいと考えました。なので、一番は4人のキャラクターたちですね。
大きなプレッシャーを感じる撮影だった

―そのときに、これはやりがいのあるものだと感じて挑戦したいと思われたともうかがっていますが、今回作品を作るうえで挑戦だったことはなんですか?
監督 まず、ひとつ目の大きな挑戦としては、ミラ役の女優に髪を全部剃ってもらうこと。製作費にそういったメイクを毎回する予算がなかったというのもありますが、私自身が本物であることを求めているので、これはマストの条件でした。
ただ、そこで発生したのは、いろいろな撮影のスケジュールの調整が難しくなるという問題。というのも、父親役のベン・メンデルソーンのスケジュールが10日間しか取れなかったうえに、そのうちの2日間でミラに髪を剃った状態で参加してもらわなければならず、そう考えると残りの8日間で彼のパートをすべて撮り終えなければならなかったので……。
それは本当に大変なことでした。自分にも非常に大きなプレッシャーをかけることになってしまったので、今後は2度とそうならないようにしたいなと思ったほどです(笑)。
―今回は若手キャストもすばらしく、非常に魅力的で印象的でした。まずミラ役のエリザ・スカンレンをキャスティングした理由を教えてください。
監督 ミラ役を決定するまでにはかなり時間がかかってしまい、何百人もの候補の方々に会いました。そこまで時間がかかってしまった理由としては、私自身もミラというキャラクターの本質を見極めるのに時間がかかってしまったからでした。
そんなときに気がついたのは、ミラというのはいろいろな側面を持っている人物なので、何者にもなれる幅広い演技力を持っている女優であれば、一緒にキャラクターを作っていけるのではないかということ。そこで、エリザをキャスティングすることにしました。
というのも、彼女は怖いくらいの才能の持ち主で、彼女自身がどんな人間なのか見当がつかないくらい本当にいろいろな顔を持っている人ですからね。
ケミストリーは現場で一緒に育むもの

―では、本作でヴェネチア国際映画祭の最優秀新人賞に輝いたモーゼス役のトビー・ウォレスさんについてはいかがですか?
監督 彼の場合は、出演していたテレビシリーズを見て、オーディションを受けてもらうようにお願いしたのがきっかけでした。実際に、オーディションで彼の様子を見ていると、自分を主張するようなこともなく、つねに周囲や相手のことを思いやれる人であることがわかったんです。それを目にしたときに、「ああ、これはモーゼスのエネルギーだな」と感じました。そういった理由から、彼にモーゼスを演じてほしいと思ったんです。
ちなみに、アメリカなどでは、ラブストーリーやバディもののように2人を中心に描くような作品では、ケミストリーリーディングといって、事前に2人の相性を見る練習をすることがあります。でも、今回の作品ではあえてそれをせず、2人にはリハーサルで初めて会ってもらいました。
―それによって、どのような効果が生まれたと感じていますか?
監督 まず、私は監督として、ケミストリーリーディングというのをあまり信用していません。なぜなら、役者2人を部屋に閉じ込めて、相性がいいところを見せてくださいとお願いするのは、すごく人工的なことだなと思うからです。私が考えるケミストリーというのは、事前に確かめるものではなく、現場で一緒に育んでいくものではないかなと。だから、今回も特に心配はしていませんでした。
電気が走るような感動を味わうことができた

―実際、現場で生まれた2人の化学反応に驚かされた瞬間はありましたか?
監督 夜に外出するシーンがありましたが、あのときはとてもマジカルな夜だったと思います。特に、カラオケバーで踊っている場面では、スタッフの誰もが2人の繋がりを感じ、電気が走るような感動を味わうことができました。本当にワクワクするような瞬間でしたね。
エリザとトビーの2人も、この日の撮影中は2人だけで過ごす時間を作ってみたり、お互いに手を取り合ってみたりしながら役作りをしていました。どういうふうに2人の雰囲気を作り上げていけばいいのかをよくわかっているので、本当に聡明な役者たちだなと。なので、私も2人を信用し、ペースを合わせることを意識していました。
―そんななかでも、監督が演出でこだわった部分はどのようなことでしょうか?
監督 基本的に私はしっかりとすべてをチェックするタイプですが、同時にカオスやクリエイティビティがつねにある状態を作ることも大切にしています。というのも、監督がミクロン単位までマネージメントした演技だと、その人自身に見えなくなってしまうこともありますからね。
細かくこうしてほしいという要望はありますが、そのなかでもお互いにアイディアを出し合い、つねに自由であることをキープするようにしているつもりです。そうすることで、独特なエネルギーが生まれるので、私はそれをとらえるような演出にこだわっています。
―監督にとって、ミラとモーゼスの関係性はどのように見えましたか?
監督 2人はとても不思議な関係性だと思いました。プラトニックのようでありながら、すごく性的なエネルギーを感じさせ、さらにそれ以上にお互いを求めあっているようなところがありましたから。ミラにとっては、自分の心が一番落ち込んだときに寄り添ってくれる人が必要であり、モーゼスにとってはほかの人とは違う視線で自分を見てくれる人が必要だったんじゃないかなと思います。
失うものがないからこその自由はすばらしい

―脚本のリタさんは、「失うものが何もなくなったとき、どんなふうに感じるか?」という大きな問いからこの作品が生まれたとおっしゃっています。監督自身もこの作品を通じて、そういったことを考えさせられましたか?
監督 ある状況下において、自分がどんなふうに振る舞うかは誰にも予測できないものだと思っています。だからこそ、キャラクターたちがそれぞれの状況に置かれたときにどんなふうに反応するのかを掘り下げていく作業は、非常に楽しかったです。
この物語には、依存症という大きなテーマも取り上げていますが、そこに関してキャラクターを厳しく裁くことなく、困難を乗り越え、うまく向き合うために薬の力を借りてしまう人と依存症の関係性を描きました。そのなかで、私は生きるうえで何も失うものがないからこそ得られる自由はすばらしいものだと私は感じています。
みなさんにも、この作品を観たあとに自分の人生においても、そんな自由がある生き方をしたいと思っていただけたらいいなと。たとえミラのように末期的な病を抱えていなかったとしても、そういう生き方をしてほしいと願っています。特に、2021年にはこういったことが大きなメッセージとなるのではないでしょうか。
―監督自身もこの作品と出会ったことで、物の見方が変わった部分があったのでしょうか?
監督 もともと私自身が持っていた考え方が多く反映されている作品ではありましたが、この映画を撮り終えたあとで、よりミラのことを思い出すことが多くなりましたね。そのうえで、鳥や海を眺める時間が増えたり、人生において素敵なものを気に留めるようになったり、生きているうえですばらしいと思ういろいろなものに対する感謝の気持ちを改めて噛みしめています。
人は忙しいとそういう感覚を忘れてしまいがちですが、それらを当たり前だと思わないようにしたいですね。ときには足を止めてその瞬間をしっかりと体感していますし、生きていることを以前よりも意識するようになったかもしれません。
―現在、監督としてますます注目を集める存在となりつつありますが、ご自身ではどのように感じていますか?
監督 「2020年注目すべき10人の監督」として取り上げられたことで、「オーストラリア以外でも私のことを監督として認知してくれるところがあるんだ」という意識を初めてはっきりと持つことができました。ただ、それとは関係なく、この先もつねに自分に対して挑戦を突きつけていきたいです。
まだ具体的に言えるものはありませんが、ミュージカルや機能不全に陥っている家族の物語など、さまざまなドラマをこれからも描きたいなと。ユニークな作品づくりが私にはできると思っているので、どんな企画でも取り組んでいけたらいいなと考えています。
美しい映像とともに引き込まれる!

少女が経験した最初で最後の恋を刹那的に描き、観る者を虜にする本作。恋のきらめきと痛みに激しく心を揺さぶられ、両親からのあふれる愛にも胸を締めつけられる珠玉の1本です。
取材、文・志村昌美
心に刺さる予告編はこちら!
作品情報
『ベイビーティース』
2⽉19⽇(⾦)新宿武蔵野館、 渋⾕ホワイトシネクイントほか全国ロードショー
配給:クロックワークス/アルバトロス・フィルム
https://babyteeth.jp/
© 2019 Whitefalk Films Pty Ltd, Spectrum Films, Create NSW and Screen Australia