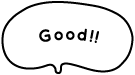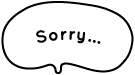志村 昌美
志村 昌美
佐橋佳幸が語る「坂本龍一や松任谷由実らが愛する音響ハウスの魅力」
ギタリストの佐橋佳幸さん

【映画、ときどき私】 vol. 343
佐橋さんが出演している本作で舞台となっているのは、昨年で創立45周年を迎え、「CITY-POP」の総本山として近年ふたたび注目を集めているレコーディングスタジオ「音響ハウス」。今回は、日本の音楽史を陰で支え続けてきた音響ハウスとゆかりの深い佐橋さんに、スタジオの魅力や忘れられない思い出などについて語っていただきました。
―まずは、初めて音響ハウスに来たときのことを教えてください。
佐橋さん 高校の先輩に、シンガーソングライターのEPOさんとアレンジャーの清水信之さんがいましたが、僕が音楽業界に入る大きなご縁となったのは、彼らとの出会いでした。あるとき、そのおふたりが音響ハウスでレコーディングしていると聞いて、「見学に行っていいですか?」とお願いして来たのが初めて。
僕は組んでいたロックバンドの解散が決まって、音楽活動とバイトを掛け持ちしていた頃でした。1985年にリリースされたEPOさんの「私について」という曲をレコーディングされていたときに、清水先輩からいきなり「ちょっとギター弾いていくか?」と言われたんです。で、そこにあったギターでソロを弾きました。あれがここで初めて演奏した瞬間でしたね。
―このスタジオでの経験が、音楽の道で生きて行こうとする気持ちを後押しした部分もありましたか?
佐橋さん それはありましたね。そのあと僕はスタジオミュージシャンをやりつつ、編曲家やプロデューサーとして裏方の仕事も始めるわけですが、35年以上のキャリアのなかで一番多く来ているスタジオは音響ハウス。少し前にもレコーディングで来たばかりですが、やっぱりいいですよね。
ここはインディペンデントのスタジオとしては先駆けだったそうで、それがいまだに同じ場所で、稼働し続けているのはすごいことだと思います。あとは、場所が銀座というのもいいですよね! 当時、下北沢に住んでいた20代の若者にとっては、銀座に行くというだけでもイベント性が高かったです(笑)。
「ここに来ない理由がない」のひと言に尽きる

―いままでを振り返って、思い出の場所や忘れられない出来事を教えてください。
佐橋さん 通常、最後は6stで全部の音をまとめるミックス作業をすることが多いんですけど、その間スタジオ前のロビーで曲が仕上がるのをずっと待っている時間が楽しいんですよ。曲が完成する瞬間は、ワクワクしますからね。
当時はテープに録音していたので、いまなら1時間でできることも3~4時間くらいかかってしまうのが普通で、当然スタジオにいる時間が長くなり、ここで1日中過ごすというのが日常茶飯事でした。でも、居心地がいいんですよね。それはみんながここを好きな理由でもあるのかなと。
それから、映画のなかで矢野顕子さんがいまはないとんかつ屋さんの話などをしていましたが、ここで食べる出前も思い出深いんですよ。だから、銀座のグルメもここで味わった感じかな。しかも、人のお金で(笑)。
―素敵な思い出ですね。ちなみに、ここだからこそ生まれた曲というのも、ありましたか?
佐橋さん いろいろありますが、一度、ほかのスタジオで録音した曲が、どうしても思い通りのサウンドにならなくて、ピアノだけここの2stで録り直したということがありました。
ほかのパートも、ピアノの演奏も素晴らしかったんですけど、ピアノの音だけがイマイチで……。それでプレイヤーに音響ハウスに来てもらって、ピアノだけ演奏して差し替えました。結果的には、妥協しなくてよかったと思える仕上がりになりましたが、そんなこともありましたね。
―そういった設備の豊富さやクオリティの高さも、音響ハウスの魅力のひとつでしょうか?
佐橋さん そうですね。ここは、時代の最先端に全部ついてきたところはあると思います。しかも、ここに常設してある機材や楽器は非常によくメンテナンスされているんですよ。最近のスタジオでは楽器どころか、ピアノがないところもありますから。
たとえば、星野源ちゃんがいまだにここを使うのは、彼の好きなマリンバがちゃんとあるというのも大きいんですよ。昔から劇伴やCMのセッションも多いので、基本的な楽器が揃っている。とても安定した響きを持った部屋もありますし、僕みたいにみんなで合奏したい人にとっては大勢で音を出せる広いスタジオ環境も魅力。とにかく好きなところや素晴らしいところがいっぱいあるので、「ここに来ない理由がない」というひと言に尽きます。
おもしろいインスピレーションが湧いてくる場所

―ミュージシャンのみなさんにとっては、インスピレーションを刺激してくれる場所でもあるんですね。
佐橋さん 過去には、10人のギタリストが弾いているような効果を僕ひとりで出したくて、「広い部屋にもし10人のギタリストがいたら?」というのを想像しながらある実験をしたこともありました。同じパートをひとりで10回演奏するんですが、1回録音するごとにマイクをどんどん離し、10人が1つの部屋で同時に演奏している様子を疑似的に生み出しました。できあがりは、最高でしたし、おもしろかったですね。
ここでしかできない実験や無駄な努力に見えるようなことも、本当にいろいろとやりました。でも、みんな本気ですし、おかしなことをしていても、誰も「バカじゃないの?」とは言わないんですよ。だからそういうおもしろいインスピレーションが湧くんだと思います。
―最高の環境ですね。では、そのなかでも佐橋さんがお気に入りの場所を教えてください。
佐橋さん 実は、2stを使うときには、“僕の部屋”みたいにしているスペースがあるんです。本来ドラムのブースなんですが、そのなかにギターのアンプを入れて扉を全開にして弾くと、すごくいい音がするので、そこが僕の好きな場所。
今回、映画のなかで作っている新曲「Melody-Go-Round」でも、(葉加瀬)太郎ちゃんのソロのあとにある僕のギターソロはそのスタイルで録りました。ここには数えきれないほど来ていますが、長年通うなかで見つけた方法です。
―では、完成した映画をご覧になったときに印象に残っているエピソードはありましたか?
佐橋さん 自分が出ていないほかの方々の話は、どれも本当におもしろかったです。特に、矢野顕子さんが娘の(坂本)美雨ちゃんが眠たくなったときに、ドラムセット用の毛布をかけて寝かせたというのには爆笑しましたね。
あとはプロデューサーの笹路正徳さんが音響ハウスの響きのことを「真面目な音」っておっしゃっていましたけど、まさにその通りだなと。オリジナリティを追求するあまり、変わった響きのスタジオもありますが、ここはどの部屋も本当にナチュラルな響きを持っているので、「ここでやれば間違いない!」という安心感はありますね。
それから、大貫妙子さんがテープで録音していた時代の話をされているなかで、「テープを巻き戻す時間がいいのよ」とおっしゃってましたが、確かに僕もあの時間に次はどうしようかなって考えていたことを思い出しました。
みんなの思いがそのまま曲に反映されている

―アナログならではの良さがあったということですね。
佐橋さん そうですね。ただ、いまでは笑い話だけど、当時はスタジオにいたみんなが固まってしまうような出来事もありました。たとえば、現在は有名な録音エンジニアがアシスタントだった頃、撮り直さないといけないところを残して、残さないといけないところを間違えて全部消してしまったんです。
いまは間違えても、「Undo」で簡単に戻れますけど、あのときはそれができない時代でしたから。怒鳴られて泣いてましたよ(笑)。とはいえ、やり直せないからこそ味わう緊張感は優秀な人材を育てるためには、必要な部分もあるのかなとも思っています。
―それはあるかもしれないですね。では、新曲「Melody-Go-Round」についてもおうかがいしますが、今回こだわった部分を教えてください。
佐橋さん この曲は、井上鑑さんや高橋幸宏さんをはじめ、音響ハウスを好きで使い慣れているメンバーが集まっているので、みなさんにもここのスタジオならではの音作りをしてもらえたと思っています。
楽曲としては、80年代っぽいところがありますが、その時代はちょうど僕が音響ハウスデビューした頃なんですよね。撮影中もその当時のことや失敗した思い出話とか、お化けが出た話とか、いろんな話をしながら作ったので、そういうみんなの思いもそのまま曲に反映されていると思います。
―現在はコロナ禍で音楽業界も大変だと思いますが、そのなかでお感じになっていることはありますか?
佐橋さん エンタメ業界に関するガイドラインは、現場の事情がわかる人の意見を聞いたうえで見直してほしいという気持ちはありますね。すでに潰れてしまったスタジオもありますし、今後もそういうところは増えてきてしまうと思うので。本当に、現場は大変なことになっていますから。
そのいっぽうで、みんな時間ができてものづくりに励んでいるところはあるので、いつかこの騒動が終わったとき、新しい良質なものがたくさん生まれている可能性もあるのかなと。僕も、そういう前向きな考えで過ごすようにはしています。
ちなみに、これまでは家でギターを弾くことはあまりなかったんですけど、最近は家でも毎日弾くようになりました。もしかしたら、前よりもうまくなったかもしれないです(笑)。先日、Charさんにこの話をしたら、「俺も今までで一番ギター弾いてるかもしれない」と。お互いに「酒を飲むか、ギターを弾くしかないよな」って話になったくらいです。
時代にそくしたものづくりを大事にしていきたい

―(笑)。いままでとはまた違う音楽との向き合い方をされているんですね。
佐橋さん そうかもしれないですね。あと、僕はギタリストの小倉博和さんと「山弦」というギターのデュオもやっていますが、「リモートでやろう」って話になって、もうすぐ15年振りのアルバムが完成しそうです。そんなふうに、おうちでできることもあるんだなというのは感じています。ただ、繰り返しにはなりますが、早くきちんとしたガイドラインの変更は早急にお願いしたいですね。
―では、佐橋さんにとって“いい音”を生み出し続ける秘訣を教えてください。
佐橋さん 時代の変遷とともにツールやメディアも変わるので、音も変わってしまいますが、僕はその都度エンジニアやスタジオの方々と相談しながら自分が表現したいイメージに近づけていくようにはしています。それはたとえるなら、いつも変わらない味を出し続けている老舗の料理屋さんと同じこと。食材も人もいつも同じとは限らないなかで、ただ同じことを繰り返しているだけではなく、変わらない味を出すための努力をしているはずですから。
そんなふうに、僕らも時代にそくしたスタイルにアレンジしながらものづくりすることは大事なことだと思いますし、変わっていくことに対応しないといけないなと。僕は「いつも通りやってるから責任取れないよ」みたいな生き方はしたくないですね。座右の銘は「温故知新」ですけど、ただの懐古主義になってしまうのではなく、「2021年なら2021年らしい音」みたいにそのときに合った音をこれからも作っていけたらいいなと思っています。
インタビューを終えてみて……。
とても気さくで、いろいろな裏話を聞かせてくださった佐橋さん。アーティストのみなさんがいかに音響ハウスを愛しているのか、その理由がよくわかりました。これからもここで誕生する素敵な音楽が、私たちの人生を彩り豊かなものにしてくれる予感でいっぱいです。
45年にわたる歴史の重みを感じる!

まるで音響ハウスのなかに、一緒にいるかのような気分を味わえる珠玉のドキュメンタリー。一流のアーティストたちがものづくりをする感動的な瞬間はもちろん、普段はなかなか見ることのできないミュージシャンたちの素顔も垣間見ることができるのはうれしいところです。“至福の音”に身を委ねてみては?
写真・北尾渉(佐橋佳幸) 取材、文・志村昌美
ストーリー

1974年12月、東京・銀座に設立された音響ハウス。多種多様なスタジオを持つ総合スタジオとして、数々の有名アーティストたちに愛されてきた。本作で、音響ハウスとの出会いや楽曲の誕生秘話について語っているのは、坂本龍一をはじめ、松任谷由実、松任谷正隆、佐野元春、綾戸智恵、矢野顕子、鈴木慶一、デイヴィッド・リー・ロス(ヴァン・ヘイレン)といった錚々たる顔触れ。
そんななか、ギタリストの佐橋佳幸とレコーディングエンジニアの飯尾芳史が発起人となり、大貫妙子や葉加瀬太郎、井上鑑、高橋幸宏といった音響ハウスにゆかりのあるミュージシャンによるコラボ新曲「Melody-Go-Round」が誕生しようとしていた。
心が躍る予告編はこちら!
作品情報
『音響ハウス Melody-Go-Round』
11月14日(土)より渋谷ユーロスペースほか全国順次公開
配給:太秦
©2019 株式会社 音響ハウス
https://onkiohaus-movie.jp/