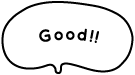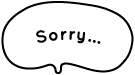志村 昌美
志村 昌美
虐待、強制結婚、育児放棄…12歳の少年が両親を告訴した理由とは?
全世界が絶賛する『存在のない子供たち』!

【映画、ときどき私】 vol. 246
中東の貧民窟に生まれた12歳の少年ゼインは、学校にも通わずに朝から晩まで両親に働かされていた。両親が出生届を出さなかったために、法的には社会に存在すらしていないゼイン。唯一の支えは妹のサハルの存在だけだった。
ところが、サハルが11歳で強制結婚させられてしまい、怒りと悲しみからゼインは家出をしてしまう。そこでは厳しい現実が待ち受けていたが、ゼインは「僕を産んだ罪」を理由に、自分の両親を訴えることを決意するのだった……。

中東が抱える貧困と移民の問題に真っ向から挑み、高く評価されている本作ですが、今回は全身全霊を捧げたこちらの方に、あふれる思いについてお話いただきました。
レバノンが生んだ美しき才能ナディーン・ラバキー監督!

2007年には、『キャラメル』で監督・脚本・主演を務め、一躍注目を集めたラバキー監督。女優としても幅広く活動しており、本作ではゼインの弁護士役として出演もしています。そこで、自身が目撃した現実やいまの思いについて語っていただきました。
―まずは、多くの難民を受け入れてきたレバノンの現在の状況から教えてください。
監督 レバノンは文化的にも、国民の気質的にも、誰に対しても温かく歓迎するところがあるので、これまでに150万人以上の難民を受け入れてきましたが、これはいろいろな意味で大きな挑戦でもありました。
そのなかで私たちはベストを尽くしてはいますが、本来この責任は世界でわかち合わなければいけないもの。難民条約にサインしたにも関わらず、多くの国がその責任を果たしていません。
それゆえに、ヨルダンやトルコなど近隣諸国が難民の60%以上を受け入れており、経済的にも社会的にも大きな影響を受けています。世界で考えたら、本来はもっとできることがあるはずですが、これが現状です。

―では、本作のストーリーは監督が実際に見たものが描かれているのでしょうか?
監督 レバノンでは苦しんでいる人々を当然のように目にする状況にあります。食べ物が足りないとか、戸籍がないために世間から“見えざる者”になってしまっている人や違法滞在者など、本当につらい現実です。
水も電気もなく、まるで下水道のなかにいるかのような耐え難い環境で暮らしている人たちも多く、収容所やキャンプでは寒さが原因で亡くなる方もいるほど。いまでは難民だけでなく、レバノン人にとっても非常に厳しい状況が続いています。そして、そのなかでもっとも心を痛めているのが、子どもたちについてです。
犠牲を払っている子どもたちの“声”を届けたかった

―その思いがこの作品を作るきっかけとなりましたか?
監督 彼らが寒さに震えていたり、お腹を空かせていたり、学校に通えなかったり、子どもなのに仕事をしなければいけなかったり、つらい思いをしている姿を見るたびに、「私たち大人がいかに彼らを失望させているのか」「いかにシステムが欠落しているのか」を感じています。
子どもたちが一番もろい存在のはずなのに、一番大きな代価を彼らに払わせてしまっているのです。その結果、自分の誕生日も知らず、無言のままに重荷を背負わされ、毎日虐待されるつらい生活が普通の人生だと考えている子どもはたくさんいます。そして、彼らは存在を知られることなく生まれ、存在を知られないまま亡くなっていくのです。
私はそういった現実を見ているうちに、「何かしなければいけない」という責任を感じましたし、この映画を作ることを義務だと思うようになりました。つまり、子どもたちは声なき者だからこそ、この作品は彼らの“声”として届けたかったのです。

―今回は主人公のゼインを演じた少年が本物のシリア難民であることをはじめ、全員がプロの役者ではないそうですが、どのように選びましたか?
監督 本作は3年間かけてリサーチをしてから脚本を書いたので、私自身が見たものからインスピレーションを受けており、事実が基になっています。キャスティングについても、現実世界で同じような境遇にある人を探すという方法で、彼らを見つけることができました。
たとえば、ゼインの外見は、栄養不足が原因で実年齢よりも体つきが小さい子どもたちをたくさん見てきたということを反映させています。キャラクターのイメージとしては、家族のために早く大人にならなければいけなかった環境にあったため、聡明さと路上で生きるタフさを持つ、大人のような子ども。それが頭のなかで描いていたゼイン像でしたが、想像していた通りの少年と出会ったときは奇跡のようでした。
―彼らの実人生が役に影響を与えた部分もありましたか?
監督 通常の映画であれば、脚本や監督のイメージに役を合わせていくものですが、今回は彼らの個性をベースにして、私たちがそこに合わせていくような作り方を意識しました。そもそも彼らの生活や人物像というのは私が想像で作り上げてはいけないものだし、そんな権利は自分にはないと感じていたからです。
それほど現実にはリアルな苦しみと困窮があるわけだから、なるべく真実を捉えたいと考えていました。彼ら自身の経験や感情を私たちが描こうとしている物語やキャラクターを寄せていったので、スタッフも演者たちも現実とフィクションがわからなくなって混乱することもあったくらいです。
演者が自分の経験をアドリブで語ることもあった

―そのなかで忘れられない出来事もありましたか?
監督 実際、彼らが本能的に自分の経験を話すようなアドリブも多くありました。たとえば、子どもから訴えられたゼインの母親が「あなたは私のような状況に置かれたことがないからそんなことが言えるんだ」と弁護士役の私に向かって言うシーン。
そのなかで、母親役の女性が「お金がなくて子どもに砂糖と水しか与えられない経験をしたことがないでしょう?」と訴えるのですが、これは彼女自身の経験です。彼女は映画のなかに出てくるスラム街に住んでいる人ですが、あの瞬間はゼインの母親としてではなく、自らの思いを語っていたのです。ほかのみんなも同様のことをしてくれました。
―だからこそ、俳優では演じられないようなリアルな表情には思わず言葉を失いました。
監督 自らの現実と演じている役が入れ替わってしまうこともありましたが、彼らの言葉はすごく重要だったので、そういったものが自然に起きるようなオープンな現場は意識していたところです。
つまり、彼らが「どんなことを言っても大丈夫なんだ」と自由でいられる環境をしっかり用意したいと思いました。それによって、彼らも“翼”を持つことができたのではないかと感じています。

―とはいえ、撮影中に問題が起きたことも多かったのではないでしょうか?
監督 確かに、演者が翌日来ないかもしれないといった我々ではコントロールできない部分でのリスクはつねに負い続けていた作品だったと思います。というのも、戸籍や証明書を持っていないような人も多かったので。
実際、ゼインを助けるエチオピア移民のラヒルを演じた女性が、拘束されたシーンを撮ったあとに逮捕されてしまったことがありました。そのときは、ラヒルの子ども役を演じていた赤ちゃんの両親も逮捕されてしまい、その先がどうなるのかわからない状況に陥ってしまったこともあったほどです。
この方法でしか作ることができなかった作品

―そんななかで、どのようにして作品を完成まで導いていったのでしょうか?
監督 そもそも大きなリスクがある作品だとわかっていたので、私たちは完全にインディペンデントで製作することにしていました。私の夫であるハーレドもプロデューサーとして入っていますが、ここまで大変だと知っていたら彼もやらなかったかもしれないですね……。
まずは製作する場所も何もないところからスタートしなければいけなかったのですが、予定していた刑務所が閉鎖してしまうことになったり、せっかく見つけた子役たちもいま撮らなければ大きくなってしまうこともあったりしたので、すぐに撮影を開始しなければいけませんでした。
ただ、子どもも大人も演技についてはまったくの未経験。「アクション!」といって求めているものをすぐに演じてくれるわけではなかったので、彼らとも時間を過ごす必要がありました。製作期間中はカメラマンも編集者もみな同じアパートで作業してくれました。編集などを含め完成までに2年。本当に小さな現場でしたが、これ以外の方法でこの作品を作ることはできなかったと思います。

―撮影自体も困難が伴ったと思いますが、身の危険を感じることはありませんでしたか?
監督 もちろん、とても危険な場所ではありましたが、危害を加えられるというよりも、公害のような環境の問題のほうが大きいと感じました。というのも、貧困地域では雨が降ると、下水から水が溢れてきて、水浸しになってしまうからです。
そのため、不衛生で臭いもすごいし、空気さえも汚染されているのがわかるほどだったので、私も熱を出してしまったことありました。しかも、当時私は2人目の子どもを出産したばかり。撮影の合間には授乳のために家に帰らなければいけなかったので大変でしたが、どんなに危険な状況でも、私たちは大きな目的があったし、使命感もあったので、それが続ける強さに繋がっていたと思っています。
―まさに意志を貫く強さを監督から感じます。それを支えているものは何ですか?
監督 彼らは同じ状況に置かれたままなのに、「私は家族と幸せになっていいんだろうか」という罪悪感をいまだ抱いている部分もあり、心理的な負荷はまだ乗り越えられてはいません。「自分にはやらなければいけないミッションがあるんだ」という感覚があるからだと思います。
人が存在しているのには、それぞれに理由があると考えています。私は恵まれていることに何かを変えることができるかもしれない自分なりの貢献方法や理由を見つけることができたと思っています。
「ひとりひとりが物事を変えることができる」という考え方は甘いと言われるかもしれませんが、私は心からみなが自分なりにできることがあると信じているのです。その変化というものは、たとえ大きくなくても、他人の人生や命に影響を与えられることができると思っています。そんなふうに自分の目標や夢、そして存在理由を感じられることが、私にとっては毎朝起きる力になっているのです。
日本でも同じ思いを感じている人はいるはず

―それでは最後に、これから観る方に向けてメッセージをお願いします。
監督 状況は違っていても、同じような思いをしているような人は世界中にいるはずなので、ただ遠い国の話という風には感じないと思っています。実際、こういった問題はレバノンだけではなく、アメリカでも子どもの7人に1人のはお腹を空かせているような状況ですし、コミュニティのなかで端に追いやられてつらい思いをしている人は文化や国に関係なく、日本にもいるはずです。
だからこそ、きっとみなさんの心に触れる作品だと思っていますし、人類はこのまま子どもたちに対する不公平さに目をつぶっていくことはできないと、私は信じています。
目をそらしてはいけない現実がそこにはある

それぞれの人物が放つ存在感と物語の持つ強さに圧倒され、激しく心を揺さぶられる本作。現代社会が抱える問題を描きつつ、「自分にできることは何か」「生きるとは」「愛されるとは」といった普遍的な思いがあなたのなかにも生まれるはず。映画の持つ力を目の当たりにすることができるいま観るべき1本です。
胸を引き裂く予告編はこちら!
作品情報
『存在のない子供たち』
7月20日(土)よりシネスイッチ銀座、ヒューマントラストシネマ渋谷、新宿武蔵野館ほか全国公開
配給:キノフィルムズ
©2018MoozFilms/©Fares Sokhon
http://sonzai-movie.jp/