実は略語でした! 「おせち」、もともとの名は何でしょう?
【実は略語】vol. 10
「おせち」って、何の略?
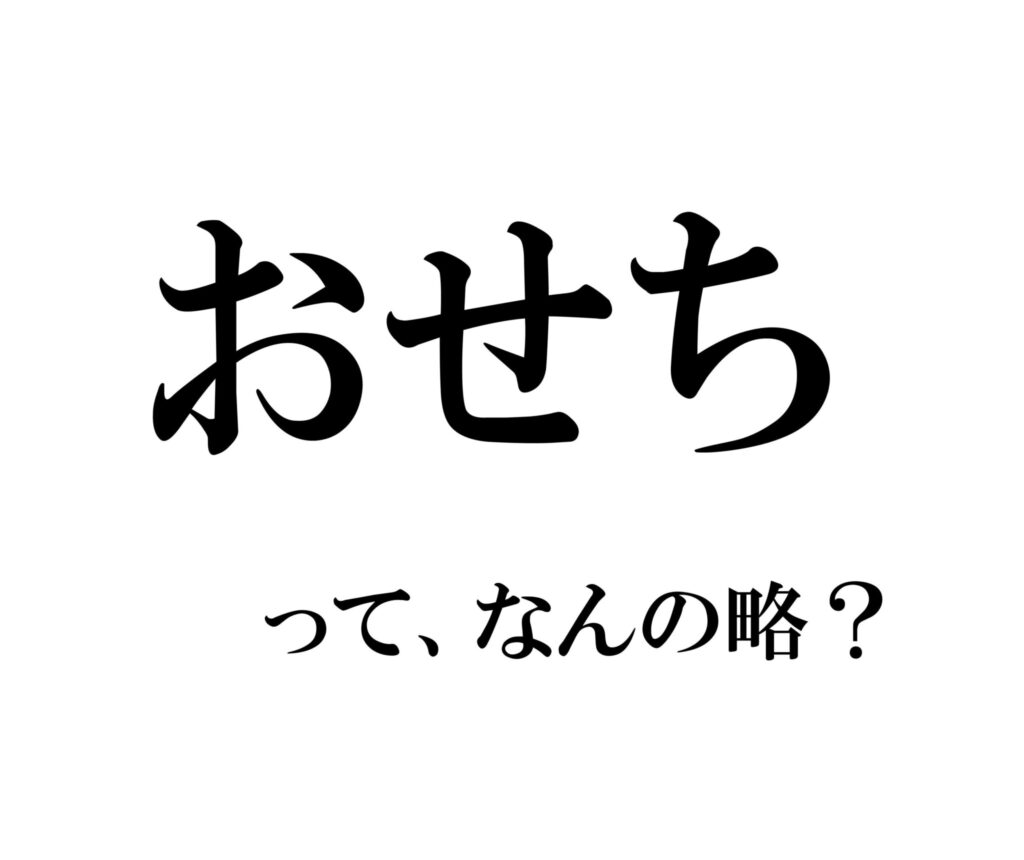
お正月が近づいてくると、スーパーの店先や広告などで目にする機会がグッと増えてくる言葉「おせち」。栗きんとんや数の子、ごまめなどが店に並ぶと、年末モードが一気に盛り上がります。
そんな日本の伝統料理である「おせち」も、実は略語。さて、いったい何の略でしょう?
おせち、もともとは…?
おせちは、漢字で書くと「御節」。「御」は接頭語で、節(せち)は節供(せちく)を略したものでした!
節供とは、季節の変わり目である節日(せちにち)に、神様に供える料理のこと。
元旦や端午、七夕などの節日のなかで、もっとも重要なのが元旦だったので、「節供」は次第に正月料理を指すようになりました。
おせちの起源は…?
では、おせちの起源はいつの時代か、わかりますか?
諸説ありますが、おせちの原型ができたのは、なんと弥生時代でした!
ぐるなびの記事『おせち料理の由来と歴史を知ろう』によると、縄文時代に稲作が中国から伝わったあと、弥生時代に「節」を季節の変わり目とする暦も伝来。「節」の日には、収穫を神様に感謝して「節供」というお供え物をする風習が生まれたそうです。
その後、奈良時代から平安時代になると、宮中行事として節日に「御節供(おせちく)」と呼ばれるお祝いの料理が振る舞われるようになります。
庶民も「おせち」を食べていた?
庶民に御節供の行事が広まったのは、江戸時代になってから。江戸幕府が、以下の五節供(ごせちく)を制定して祝日としたことから定着していきました。
・人日(じんじつ:1月7日)
・上巳(じょうし:3月3日)
・端午(たんご:5月5日)
・七夕(しちせき:7月7日)
・重陽(ちょうよう:9月9日)
ここでピンときた人もいるかと思います。五節供とは、五節句のこと。七草や雛祭り、子どもの日や七夕、菊祭りなど今でもおなじみの行事です。
広い意味では、端午の節句に食べる「ちまき」もおせち料理のひとつになるようですが、現代では正月料理だけが「おせち」とされています。
おせちに込められた願いは…
また、おせちの各料理に意味が込められるようになったのは、江戸時代後期です。
例えば、栗きんとんは黄金色に見えるので豊作や金運への願いが込められ、数の子は数が多いので子孫繫栄、昆布巻きは「喜ぶ」にかけられています。
おせちは略語でした!
おせちは「御節供(おせちく)」の略でした。その起源は弥生時代まで遡ることができ、2000年近い歴史がありました。
忙しい年末に、ゼロからおせち料理をつくるのは大変ですが、今はコンビニでも買える時代。つくらなくても、食べる習慣だけは続けたいですね。
意外な略語はまだまだあります。次回もお楽しみに!
参考資料
・『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)
・『世界大百科事典』(平凡社)
・おせち料理の由来と歴史を知ろう(ぐるすぐり/ぐるなび)https://gurusuguri.com/special/season/osechi/spcu-osechi_yurai/






