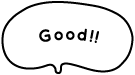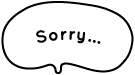志村 昌美
志村 昌美
「元恋人の2人を再会させることに怖さもあった」トラン・アン・ユン監督が語る名優たちの共演秘話
『ポトフ 美食家と料理人』

【映画、ときどき私】 vol. 623
〈食〉を追求し芸術にまで高めた美食家ドダンと、彼がひらめいたメニューを完璧に再現する料理人でパートナーでもあるウージェニー。2人が生み出した極上の料理は人々を驚かせ、類まれなる才能はヨーロッパ各国を熱狂させていた。あるとき、ユーラシア皇太子から晩餐会に招待されたドダンは、豪華なだけで論理もテーマもない大量の料理にうんざりする。
ドダンは〈食〉の真髄を示すべく、もっともシンプルな料理「ポトフ」で皇太子をもてなす計画をウージェニーに打ち明けるのだった。ところが、準備の最中にウージェニーが倒れてしまう。ドダンは人生初の挑戦として、すべて自分の手で作る渾身の料理で、愛するウージェニーを元気づけようとするのだが…。
「新たなグルメ映画の傑作が誕生した」と絶賛されている本作。そこで、完成までの裏側について、こちらの方にお話をうかがってきました。
トラン・アン・ユン監督

『青いパパイヤの香り』や『ノルウェイの森』などで知られ、多くの映画ファンを魅了してきたトラン・アン・ユン監督。今回は、料理にかける熱い思いや撮影時の忘れられないエピソード、そして日本の観客に伝えたいことなどについて、語っていただきました。
―6年前にananwebで取材させていただいた際、「フランス料理についての作品を考えている」とおっしゃっていて、それを実現されたわけですが、料理を題材にしたいと思ったきっかけは何ですか?
監督 料理に関してのプロジェクトというのは、アメリカや日本をはじめさまざまな国を舞台にした企画や食いしん坊で知られる小説家ジム・モリソンの映画など、いくつか話はありました。そのなかで、着地したのが本作でしたが、僕が一番やりたかったのは芸術を映像化すること。僕にとって料理というのは、具体性のある芸術だと思っています。
肉や野菜などを使って素晴らしい一品を完成させるのが料理ですが、それこそがまさにアートの縮図ではないかなと。そう感じていたこともあり、今回は料理という芸術に焦点を当てることにしました。フランス料理に決まったのは偶然なので、いまでも日本やほかの国の料理映画を撮りたい気持ちはあります。
正しいものより、ふさわしいものを探すのが大事

―以前の取材では、「もしプロジェクトが実現したら、死ぬまで料理のシリーズしか撮らないかもしれない」ともお話されていました。ということは、今後も料理をテーマにされるのでしょうか。
監督 この作品を終えた直後ということもあり、正直に言うといまは違うことをしたいと考えています。だから、映画監督の言うことなんて信じてはいけませんよ(笑)。監督というのは、そのときのフィーリングと合ったり、自分の感性が動くものを見つけたりすると、すぐそっちのほうに向かってしまうものですからね。
―気を付けます(笑)。また、料理については、ミシュラン三つ星シェフのピエール・ガニェールが完全監修ということですが、ご一緒されてみていかがでしたか?
監督 この作品では、料理の準備がとにかく大変だったので、彼の存在は本当に必要不可欠でした。彼はシナリオに書かれていたすべての料理を再現してくれましたし、俳優たちは調理をする際の手やカラダの動かし方を彼から学んでいます。
そして、「自分が一番ふさわしいと思うものを見つけてさえいれば、それがおいしいものに繋がっている」という彼の考え方は、僕と呼応していると感じました。僕自身も「正しいものを探しに行く」というよりも、「ここにふさわしいものを見つければ、おのずと美しいものができあがる」という考え方ですからね。
本作では、2つの官能性を合わせて表現している

―本作は料理映画ではありますが、官能性を持って表現されているのがトラン・アン・ユン監督ならではだと感じました。そのあたりはどのような意識をされていましたか?
監督 映画というのは、アイデアや言葉を具現化するものだと思っているので、この映画では料理が持つ“肉体性”というのを描き出したいと考えていました。本作で感じられる官能性については、俳優たちの内から湧き出るものとカメラワークが重要で、それらが交わり合って1つのハーモニーとなっています。
僕が人間の営みのなかでもっとも官能的な行為と考えているのは、食べることとセックスをすること。劇中でわかりやすい例を挙げるなら、洋ナシのコンポートが登場するシーンのあとに、まるで洋ナシのようなフォルムをしているウージェニーの裸体を映しています。そんなふうに、2つの官能性を映像で表現しました。
―なるほど。調理過程の撮影はワンカットで行い、カメラは1台しか使われなかったというのも驚きです。
監督 みなさんからすると、とても自由で優雅な感じに見えるかもしれませんが、今回のカメラワークは非常に複雑でした。事前に作り込まず、俳優たちに好きなように動いてもらうなかで一番いいタイミングをカメラに捉えようとしていたので、そこは大変だったかなと。
でも、余白を残すからこそ、そこに発見や即興の余地がありますし、しなやかさも生まれたと思っています。撮影中は、ステディカムを持ったカメラマンの後ろで腰を持ち、僕が誘導していく形を取りました。
自分と妻との関係性が反映されている

―官能性を意識されていたとはいえ、監督の過去作で描かれているエロティックさとは異なるような印象を受けましたが、ご自身のなかでもそのあたりの感覚に変化はありますか?
監督 下手すると退屈に見えてしまうので、そもそも官能性を映像化するのは非常に難しいことなんですよ。しかも今回は、人物の精神性や魂の美しさを含めたうえで官能性を出さなければいけなかったので。
劇中にドダンがウージェニーに対して「君が食べているところを見ていてもいい?」というシーンがありますが、これはフレーズ自体がとてもエロティックですよね。そんなふうに、本作では2人がお互いの話に耳を傾け、穏やかな視線を向け合うなかで生まれる官能性を描きました。とても繊細な感覚ですが、みなさんにも感じ取っていただけると思っています。
―本作でドダンが素材を料理に変換していく姿は、映画監督の仕事にも通じるところがあるのではないかなと。主人公にご自身を重ねている部分はありましたか?
監督 恋愛の要素がない原作にラブストーリーを加えたので、そういう意味では僕と妻の関係を料理という場を借りて映画化したと言えるかもしれませんね。僕たちの夫婦生活も長く続いており、すでに37年になりますが、いまでも愛し合い、お互いを尊敬し合っていますから。
―トラン・ヌー・イェン・ケーさんといえば、監督にとって公私ともに長年のパートナー。本作でもアートディレクションと衣装を担当されているので、まさにドダンとウージェニーのような関係ですよね。
監督 それに私の妻は、ウージェニーと似ているところがあるんですよ。なぜかというと、僕は彼女にすごく優しいのに、彼女は僕にちょっとつれないところがありますからね(笑)。そういう部分にも僕たちの関係性が投影されていると思います。
怖さもあったが、偉大な俳優に心配はいらなかった

―また、キャスティングで話題となっているのは、主演のブノワ・マジメルさんとジュリエット・ビノシュさんが私生活でかつて恋人同士であったこと。そういうおふたりだからこそ、できたこともありましたか?
監督 彼らはケンカ別れをしたようなところがあったので、本作で再会させることに対して、実はちょっと怖さもあったんです…。でも、彼らは偉大な俳優ですからね。実際は何の心配もいりませんでした。
ただ、印象に残っているのは、2人が野原を歩いているシーンを撮影したときのこと。ジュリエットが振り向いて、ブノワにキスをしたんです。すると、「カット」がかかった瞬間に、ブノワが僕のところにきて「シナリオに書かれていなかったけど、ジュリエットにキスをしろって言ったんですか?」と抗議されました(笑)。
―裏でそんなことがあったとは驚きですが、どのように対応されたんでしょうか。
監督 「僕は俳優じゃないからジュリエットの気持ちはわからないけど、彼女が『そのほうが美しい』と感じてキスをしたんだと思うよ」と答えました。撮影のなかでも最後のシーンだったので、彼女にとってはキスをするラストチャンスだと思ったのかもしれないですね(笑)。
―事前におふたりの過去についてはご存じで怖さも感じていたにもかかわらず、それでもこの2人に決めたのはなぜですか?
監督 まず、ジュリエットはウージェニーの役柄に見事にマッチングしている俳優だと思ったからです。そして、少し脆弱で女性的な感じがありつつ、オープンな部分も持ち合わせているブノワもドダンには完璧だなと。なので、最初から2人で行きたいと決めていました。
日本料理は、素材に対するリスペクトが素晴らしい

―そんなおふたりが劇中で交わす言葉がとても詩的でロマンチックでしたが、脚本を執筆している際や演出時に意識されていたことはありますか?
監督 何気ない会話でも、彼らの気持ちや関係性が一瞬にしてわかるように作り上げることを大切にしていました。あと、映画を作っているときに、僕がつねに思いをはせていたのは日本のみなさんのこと。なぜなら、日本人は思っていることや自分の感情についてあまり言えない印象があるからです。
スピリチュアルな言葉もわりと簡単に口に出せるフランス人たちを見ていて、対極にいる日本の方々のことを考えていましたが、みなさんも思っていることは言ったほうがいいですよ!
―ぜひ、見習いたいところです。ちなみに、「納豆以外イナゴも食べられるくらい日本食は全部大好き」とおっしゃっていましたが、監督が思う日本食の魅力についてもお聞かせください。
監督 まずは、素材の良さがありますが、素材が持つ風味を変えることなくリスペクトしているところも素晴らしいと思っています。それに比べて欧米の料理は、素材を変換させてより濃厚なものにしようとすることが多いですからね。そんなふうに、感動を生み出す方向性がまったく違うように感じています。
―それでは最後に、日本の観客に向けてメッセージをお願いします。
監督 映画館のなかで、“食べる喜び”というのを感じていただけたらいいなと。みなさんに受け取っていただけることを心から願っています。
美食と愛の奥深さを堪能する

実り豊かな人生に欠かすことのできない「食」と「愛」に対する情熱が、観る者の五感を刺激する本作。官能的で美しい世界観に、誰もが引き込まれてしまう珠玉の1本です。
取材、文・志村昌美
釘付けになる予告編はこちら!
作品情報
『ポトフ 美食家と料理人』
12月15日(金)Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、シネスイッチ銀座、新宿武蔵野館ほか全国順次公開
配給:ギャガ
https://gaga.ne.jp/pot-au-feu/
(c)Carole-Bethuel(c)2023 CURIOSA FILMS- GAUMONT - FRANCE 2 CINEMA(c)Stéphanie Branchu(c)2023 CURIOSA FILMS- GAUMONT - FRANCE 2 CINEMA(c)2023 CURIOSA FILMS- GAUMONT - FRANCE 2 CINEMA