『ボクたちはみんな大人になれなかった』×『新聞記者』両監督が語る“配信の可能性”
映画とはまったく違う『新聞記者』にしたかった。
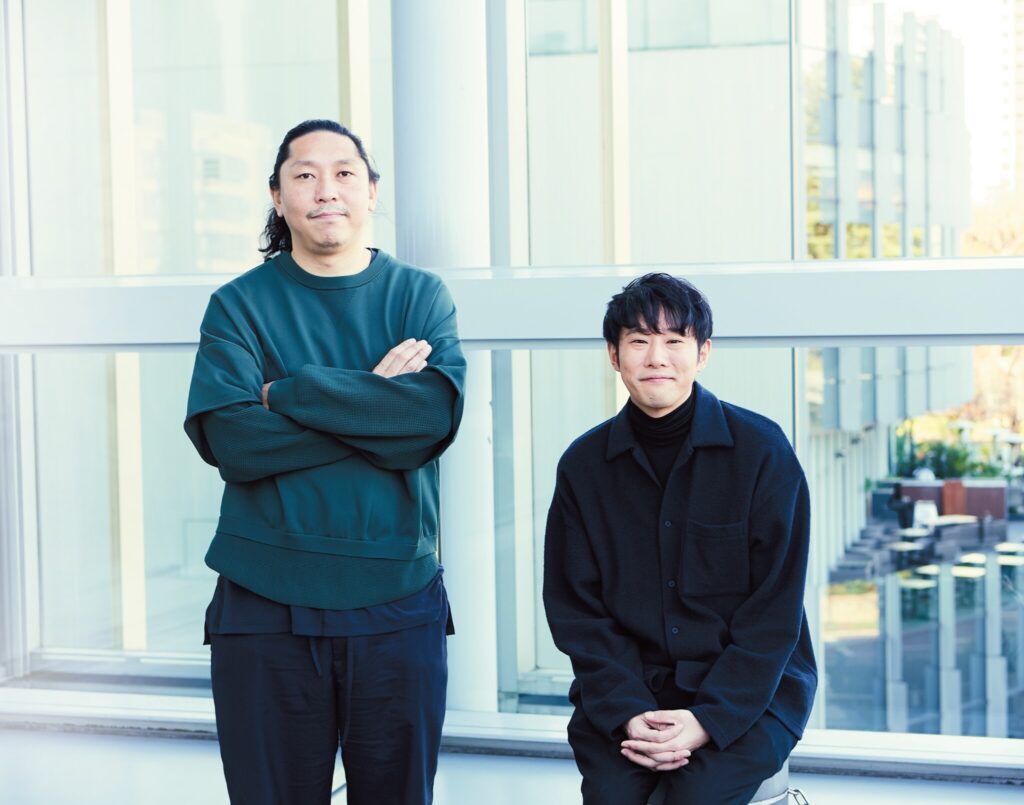
森義仁:Netflix版『新聞記者』、面白かったです! すでに映画として自身が製作した作品をリブートすることに対して、藤井さんはどう思いましたか。
藤井道人:正直、最初はやりたくなかったです(笑)。でも、プロデューサーの河村(光庸)さんにとって、『新聞記者』は人生を懸けたコンテンツ。Netflixの坂本(和隆)さんも立ち上げの頃からずっと仕事をしている仲。その二人から頼まれたらやるしかないなと。ただ、映画とは別物にしたいというオーダーはさせてもらって。その結果生まれたのが亮(横浜流星)というキャラクターでした。
森:あの政治に関心のない就活生という立ち位置はすごくいいなと思いました。
藤井:映画版のときも政治に興味がない人でも感情移入できるように工夫はしたんですけど、やっぱりまだ遠いという感覚は否めなくて。ちゃんと自分の視点を入れたいと思ったんです。そこで、記者側でも官僚側でもない第三の視点として、亮を新たに追加しました。
森:だからでしょうか。今回はより、ヒューマンドラマに引き込まれた感じがしました。
藤井:映画版は、記者側と権力者側の二項対立なんですよね。それがセンセーショナルではあったんですけど、Netflixなら45分×6話という長尺で描ける。だったら、もっと徹底的に人を描いて、群像劇として掘り下げたいという気持ちはありました。
森:新しい物語の中で、田中哲司さんの役は映画と共通でしたね。
藤井:田中さん演じる多田は、内閣情報調査室のシンボル。そこはブラさなくてもいいと思ったのと、あんな怖い顔した人、田中さん以外できないだろうと(笑)。
森:こういう社会的なテーマを持った作品って大変じゃないですか。自分がやるとしたらと考えましたけど、難しいなと思いましたもん。
藤井:だからこそ、善悪を断定しないように意識はしていました。取材でお話を聞いても、記者の方も内調の方も純粋に自分の仕事に取り組んでいるんですよね。だから両者にちゃんとリスペクトを払いたかった。この作品が描いているのは、いろんな人たちがもっと自分ごととして世の中の問題を考えられる社会。そうした明るい問いかけで終わりたくて、映画版とはまた違うストーリーラインにしました。
スマホで観る面白さと“街”で観る面白さを体感して。
藤井:『ボクたちは~』は、やっぱり劇場公開とNetflixでの配信を同時に行うという試みが新しいですよね。僕は配信が始まってすぐスマホで観たんですよ。そのあと、テレビでも観たんですけど、意外とスマホの方が没入できた感覚があって。きっとこの物語が佐藤(森山未來)の内なる対話だからこそ、スマホの方がよりパーソナルな感じがしたんだと思います。そんなふうに映画館で観るのと、自宅で観るのとでは、体験性が違う。その両方のニーズに応えるのは、今の時代を鑑みれば自然な気がします。
森:藤井さんのおっしゃる通りで、それぞれ楽しみ方が違うし、それを受け手が選べるのは、今の時代らしくていいなと。
藤井:音楽や背景、ポケベルなどの小道具で徹底して’90年代を描いていますよね。劇中で佐藤とかおり(伊藤沙莉)がドライブをするシーンがあるじゃないですか。そこで小沢健二さんの曲が立て続けに流れるんですけど、あれはギークな人じゃないとできない選曲だなと思って。あれは森さんが?
森:そうですね。あそこで一気にあの時代に帰らせたかったというのがあって。小沢健二さんの『犬は吠えるがキャラバンは進む』というアルバムを曲順にどんどんかけていきました。今回、時代をどう描くかが大きなポイントで。本来ならTSUTAYAができる前、まだ東海銀行だった頃の渋谷のスクランブル交差点をバンッ! と見せたりするのが王道なんでしょうけど、いろいろ事情もあって、そうはいかず。逆にラフォーレ原宿とか、渋谷のタワーレコードとか、主人公のパーソナルな場所をおさめていくことで、二人の足跡を辿れるように切り替えました。
藤井:変に時代劇を撮るより、みんなの記憶にある「過去」の街を描くのは大変ですよね。画という意味では、現代を映す中で出てくる無人の新宿の街も印象的でした。
森:あれはちょうど’21年1月の緊急事態宣言下に撮影しました。だから偶然の産物ではあるんですけど、確かに画力のあるものが撮れましたね。
藤井:あのコロナ禍の街並みが、主人公の孤独感と重なって見えたんですよね。コロナを作品に取り入れるかどうかは今みんなが葛藤するところだと思うんですけど、こういう使い方があるんだと羨ましくなりました。
森:『ボクたちは~』では一貫してコミュニケーションを描いていて。時代とともにツールが変わる中、コロナによって突然分断され、佐藤が完全にひとりぼっちになった。その感じが作品にマッチしている気がして。脚本を直していたのは、’20年春の最初の緊急事態宣言の時期でしたが、コロナを物語に入れようと決めました。
藤井:この作品、1995年当時に青春を過ごした人が、当時から付き合っていた今の夫なり妻なりを誘って渋谷の映画館まで観に行ったらエモいでしょうね(笑)。そうやって多様な楽しみ方ができるのはいいなと思います。
僕たちの世代で面白いものをつくりたい。

森:藤井さんは配信というプラットフォームで作品をつくるにあたって意識したことはありましたか。
藤井:一気見させる感覚はすごく大事にしました。今日は3話までと決めていたのに、3話のラストまで観たら、ここで終われるかという気持ちになる。僕自身、その感覚に踊らされるのが好きなので、『新聞記者』もそんなふうに楽しんでもらえたらなと。
森:以前やった『恋のツキ』はテレ東で放送終了後、Netflixで全話一挙配信されることがあらかじめ決まっていたんですね。だから、僕もお客さんを離さない仕掛けづくりには知恵を絞って。毎回いかにクリフハンガー的なラストで次につなげられるかという挑戦をしていました。
藤井:僕たちクリエイターにとって、いま配信作品をやる醍醐味は、海外の人たちに観てもらえること。映画ならカンヌやベネチアの映画祭に出品するという方法がありますが、そこで目にとまり上映が決まる可能性は高くはない。映画祭以外で、出会ったことのない国の人たちに観てもらえるチャンスがあることは、すごく魅力ですね。
森:小学校の同級生がオランダに住んでいて。「『ボクたちは~』を観たよ」と30年ぶりに連絡が来ました。海外の方からDMで感想をいただけたのも、配信だからこそ。世界に届いているんだと実感できて、うれしかったです。
藤井:結局何をつくるかは、テレビであろうと映画であろうと配信であろうと、自分たち次第なんですよね。それぞれ制約との戦いはありますけど、自分たちが信じたことを貫き通せば、ちゃんといいものがつくれると思う。
森:その中でいま面白いことが起きているとワクワクさせてくれる場が配信なのかなと。広告を見ても勢いを感じます。
藤井:あとは、スケールの大きい作品を配信でやってみたい。オリジナルで、長い年月をかけてシリーズものとかつくれたら面白そう。個人的には観る側として、『ストレンジャー・シングス』の最新シリーズが今から楽しみなので(笑)。
森:僕は『全裸監督』的な“キャッチーな大作”だけを配信するというイメージも覆していけたらと思います。『ボクたちは~』みたいな私小説風の作品は、最初は配信には合わないかなと思ったけど、ボーダーレスな作品が集まる場になるといいなと思うし、僕たちの世代でどんどん面白いものを生み出していきたいですね。

Netflixオリジナルシリーズ『新聞記者』 異端の新聞記者・松田杏奈が公文書改ざん事件の真相を追う中、問題の渦中に置かれた官僚、その家族など様々な人間関係が絡み合っていく。Netflixで’22年1月13日より全世界同時独占配信。出演/米倉涼子、綾野剛ほか

『ボクたちはみんな大人になれなかった』 46歳のボクは、いくつかのほろ苦い再会をきっかけに1995年の“あの頃”を思い出す…。時代を彩ったカルチャーとともに忘れられない恋を描いた青春映画。Netflixで配信中。出演/森山未來、伊藤沙莉ほか
森 義仁さん(一枚目写真・左) 1982年生まれ、三重県出身。日本映画学校(現日本映画大学)卒業。MV監督、CMディレクターなどを経て2018年にテレビ東京とNetflix共同制作のドラマ『恋のツキ』を監督。映画監督作品としては本作が初。
藤井道人さん(一枚目写真・右) 1986年生まれ、東京都出身。日本大学芸術学部卒業。『オー!ファーザー』(2014年)でデビュー。近作に『ヤクザと家族 The Family』(’21年)、ドラマ『アバランチ』(フジテレビ系)など。映画『余命10年』の公開を控える。
藤井さん・タートルネック¥13,200(Iroquois TEL:03・3791・5033) パンツ¥13,500(COS/COS銀座店 TEL:03・3538・3360)
※『anan』2021年12月29日‐2022年1月5日合併号より。写真・小笠原真紀 スタイリスト・DAN(藤井さん) ヘア&メイク・酒井真弓(藤井さん) 取材、文・横川良明
(by anan編集部)






