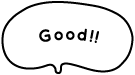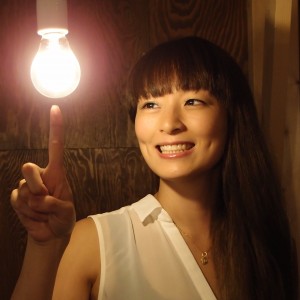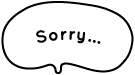志村 昌美
志村 昌美
「日本の方の仕事は正確でした」香港・日本の共同製作で話題の監督が言及
『Blue Island 憂鬱之島』

【映画、ときどき私】 vol. 503
一国二制度が踏みにじられ、自由が失われつつある香港。2014年に起きた民主化要求デモ「雨傘運動」のあと、やるせない思いが憂うつさとなって覆っていた。そんななか、異なる時代を生きた実在の3人が若者たちに語るのは、文化大革命や六七暴動、天安門事件といった世界を震撼させた事件の記憶。激動の歴史を乗り越え、自由を守るために闘ってきた彼らが、時代を超えて現代の人々に伝えたい思いとは……。
今回、香港と日本による共同製作によって完成した本作。北米最大のドキュメンタリー映画祭「Hot Docs 2022」では最高賞を受賞するなど、大きな注目を集めています。そこで、こちらの方にお話をうかがってきました。
チャン・ジーウン監督

2016年に発表した長編ドキュメンタリー第 1 作『乱世備忘 僕らの雨傘運動』では、山形国際ドキュメンタリー映画祭で小川紳介賞を受賞したのをはじめ、台北金馬奨で最優秀ドキュメンタリー賞にノミネートされるなど、高い評価を得ているチャン監督。本作を制作するに至った思いや撮影時の苦労、日本との共同作業で感じたことなどについて語っていただきました。
―本作の構想は、いつ頃から監督のなかにあったのでしょうか。
監督 2014年の雨傘運動も終わり、少し落ち着き始めていた2017年頃に本作のことを考えるようになりました。特に、前作『乱世備忘 僕らの雨傘運動』のラストシーンで、主人公の男性に「自分の将来はどうなると思いますか?」とたずねているところがあったので、その続きになるような作品ができたらいいなと。
なかでも、彼らと同じような運動に参加し、似た経験をしてきた年配の方々がどうなったのかを見せることで、若い世代の人たちに、これからの20年、30年、さらに50年後の未来について考えてほしいと思いました。
―本作は通常のドキュメンタリーとは違い、再現シーンでは当事者たちを現代の若者に演じさせている構成も非常に印象的でした。そのようにした意図についても、お聞かせください。
監督 2019年に大規模な反政府デモが起きたので、ただ歴史的な話を入れるのではなく、その運動に参加した若者たちの困難も描きたいと思うようになりました。なぜなら、本作に出演している若者たちは、裁判を控えていて、刑務所に入るかもしれない不安を抱えていたり、香港を離れることも考えたりしているような状況だったからです。
撮影に関していうと、70~80年代の衣装や美術の準備をすることも、俳優ではない彼らにパフォーマンスしてもらうことも、とても難しくて大変でした。とはいえ、それによって映画が豊かになっていくような感じはあったと思います。
一人一人の意志と精神を引き継ぎたい

―いっぽうで彼らは政府に目をつけられているような立場に置かれている状況でもあるので、こういった映画に参加するリスクなどもあったのではないかと想像してしまうのですが……。
監督 僕自身も、彼らの安全に関してはいろいろと考慮しました。ただ、2019年のデモが終わったあと、彼らが過ごしていたのは何もできない状態の日々。それだけに、「何かやりたい」という思いからこの作品に参加してくれた人がほとんどでした。
もちろんリスクも考えなければいけなかったので、どこまでできるかはそれぞれと相談しながらでしたが、できるだけみんなの思いを尊重しています。今回も日本にこの作品を持ってくることで、彼らに影響を与えてしまうのではないかという心配もありました。でも、いまは一人一人の意志と精神を引き継ぎたいという思いです。
―監督自身が本作を制作するうえで、当局から制限されたり、圧力をかけられたりしたことはなかったですか?
監督 僕が唯一残念だと思っているのは、香港で上映ができないこと。どこでもいいから上映したいと考えていましたが、2020年に反政府的な動きをする人々を取り締まる香港国家安全維持法、そして2021年に映画の検閲を強化する条例が改正されたことによって実現できなくなりました。日本以外にもアメリカやカナダなどで上映されますが、香港の映画を撮ったにも関わらず香港の人々に観てもらえないのは悲しいことですね。
あとは、将来的な資金面において、香港からもらうことは難しいので、今後も海外に頼ることになるのではないかと考えています。ただ、いまの香港はさまざまな変化をしているときでもありますし、難しければ難しいほど撮る意義があるということでもあるので、今後も香港のドキュメンタリーを撮っていきたいです。
香港人のアイデンティティは、つねに変化し続けている

―香港の方々は、“香港人のアイデンティティ”をつねに追求しているところがあり、そこが日本人とは大きな違いだとは思います。監督にとって、香港人としてのアイデンティティとは何ですか?
監督 確かに、日本では日本人のアイデンティティについて普段から考えることはあまりないかもしれませんが、香港といえば、1997年までイギリスの植民地で、そのあと中国に返還されたので、僕たちからすると別の植民地に移ったような感覚。
そのため、香港のなかでも、自分のことを「中国の香港人だ」という人がいたり、「イギリスの香港人だ」という人がいたり、「どちらでもないただの香港人だ」という人がいたり、本当にいろいろです。しかも、僕も含めた香港人はみな流動的なところがあるので、今日思っていたことと、明日思うことが違う場合もあるほど。今回の撮影中に、僕自身もその答えを模索しようと考えていましたが、いまだに結論には達していないので、香港人のアイデンティティはつねに変化しているものだと感じています。
―なるほど。また、今回は3世代にわたる方々に取材をされていますが、上の世代の方と話をしてみて、印象に残っていることはありましたか?
監督 先輩たちが思う香港といまの香港が全然違うので、こういう考え方もあるのかと、いろんな気づきはありました。そのほかに興味深いと感じたのは、彼らが経験してきた天安門事件や六七暴動などの運動というのは、短くて1日、長くても数か月くらいのものでしたが、そんな短期間だったにもかかわらず、いまでも彼らの人生に大きな影響を与えていること。
そういった運動をきっかけに弁護士になった人もいましたが、彼らはいまでも香港人のために何かしたいという姿勢を崩していないですし、誰かのためになることを考え続けているのです。運動から何十年経っても引きずってしまうほど、当事者にとっては一生忘れられないほどの出来事だったのだと改めて感じましたし、そんな彼らの姿からは学ぶこともありました。
これからの香港は、もっと暗い色になる可能性もある

―タイトルの「Blue」には悲しみや落胆、そして香港が感じている憂うつを表しているということですが、今後の香港にはどんな色に変わってほしいと願っていますか?
監督 僕は毎回作品には色をつけようと思っているので、前作では黄色、そして今回は青色を使いましたが、正直に言うと、これからの香港はもっと暗い色になる可能性があるのではないかと感じています。
次回作では黒を使おうかと考えていますが、黒というのはいろんな色が混ざり合って出来上がった色でもありますからね。黒のなかにも、鮮やかな色も入れられたらと思っています。
―これまで何度か日本にはいらっしゃったことがあるそうですが、日本での思い出といえば?
監督 今回が5回目の来日ですが、一番印象に残っているのは、山形国際ドキュメンタリー映画祭で賞をいただいたこと。どうしても仕事の思い出ばかりではありますが、いろんなところをブラブラしてラーメンを食べたり、お寿司を食べたり、買い物なども楽しんでいます。
―ちなみに、本作は日本との共同製作となりましたが、日本人と仕事をしてみた印象についても教えてください。
監督 今回は、「なぜ香港の若者たちはこんなに政治に興味があるのか」というところに興味を持っていただき、協力を申し出てくださったことで合作となりました。日本の方は時間に正確で、仕事もすごく的確。おかげで、いろんなことが本当にスムーズに進みました。
香港もそこまでルーズではありませんが、適当なところもあるので、そこは日本と違うところかなと。ちなみに、仕事では大丈夫でも、香港の人たちはプライベートでは基本的に時間に遅れる人が多いですよ(笑)。
―それでは最後に、日本の観客にメッセージをお願いします。
監督 香港だけでなく、いまの世界が共通して抱えている問題や人々の思いというのが、日本のみなさんにもわかりやすく見ていただけると思っています。あとは、ジェネレーションの違いも見せているので、それがどのようにつながっているのかも感じていただけたらいいなと。
香港と日本というのは、遠そうで近い場所でもあるので、いまの香港の若者たちがどんな困難に見舞われ、何に苦戦しているのかといったことを見て、みなさんにも考えていただきたいです。
過去を知ることで、未来を考える!

住む場所は違っていても、激動の時代を生きた人々から学ぶべきこと、そして同じ時代を生きる若者たちがどんな思いを抱えながら闘っているのかを知ることができる本作。それによって、自分の置かれている環境や生き方を改めて見直す機会を与えられるはずです。
取材、文・志村昌美
心を揺さぶられる予告編はこちら!
作品情報
『Blue Island 憂鬱之島』
7月16日(土)より、渋谷のユーロスペースほか全国順次公開
配給:太秦
https://blueisland-movie.com/
️©2022Blue Island project