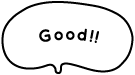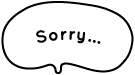志村 昌美
志村 昌美
両親の死と直面。映画『悲しみに、こんにちは』が描く少女の再生物語
スペインから届いた話題作『悲しみに、こんにちは』!

【映画、ときどき私】 vol. 179
母親を亡くし、ひとりになってしまった少女フリダ。バルセロナを離れ、カタルーニャの田舎に暮らす叔父夫婦のもとへと引っ越すこととなる。若い叔父と叔母、そしていとこのアナは、フリダを新しい家族として優しく迎えてくれるが、フリダはすべての事実を受け入れることができないまま。それは、フリダにとって “特別な夏” の始まりとなるのだった……。

さまざまな困難と向き合いながらも、少女が成長していく瞬間を見事に切り取った本作。今回は、特別な思いを抱きながらこの作品を制作したこちらの方にお話を聞いてきました。それは……。
カルラ・シモン監督!

シモン監督にとっては、本作が長編デビュー作となりますが、アカデミー賞外国語映画賞のスペイン代表に選出されたのをはじめ、ベルリン国際映画祭でも新人監督賞に輝くなど、スペインの新星として注目を集めています。そこで、自身の体験を色濃く反映している作品に込めた思いや心境について語ってもらいました。
自伝的映画にした理由とは?

―主人公のフリダと同じく、監督もご両親をエイズで亡くされているということですが、自分の人生を題材にしようと思った理由を教えてください。
監督 まず今回私が重要視していたのは、子どもが死に直面するというテーマ。そこで、自分の経験のなかで実際に私がどういうふうに感じていたのか、というところを通して伝えるのが一番いいのではないかと思ったんです。というのも、子どもというのは、私たちが思っているよりも死について理解ができるもの。ただ、感情をうまくコントロールできないところがあるだけなので、今回はそういう複雑さについても描きたいと思いました。
あとは、そういうリアルな感情に加えて、スペインでエイズが蔓延していた当時の時代背景などもとらえたいという気持ちもあり、このようなストーリーにしたんです。
悲劇を乗り越えられたのは周囲の支えがあってこそ

―とはいえ、ご両親を亡くすというのは人生のなかでもつらい過去だと思うので、そこに向き合うことへの苦悩はなかったのでしょうか?
監督 映画化にあたっては、そういう思いや怖さはありませんでした。というのも、私がこの経験をしたのは6歳のとき。幸いなことに私を取り囲む環境は、必要であればいつでも話を聞いてくれるオープンなものだったので、脚本を書き始めたときにはすでにこの問題を乗り越えることができていたんです。
ただ、つらかったことは、小さかったこともあり、実際の母親を覚えていないこと。だから、思い出したくても思い出せず、自分のなかに母のイメージがないというのは、悲しいことだなとは思いました。

―映画の前半ではフリダの両親や病気については、説明をせずに描いていますが、そこには母親の記憶がないという監督の心境も反映されているのでしょうか?
監督 それよりも、私にとってはこの映画を母親の死後から始めるということのほうが大事でした。なぜなら、そこを境にフリダの新しい生活が始まっていくことを描きたかったからなんです。つまり、「喪失」という部分に重きを置くのではなく、「新しい生活への適応」という部分を見せたいと思いました。
それに、子どもというのはつらいことは忘れてしまうので、母が亡くなったことよりも、そのあとのことのほうがよく覚えているんです。だから、私にとって1993年の夏というのは喪に服していた寂しい時期というよりも、新しい家族に溶け込むために努力していた前向きな意味を持つ時期だったと思っています。ちなみに、エイズという単語を出さなかったのは、子どもの視点で物語を伝えたかったので、そういう手法を取ることにしたんです。
スペインが抱えていたエイズの問題とは?

―スペインでは80年代半ばから90年代の初頭にかけて、ドラッグの蔓延によってHIV感染者が増加。ヨーロッパでもエイズの発症率がもっとも高い国となっていたほど、大きな問題となっていたそうですが、そういう時代の雰囲気を実際にはどのように感じていましたか?
監督 子どもたちの間では、エイズに対する恐怖というのはあまりなかったように思います。それに、私は両親がエイズで亡くなったことを初めて知ったのは、12歳のときで、それまではまったく知りませんでした。
なぜ叔父と叔母が私に黙っていたかというと、幼い私がその事実を知ってしまったら、みんなに話してしまって、田舎中に広まってしまうと考えたからだと思います。そういう意味では、大人たちには恐怖心があったかもしれないですね。
それから、フリダがケガをして血を流すシーンでは、感染を警戒して周りが過剰な反応をしていますが、あれは実体験ではありません。映画のなかでは、そういったフィクションのエピソードをいくつか入れていますが、それは観客に「フリダの両親はエイズで死んでしまったんだ」というのを少しずつ知らせるためにしていることです。

―地元の方々はこの映画ではじめて監督のご両親のことを知ったそうですが、それに対して何か反響などはありましたか?
監督 私の知る限りでは、このことで悪いレッテルを貼ったり、問題にしているような人はいませんでした。私がその事実を知らされたときは、消化するまでに時間はかかりましたが、エイズについて詳しく知るために、叔父と叔母はお医者さんのところに私を連れて行ってくれて、理解する機会を与えてくれたんです。そのあと受け入れるまでに数か月かかりましたが、自分で納得してからは、親友や彼氏にも打ち明けていました。
私も多くのことを学びましたが、このことで一番変わったのは当時の彼氏。というのも彼はドラッグに憧れるようなタイプの子だったんですけど、私の両親の話を聞いてから、突然アンチドラッグになって、「ドラッグは絶対にやめなさい!」というくらいすごく厳しい人になったりもしたんですよ(笑)。
子どもたちが見せる圧巻の演技!

―この作品も観客に大きな影響を与える力があると感じましたが、そんな作品の力強さを担っているのは、フリダとアナを演じた2人の子役。本当に素晴らしかったので、どのように演出したのかを教えてください。
監督 今回は普通の小学校でキャスティングをしたので、フリダ役のライアとアナ役のパウラは子役としてはまったく訓練を受けていない子どもたちでした。起用を決めたポイントは、キャラクターと性格が似ていること。それから、遊んでいる最中に遊びのなかに入り込んでそれを真実だと思いこんでしまうようなところがある子であること、そして2人が自然な関係性でいられることでした。それが、彼女たちを選んだ大きな理由です。
それから、ライアに関しては、すごくいい子にも見えるし、すごく悪い子にも見える二面性のあるまなざしの持ち主だったので、それだけで撮りたいと思わせるところもありましたね。

―自然な関係性という言葉通り、まるでドキュメンタリーを見ているかのようなリアルなやりとりが映し出されていますが、どのようにして撮影を進めていきましたか?
監督 正確に言ってもらう必要があるセリフに関しては、私が脚本通りのセリフを何度も繰り返して、それを聞きながら覚えてもらうようにしました。ただ、それ以外の場面では、即興性や自由を優先。できるだけ彼女たち自身の言葉で話してもらうようにしています。
そんなふうに子役は脚本を読まずに撮影しましたが、脚本を読んでいる大人の俳優でも、セリフは丸暗記するのではなくて、できるだけ自分の言葉に変えて話してもらいました。そうすることで映画のなかにある自然体というものを見せたかったんです。実際、家族としての自然なふるまいができるように、キャストには2週間くらいずっと一緒にいてもらいながら、リハーサルにたっぷりと時間をかけるようにしました。
自身の経験があったからこそ生まれたラストシーン

―どのシーンも印象的でしたが、なかでもさまざまな思いのこもった涙をフリダが見せるラストシーンは秀逸でした。そこにはどんな思いを込めたのでしょうか?
監督 あのフリダの涙には、いろいろな感情が混ざり合っていると思うんですけど、まずは自分の居場所を見つけて、新しい家族に愛されていることを感じている幸せ。でも、そのいっぽうで、今後もこの生活が続いていくんだという悲しみでもあります。つまり、両親は本当に戻ってこないんだということを理解した瞬間ということです。
なぜ私がこのシーンをラストに決めたかというと、実は私は母が亡くなった日に泣くことができなくて、それがずっと「泣くべきだったのではないか」という罪悪感が心に残っていたからでした。でも、大人になってから、そういうことは起こりえるのだと知り、いまではその気持ちも変わっています。
ちなみに、編集の段階ではフリダが泣くバージョンと泣かないバージョの両方を試してみましたが、涙を見せるほうが彼女の感情が解放されて幸せなラストになるだろうと感じられたので、今回のようなシーンにしました。

―ananwebを読んでいる女性読者たちにも響くところの多い作品だと思うので、ひとことメッセージをお願いします。
監督 この映画は、非常にドラマティックなストーリーのように思うかもしれませんが、日常的なストーリーとして共感していただく部分も多いと思っています。なかでも、“生きる喜び” というものを見出してくれるはずです。
そして、当たり前だと思っている家族の温かさや「家族ともっと一緒にいたい」という思いをを改めて実感してもらえる作品になっているので、ぜひみなさんご覧ください。
どの瞬間も忘れられない!

スペインの美しい自然の景色を舞台に繰り広げられる珠玉の感動作。誰もが経験する思春期ならではの痛みは、何よりも自分を成長させてくれるはず。悲しみを乗り越えた先に待ち受ける “新しい自分” と出会ってみては?
心をつかまれる予告編はこちら!
作品情報
『悲しみに、こんにちは』
7月21日(土)より渋谷・ユーロスペース他、全国順次ロードショー!
配給:太秦、ノーム
ⓒ2015, SUMMER 1993
http://kana-shimi.com/
撮影協力:スペイン大使館