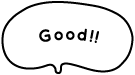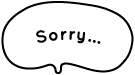志村 昌美
志村 昌美
ホロコーストを生き延びた男と少女…スキャンダラスな関係が生んだ希望
『この世界に残されて』

【映画、ときどき私】 vol. 350
ナチス・ドイツによって、約56万人ものユダヤ人が殺害されたと言われていたハンガリー。終戦後の1948年、ホロコーストを生き延びたものの、家族を失った16歳の少女クララは、ある日寡黙な医師アルドと出会う。言葉をかわすうちに、クララは彼の心に自分と同じ欠落を感じるようになり、父を慕うようにアルドになついていくのだった。
ホロコーストの犠牲者であったアルドもまた、クララを保護することで自分の人生を再び取り戻そうとする。ところが、ソ連がハンガリーで権力を握るようになっていくなか、世間は彼らに対してスキャンダラスな誤解を抱くようになっていくことに。“残された者”としてともに生きる2人の関係は、どうなってしまうのか……。
ハンガリー映画批評家賞3部門受賞をはじめ、さまざまな賞に輝いた本作。今回は、こちらの方に見どころなどをお話しいただきました。
バルナバーシュ・トート監督

短編を中心に手がけ、ハンガリーのみならず国外でも高く評価されてきたトート監督。本作は、監督にとって10年ぶりの長編2作目となる意欲作です。そこで、完成までの道のりや作品に込められた思いについて語っていただきました。
―まずは原作から映画化するにあたって、難しかったのはどのあたりでしょうか?
監督 今回、大きな挑戦だったのは、小説で細かく書かれている登場人物たちの過去や表情をどうやって映像で表現し、観客に伝えるかということでした。たとえば、これまでの作品であれば、収容所にいたことを知らせるために、わかりやすく列車に乗せるシーンがあったり、たくさんの亡骸を見せたりしていたと思いますが、この作品では収容所にいたことを示す数字が腕に刻まれているのを見せるだけで表しています。
そのほかに苦労したのは、キャラクターの数。小説は25年間という長い期間を描いた物語ということもあり、数多くの人物が登場しますが、映画では最初の6年だけに集中して、人物の数も10名前後に絞ることにしました。
―原作者のジュジャ・F・ヴァールコニさんとはもともと別のお仕事で知り合われたそうですが、映画化にあたって何か相談されたこともありましたか?
監督 この小説にはすべてが詳細に書かれていて、文句のつけどころのない出来だったので、特に説明やアドバイスを求める必要はありませんでした。ただ、僕が脚本を書いていたとき、実は彼女はあまり喜んではいなかったようで……。
―それは、なぜでしょうか?
監督 「まさに心理学者の人が書いた小説」という感じで、小説には人物の心の動きが事細かに書かれていました。それに比べると、脚本ではいろいろな情報がそぎ落とされているように見えたそうで、「これでは観客に理解してもらえないんじゃないだろうか?」と思われていたからです。もちろん、そういった意見も僕にとってはとても重要ではありました。
確信があったからこそ、自分の選択に迷いはなかった

―とはいえ、原作者の方がそういう状況で制作を続けるのは、気がかりだったのではないでしょうか?
監督 確かに、原作者が納得していない状態というのは怖かったですし、原作を傷つけてしまうのではないかという不安もありました。彼女にとっては、この作品が唯一の小説だったこともあって、ひとりっ子のように大切に思っていたから心配していたんだと思います。
そういったこともあり、キャスティングに関しては、彼女にもいいと言ってもらいたいと思っていたので、特にアルドとクララ関しては事前に映像を見てもらいました。2人ともすごく気に入ってもらえたので、それはよかったですね。
―そのなかで、監督として手ごたえを感じる瞬間もありましたか?
監督 今回の撮影期間は、19日間と非常に短かったですが、俳優たちの演技も相性もセリフもとてもよかったので、そのときに「これはいいものになるだろう」という確信を持つことができたように思います。それだけでなく、カメラマンも音楽もすべて素晴らしかったので、ひとつずつ形になっていくのを見守っていくような感じでした。だから僕自身としては、自分の選択に迷いがなかったというのが正直な気持ちですね。
その後、実際に完成した映画を観てもらったときに、俳優たちの演技や映像、音楽といったすべてが合わさることで彼女も理解してくれました。つまり、小説と脚本はずいぶん違うものなんだ、ということを。
ちなみに、彼女から「映画が完成して、もし気に入らなかったら、私のクレジットを入れずに、キャラクターの名前も変えてね」と言われたこともありました。でも、「撮影したあとにどうやって名前を変えたらいいんだろう? そんなことは不可能じゃないの?」と思っていたので、ハッピーエンドを迎えられてよかったです。いまでは友達になりました(笑)。
時代は違っても、心理的に通じる部分があった

―それは何よりです。では、映画を作る過程で、実際にホロコーストを生き延びた方々に取材をするような機会もあったのでしょうか?
監督 今年で100歳になるおばあさんに、俳優2人と会いに行ったりしたこともありました。ただ、これは全般的に言えることですが、ホロコーストで生き残った方というのは、実際にそこで何があったのかを語らない人がほとんど。前後の人生についてや収容所で起きた“いい話”については、話すことがあっても、それ以外のことを話さない方が多いということがわかりました。
そういった理由もあって、今回参考にしたのは、生き残った方のインタビュー映像や関連する本など。そこからイマジネーションを働かせて演出することを心がけました。クララに関しては、収容所を経験していない少女の設定ではありますが、ナチスの恐怖や病気、さらに家族を失う悲劇などを経験しています。つまり、収容所と同じくらい本当に厳しい状況で苦しみを味わっていた人たちがいたということです。
―作品を仕上げていくなかで、ほかの映画から影響を受けた部分はありましたか?
監督 まずは、1979年のハンガリー映画『コンフィデンス 信頼』がほぼ同じ時代だったので、最初に参考にしました。そのほか、『ファントム・スレッド』からは同時代の空気感やカメラワーク、衣装や色使いなどに関してインスパイアされています。
それからクララとアルドの2人の間にある感情的な関係性については、『ロスト・イン・トランスレーション』から。これは若い女性と年上の男性の間にある愛やコミュニケーションの“不可能さ”みたいなものを描くうえで影響を受けていると思います。あと、これも同じく少女と年上の男性を描いた作品として『レオン』。自分の感情を抑えている男性と思っていることをすぐに口にする女性という関係性ですね。時代は違っていても、心理的な部分では通じるところがあると思います。
編集の段階で深く心を揺さぶられてしまった

―興味深いですね。この作品と各国を回るなかで、観客たちの反応から「この作品がさまざまなトラウマに対する癒しになるかもしれない」と感じたそうですが、監督にとってもこの作品はそういう存在なっているのでしょうか?
監督 自分のことは考えたことはなかったけれど、美しい質問ですね。言われてみればそうかもしれません。ちょっとプロではないように聞こえてしまうかもしれませんが、作品を編集しているとき、まだ音もミックスしていないような段階で深く心を動かされてしまって、編集を担当しているスタッフと建物を出てすぐのところにある酒場で1杯飲まずにはいられなかったほどですから(笑)。
観客の方々が作品とそういう出会いをしてくれていること、そしてみなさんがそう感じてくださっていることはすごく幸せなことであり、うれしいことだと感じています。
―監督も映画によってトラウマを克服したような経験はありますか?
監督 恵まれていることに、いままであまり大きなトラウマというのはまだ経験していないですが、父との関係がうまく行っていない時期がありました。そこで、長編1作目では父と息子の話をコメディで描くことにしたんです。それを父と一緒に見ることによって、いいほうに向かっていったということはありました。
生きるうえで、何かに対して愛情を持てることが大事

―素敵なお話ですね。現代でも本作の登場人物たちのように孤独を抱えている人は多いので、彼らにシンパシーを感じる観客も多いと思います。そういう方々に監督から声をかけるとしたらどんな言葉をかけたいですか?
監督 孤独やトラウマを抱えているときに一番いいと思うのは、自分が面倒を見ることができる対象を見つけるということではないでしょうか。それは人でもペットでも何でもいいと僕は思っています。ちょっと説教っぽく聞こえてしまうかもしれませんが、そうすることで“生きる意味”を見つけることができると思うからです。
たとえば、僕は映画や音楽、本といった芸術に対して、まるで自分の子どものような愛を強く感じることがあります。以前、日本に関係するニュースで孤独を解消するためにロボットを使っているというような内容の話を見たことがありますが、それでもいいと思っているんです。
―つまり、自分以外に愛情を注げるものを見つけることが大事ということですね。
監督 そうですね。以前、スパイク・ ジョーンズ監督の映画『her 世界でひとつの彼女』にもありましたが、コンピューターに愛情を感じることも美しいと僕は考えています。“新しい種類の愛”とさえ言えるのではないでしょうか。僕はそれをジャッジしたり、笑ったりするつもりはありません。そんなふうに何かに対してそういう思いを持てるということ自体が大事だと思っているからです。
ちなみに、当初この映画のタイトルは別のものを考えていて、「誰かのために生きる」といった意味のあるものにしようかと考えていたほど。それこそが生き残るための方法のひとつなのです。
―それでは最後に、日本の観客へ向けてメッセージをお願いします。
監督 映画にすべての思いを込めているので、観ていただければわかると思いますが、それが文化や国を超えてみなさんに響くといいなと思っています。事前に、ホロコーストや政治的な問題が背景にある話だと難しく考えるのではなく、まずは純粋にご自身の心と目でこのキャラクターにフォーカスしてほしいです。実際、僕はこの作品を“ラブストーリー”だと思っていますから。
年齢も性別も超えた絆に救われる!

すべてを失い、孤独と絶望を味わっていたなかでもう一度希望を感じさせてくれたのは、そっと抱きしめてくれる人の温もり。他人と触れ合うことが難しい時期に生きているからこそ、映画が傷ついた心の癒しともなるはずです。
取材、文・志村昌美
魂を揺さぶる予告編はこちら!
作品情報
『この世界に残されて』
12月18日(金)より、シネスイッチ銀座ほか全国順次公開
配給:シンカ
https://synca.jp/konosekai/
©Inforg-M&M Film 2019