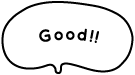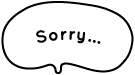志村 昌美
志村 昌美
「愛情がたくさんあることがいい親とは限らない」里親制度が抱える難しさ【仏映画】
『1640日の家族』

【映画、ときどき私】 vol. 506
アンナと夫のドリスが、母親を亡くした里子のシモンを受け入れて4年半。18か月だったシモンは長男と次男と兄弟のように成長し、いつだって一緒に遊びまわっていた。5人はにぎやかで楽しい日々が続くと思っていたが、ある日、激震が走る。
月に1度の面会交流を続けてきたシモンの実父エディが、息子との暮らしを再開したいと申し出をしてきたのだ。突然訪れた“家族”でいられるタイムリミットが迫るなか、彼らが選んだ未来とは……。
人権や児童福祉を重視し、幅広い取り組みをしているフランスの現状を知ることができる本作。今回は、実際に里親制度を経験したこちらの方にお話をうかがってきました。
ファビアン・ゴルジュアール監督

子ども時代に、両親が迎えた里子と生活をともにした実体験をもとに本作を手掛けたゴルジュアール監督。そこから自身が学んだことや育児をするうえで大切なこと、そして里親制度に必要なものなどについて語っていただきました。
―幼少期に味わった里子との出会いとつらい別れは、監督のご家族みんなに影響を与えたそうですが、それによって監督の人生はどのように変わったと思いますか?
監督 僕にとっては、“映画監督になるための礎”となるような経験でした。というのも、「映画監督になったらこのストーリーを語るんだ」といった強い思いが自分のなかで生まれたからです。その後、22歳くらいのときに里子に関するシナリオを書いてみたもののうまくいかず、まずはほかの作品で経験を積むことに。そこでプロデューサーともいい関係を築けたので、本作を作ることができました。
―里子と一緒に過ごした経験を通して、一番描きたいと思ったものは何だったのでしょうか。
監督 それはいままでにどんな映画を作っていても感じることですが、僕がテーマとして描いているのは、人の感情について。やはりそれは、子どもの頃に感情を揺り動かされるような経験をしたことが大きいのだろうと自覚しています。
前作の『ディアーヌならできる』では、代理母の役割を務めた女性のエモーションが溢れ出るところでラストを迎えていますが、本作では最初からエモーションが溢れ出ている女性を描きました。僕にとって映画というのは、人間の感情を描く役割を果たしているのだと思います。
里親は距離感を保つのが難しいと感じた

―里親制度を目の当たりにしたことで、親子の在り方についても考えたと思いますが、育児をするうえで大切なものは何だと思いますか?
監督 僕にも5歳半の娘がいるのでよくわかりますが、子どもが生まれたことによって自分の人生は大きく変わりました。そんななかで、愛が不足することなく、溢れるほどの愛があるほうが親子関係においては大切なことだと確信しています。
ただ、愛情がたくさんあるからいい親であるとか、正しい判断ができるとは限りませんよね。愛が溢れすぎて過保護になる場合も、子どもが息苦しいと感じてしまう場合もありますから。そういった弊害もありますが、それが愛であると言えるのかもしれません。
―里親だった監督のお母さまがソーシャルワーカーから受けた唯一のアドバイスは、「この子を愛しなさい、でも愛し過ぎないように」だったとか。
監督 確かに、里親の場合は、愛してあげなきゃいけないけど、愛しすぎてはいけないという距離感を保つのは非常に難しいことだと思います。そのときに考えたのは、里親のように感情を職業的にコントロールするのは可能なのだろうか、ということでした。人によってはできるかもしませんが、僕個人としては、難しいと感じています。
母親と父親の立場の違いも見せたかった

―劇中では、愛情を抑えきれない母親に対して、冷静さを保つ父親も登場します。里子との距離感がそれぞれ違って描かれていますが、それは母性によるものなのか、それとも監督が実際にリサーチや経験から感じたことなのでしょうか。
監督 いまの質問にもあったように、それは母性でもあり、リサーチの結果でもあり、自分の母親の姿でもあり、それらすべてが含まれています。ただ、今回の作品で言うと、アンナがヒロインなので、彼女の目線で描くことを意識しました。実際、里親を仕事にしているのは女性のほうが圧倒的に多いと言われています。しかし、だからといって父親よりも母親のほうが愛情深いという意味ではありません。
本作では、シモンの母親が亡くなっていることもあり、アンナは余計に母親の代わりになろうとしてしまうところがあります。いっぽう、実の父親は存在しているため、アンナの夫であるドリスは自分を父親と同一化することがないのです。それだけでなく、彼は自分の家族に“嵐”が待っていることを予見していることもあって、愛情を溢れさせることなく、自分が家族を守るために距離を保つことを意識しています。そういった立場の違いというのも、本作のなかでは見せたいと思いました。
里親の存在は必要だが、改善すべき点が多い

―なるほど。まもなく日本では公開を迎えますが、日本に対してはどのような印象をお持ちですか?
監督 まだ訪れたことはありませんが、日本といえば新婚旅行で行こうかと話が出たこともあったくらい興味がある国のひとつ。実は、この作品と一緒に行けるのではないかと淡い期待を抱いていたのですが、コロナ禍でその夢が破れて残念に感じています。
日本に興味を持つようになった出発点はやはり日本映画ですが、なかでも好きなのは成瀬巳喜男監督です。いま一番好きな監督と言えるほど、最近になっていろんな作品を観ているところです。彼の作品に惹かれる理由は、感情を揺さぶるメロドラマの要素があること。いつか映画のなかの場所を体感できるように、スクリーンを通り抜けて日本にたどり着きたいと思っています。
―日本では親と暮らせない子どもたちに対して、施設養育から里親養育への転換を進め始めたところと言われていますが、里親制度を広めていくうえで欠かせないことや改善すべき点などがあれば、教えてください。
監督 里親制度が存在すること自体はいいと思いますが、システムに関してはまだ欠点のほうが多いように感じています。必要としている子どもの数は減っていないにも関わらず、残念ながら里親になろうという人が減っているのが現状。これはフランスに限ったことではなく、世界的に見ても、他者に対する寛容さが失われつつあるので、悲しいことだと思っています。
里親制度において問題を挙げるとすれば、まずは財源不足。そして、使命感の欠如です。里親になりたい人を増やすのは大事なことですが、現在はあまり選別することなく誰でもなれる状況なので、お金目当てだけでやっている人がいると言われることも……。そうならないためにも、財源を増やし、里親を養成する期間をしっかりと設ける必要があると思います。
新しい家族の在り方を考えさせられる

里親という制度を通して、親と子の間における愛の大切さと難しさを突きつける本作。演技初挑戦とは思えない子役が見せる繊細な表情をはじめ、フランスの実力派俳優たちによる見事な演技は、観る者の感情までも溢れさせてしまうはずです。
取材、文・志村昌美
心が震える予告編はこちら!
作品情報
『1640日の家族』
7月29日(金) TOHOシネマズ シャンテほか全国公開
配給:ロングライド
https://longride.jp/family/
️© 2021 Deuxième Ligne Films - Petit Film All rights reserved.