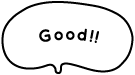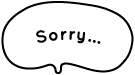志村 昌美
志村 昌美
「日本人は僕のアイドル」フランス人監督がいまの日本人に伝えたい思い
『東洋の魔女』

【映画、ときどき私】 vol. 435
1954年、大阪に本社を構える大日本紡績株式会社は、貝塚工場・女子バレーボール部を設立。監督に就任した大松博文は「鬼の大松」と呼ばれるほど、徹底したスパルタ式トレーニングで選手たちを指導していた。
設立から数年後には、日本国内の四大タイトルを独占。さらに、「回転レシーブ」などの秘密兵器を生み出し、世界選手権でも優勝を果たす。「東洋の魔女」と恐れられた彼女たちが、当時の秘密をいま打ち明ける……。
女子バレーボールの歴史を語るうえで、欠かすことができない東洋の魔女たちの存在。そこで、日本人でも知ることのなかった舞台裏に迫ったこちらの方にお話をうかがってきました。
ジュリアン・ファロ監督

フランス国立スポーツ体育研究所の映像管理部門で働きながら、スポーツと映画をつなぐ映像作品を数多く手がけてきたファロ監督。今回は、東洋の魔女たちとの撮影で得た真実や日本に対する思いについて、語っていただきました。
―10年ほど前に、女子バレーボール日本代表チームの映像を見たことが本作の始まりということですが、最初に映像を見たときはいかがでしたか?
監督 いまでは多くの選手がしていることですが、あそこまでハイレベルなトレーニングは60年代では非常に珍しいことではないだろうかと感じました。体格の大きなヨーロッパの女子選手でも、あれほどの厳しい練習はおそらくできなかったでしょうね。そういう意味でも、女子バレーボール界において、東洋の魔女たちはパイオニア的存在だと思いました。
―映像を見たとき、監督のなかで感覚的なつながりもあったとか。
監督 確かに、神経回路がパッとつながるような感じはありました。それは子どもの頃にバレーボールを題材にした日本のアニメを見ていたので、構図や選手たちの美しさが僕のなかで一致したのだと思います。そして、その瞬間に何かがひらめき、この映画を作ることにしました。
―いまの時代に、東洋の魔女たちの真実を伝えることには、どういった意味があるとお考えですか?
監督 昔に比べると、女性の地位も上がったので、近年は激動の時代と言えるかもしれませんが、それでもいまだに学者や政治家をはじめとする著名人や主要なポストにおいて、男性のほうが優位であることは変わっていないのではないでしょうか。そんななかで、男子選手でも難しい258連勝という偉業を成し遂げた東洋の魔女たちに光を当てたいと考えたのです。
バレーボールは世界的に見てもポピュラーなスポーツですし、彼女たちはいまでも美しくて生き生きとしているので、その姿を多くの人に見せたいと思ったのもこの作品の原動力になりました。
今回は、監督と選手の関係性を掘り下げたかった

―大松監督に関しては、賛否あったようですが、監督自身はどのような人物だと捉えましたか?
監督 確かに、「鬼の大松」と言われているくらいですからね。怖いイメージはありました。でも、だからこそ監督と選手の関係性をより掘り下げていきたいと思ったのです。ただ、暴力やセクハラの犠牲者というのはなかなか自己表現ができないものなので、もし彼女たちがそう感じていたのであれば、非常にデリケートな問題になることはわかっていました。
そういったこともあって、今回はナレーションを入れずに、彼女たち自身の言葉で語ってもらっています。とはいえ、もし話しにくいと感じていたらどうしようという不安もありましたが、意外にも彼女たちは「大松監督は、自分たちが会った監督のなかで一番優しい監督。本当に鬼みたいだったと思いますか?」と言って笑っていました。
―とはいえ、練習風景を見るとかなり過酷なので、選手は監督に対して反発しているのかと思っていましたが、みなさんが大松監督を父親、もしくは彼氏のように慕っていたとおっしゃっていて驚きました。
監督 そうですね。ただ、なぜ彼女たちがそう思っているかというと、強くなるために厳しい練習をするのは当然だと感じていたからなんです。彼女たちも納得したうえでトレーニングを受けていましたし、監督と選手がお互いに信頼し合っていたからこそ、健康的な関係を築けていたんですよね。それは話を聞いて、初めてわかったことです。
ただ、海外のメディアでは批判的な見方もあり、特にアメリカの記者からは「女性にそんなことをしてはいけない」といった意見があったと聞きました。でも、僕からすると、「男性ならOKだけど、女性だからダメ」というのは女性の尊厳を汚しているように感じて、苛立ちを覚えたことも。なぜなら、その記者の言葉の裏には、「女性は家で家族の世話をしていればいい」といった意図があったからです。
僕は女性でも高いモチベーションと熱意を持ち、納得しているのであれば、自分たちが望むトレーニングを受ける権利があると思っています。つまり、犠牲者かどうかは本人たちの意志次第。周りがそれを否定することはできません。
アーカイブにはなかった面白い発見があった

―今回の彼女たちの証言がなければ、多くの人が誤解していたままだったかもしれませんね。
監督 そうですね。ちなみに、60年代のフランス人女性は日本人女性に比べると、ほとんどの権利を持っていたと言えますが、「すべてにおいてほどほどに」が暗黙の了解。たとえば、お酒は飲んでもいいけど酔っ払うほど飲んではいけないし、スポーツもしていいけれどあまり激しいのはダメといった感じだったので、東洋の魔女たちほどの過酷なトレーニングは許されていませんでした。
その理由としては、「女性は子どもを産むためのエネルギーを残しておかなければいけない」という社会の見方が強かったから。だからこそ、僕は東洋の魔女たちの真実を立証したいと思いました。
―日本で撮影するなかで、思い出に残っていることについて教えてください。
監督 本作では彼女たちの日常も見せたかったので、撮影場所はそれぞれ好きなところを選んでもらいました。普段通りにしてもらったからこそ、これまでのアーカイブでは見せられない面白い発見もできたと思っています。回転レシーブがダルマや起き上がり小法師からヒントを得て生まれたものだった、というのもそのひとつですね。
あと、今回は是枝裕和監督作で知られている山崎裕さんが撮影監督を務めてくださったのですが、東洋の魔女たちと同世代ということもあり、彼女たちから聞けなかった話を山崎さんから聞けたのも興味深かったです。ちなみに、山崎さんは若い頃に東洋の魔女の一員である宮本恵美子さんに憧れていたのだとか。ただ、残念ながら体調の関係で電話での取材しかできなかったので、山崎さんは「もう少しで“昔の恋人”に会えそうだったのに」とがっかりされていたのが印象的でした(笑)。
日本人には、自分を過小評価してほしくない

―撮影ではさまざまな日本人と触れ合ったと思いますが、どのような印象を受けられましたか?
監督 日本に滞在している間は、本当に驚くべきことにたくさん出会いました。そのなかでもフランス人から見て不思議だと思ったのは、日本のみなさんがいつも自分たちの価値を過小評価しているところがあること。非常に謙虚で、自分を表に出さないからというのはありますが、ときには海外を理想化し、自分たちは劣っていると感じているようにも見えました。
おそらく、戦後にアメリカがモデルとなっていたことで、「欧米がベストなんだ」という考えが根づいているからかもしれませんが……。でも、日本には景色や工芸品、和食など、繊細で美しくて素晴らしいものがたくさんあるので、僕からすると日本のみなさんこそが“僕のアイドル”なんですよ。日本のアニメはもはや世界の文化になっていますし、ほかの国からすると日本はモデルになっている部分もあるので、そんなふうに思わないでほしいです。
―ありがとうございます。今後もまた日本をテーマにした映画を作る可能性があれば、どんなことを取り上げたいか教えてください。
監督 僕の場合、最初にテーマを探してからアーカイブを探すのではなく、アーカイブを見ているなかで火花が散るようなインスピレーションを受けたものを題材にするという仕事の進め方なので、いまはまだわかりませんが、日本にはまだまだ興味はありますよ。
実はいま、片目だけ入れたダルマを持っていて、また日本に行くという目標が達成できたら、もう片方の目を書こうと思って大事に置いてあります。でも、次は仕事ではなく、観光で行けたらいいですね(笑)。
バレーボール界が変わった瞬間の目撃者となる!

アニメーションを駆使した演出と新しい視点で、通常のスポーツドキュメンタリーとは一線を画す本作。60年の時を経て明かされる偉業の裏側と東洋の魔女たちの真実に、胸が熱くなる1本です。
取材、文・志村昌美
エネルギーに満ちた予告編はこちら!
作品情報
『東洋の魔女』
12月11日(土)より、渋谷ユーロスペースほか全国順次公開
配給:太秦
https://toyonomajo.com/
©UFO Production、©浦野千賀子・TMS