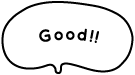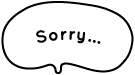志村 昌美
志村 昌美
ただの黙とうが国への反逆とみなされ…戦後を生きた学生の壮絶な実話
衝撃の実話『僕たちは希望という名の列車に乗った』!

【映画、ときどき私】 vol. 229
1956年、東ドイツの高校に通っていた青年テオとクルト。ある日、列車に乗って訪れた西ベルリンで、自分たちの国と同じくソ連の影響下に置かれていたハンガリーのニュース映像を目の当たりにする。
自由を求めて立ち上がるハンガリー市民に共感した彼らは、授業中に2分間の黙とうをすることをクラスメイトたちに提案するのだった。純粋な哀悼の気持ちで実行した彼らだったが、東ドイツでは「社会主義国家への反逆」とみなされ、国家を敵に回す一大事へと発展してしまう。彼らを待ち受ける未来とは……?

本作は、ディートリッヒ・ガルスカ氏の実体験を綴ったノンフィクションをもとに映画化された注目作。そこで、完成までに緻密なリサーチを重ねて作り上げたこちらの方にお話を聞いてきました。
ドイツ映画界の気鋭ラース・クラウメ監督!

前作『アイヒマンを追え! ナチスがもっとも畏れた男』でも高い評価を受けているクラウメ監督は、今回も実話に挑戦。制作過程で感じた思いや自身の若い頃の経験などについてなどを語ってもらいました。
―未成年の若者たちがたった数分間の黙とうを捧げただけで、ここまでの政治的弾圧を受けたという事実に観客は衝撃を覚えると思いますが、監督が最初にこの話を聞いたときはどのように感じましたか?
監督 僕が初めて知ったとき、実はあまりショックはなかったんだ。というのも、ドイツの歴史にはもっと恐ろしい出来事もたくさんあったから、ドイツ人としては正直言って「そういうこともあるよね」くらいの感じだったよ。実際、ドイツ中で作品を見せて話を聞いてみると、「自分の学校や職場でも似たことが起きました」といった反響がたくさんあったくらい。
ただ、僕にとって興味深く感じたのは、学生たちが連帯したこと。こういう経験をしたとみなさん話してはいたけれど、劇中の学生たちのように独裁的な体制に対して立ち上がったという方がとても珍しいことだったんだ。たから、僕もこのストーリーのなかでも、その部分が一番強いところだと感じているよ。
観客のリアクションは面白いものがあった

―ドイツでは歴史的な実話を描いた作品は数多くありますが、1950年代はあまり注目されて来なかった時期。それにも関わらず、監督は前作と本作でいずれもこの年代を描いていますが、その理由を教えてください。
監督 映画ではなかなか50年代が描かれることがなかったからこそ、どちらの作品もドイツの観客のリアクションはとてもおもしろいものがあったよ。というのも、戦後のドイツが東と西それぞれでどのように社会再建をし、どうやって政治的な秩序を作り直したのかということが知られていなかったからなんだ。
それがこの2作品のテーマでもあるけれど、特に今回は生徒たちが大人の社会の決まりみたいなものを破ったことがみなさんに響いた部分もあったと思うよ。
今回は批判を受けることもなかった

―本作の舞台は東ドイツですが、監督は西ドイツの出身。リサーチをされるうえで、これまで西ドイツから見て感じていた東ドイツと印象が変わることもありましたか?
監督 社会における「個」の概念が違うというのは、非常に興味深かったところかな。というのも、やはり自分は西側で育っているから資本主義的な考え方にのっとった「社会における個人とは何か?」という考え方に慣れているけれど、劇中で描かれているのは社会主義国としての社会。
実際、ドイツが分断されたとき「東ドイツは社会主義国になりました」と突然言われて、東ドイツの人たちは「自分で選んだわけではないけれど、新しい政治的体制がそういうものであれば個人よりも社会という集合体に重きを置くやり方を試してみよう」と思っていたんだ。僕はリサーチをするまでは、彼らがそんな葛藤を持ちながら向き合っていたことは知らなかったから、そういう姿を見ることができたことは一番の驚きだったよ。
ちなみに、東ドイツの題材を西ドイツ出身の監督が作ると、批判を受けることもけっこうあるんだけど、原作者のディートリッヒさんと密にコラボレーションしていったおかげか、今回はそういった声を聞くことはなかった。それだけ旧東ドイツの人たちにとっても、リアルに感じてもらえたということじゃないかな。
タイムレスなものを目指していた

―本作では、ドイツが恐ろしい過去から新しい未来に移行しようと模索する話であり、世代間にある価値観の違いといったものなどが描かれていますが、いまの時代にそういったことを描きたかったのはなぜですか?
監督 すべては『アイヒマンを追え! ナチスがもっとも畏れた男』から始まっていることでもあるけれど、どちらの作品にも共通している映画のモチーフとしては何かに対する反抗心や抗議すること。ナチス政権のあとにどんなふうに社会を再建していったのかということについても、深く洞察できる内容だと思ったんだ。
ただ、歴史的な物語をそのまま描くだけでは単なる歴史の授業のようになってしまい、映画にするまでもないよね? だからこそ、そこに人間的な価値観や言論の自由、さらには連帯することという普遍的なものをプラスして、タイムレスなものを目指したんだ。
監督が自らを投影したキャラクターとは?

―まさにその“普遍性”という部分がいまの観客にも響くところであり、「自分だったらどうするか?」と考えさせられました。監督も共感できるような自分に近いキャラクターなどもいたのでしょうか?
監督 僕の分身と言えるのはテオ。実は、僕も17歳くらいのときに政治的な抗議活動に参加していたことがあるんだけど、その理由はそうすれば好きな女の子が僕に関心を持ってくれると思ったから(笑)。本当は政治には興味がないサッカー青年だったんだ。だから、劇中のエピソードには僕の体験から来ているところもあるんだよ。
自分だったらどうするかは、「彼らと同じように連帯感を持って立ち上がっただろう」と言うのは簡単だけど、やっぱり実際にその場にならないとわからないと思うよ。たとえば、頭でよくないとわかっていることでも、僕もスマホを使いまくってしまうし、必要のないものを消費してしまうことも多いからね。
数日間で自分の未来像が変わったことがある

―本作ではたった2分が彼らの人生を変えてしまいますが、監督にとってもひとつの出来事で人生や考え方が変わったしまった経験があれば教えてください。
監督 もちろん、人生においてそういう瞬間はたくさんあったよ。彼らと同じくらいの年齢の頃、僕は写真家になりたいと思っていたんだ。そんなとき、ベルリンの壁が崩壊して、ルーマニアから来た先生にルーマニアの状況がよくないことを教えてもらい、学校で寄付を募って、それをトラックに積んでみんなで運んだことがあった。
僕は記録係として写真を撮っていたんだけれど、そこでルーマニアの人たちがどんな状況で暮らしているのかを初めて自分の目で見て、すごく心に刻まれたんだ。それがフォトジャーナリストになりたいと思うようになったきっかけ。たった数日間の滞在だったにも関わらず、そこで自分の未来像が完全に変わったんだけど、そういった瞬間は誰にでもあるものだと思うよ。
希望を胸に未来へ走り出す!

日本人にとってはあまり知ることのできない歴史的背景を舞台にしているものの、描かれているのは人として正しい行いとは何かという時代を超えた価値観や仲間との絆。実話だからこその心揺さぶる展開と、それを体現する若手俳優たちの熱演からも目が離せない1本です。
胸がザワつく予告編はこちら!
作品情報
『僕たちは希望という名の列車に乗った』
5月17日(金)、Bunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町他全国公開
配給:アルバトロス・フィルム、クロックワークス
©Studiocanal GmbH Julia Terjung
http://bokutachi-kibou-movie.com/